十二月の組香
夜の冬景色から本当の月を探すという組香です。
聞き間違いの様子が香記に反映されるところが特徴です。
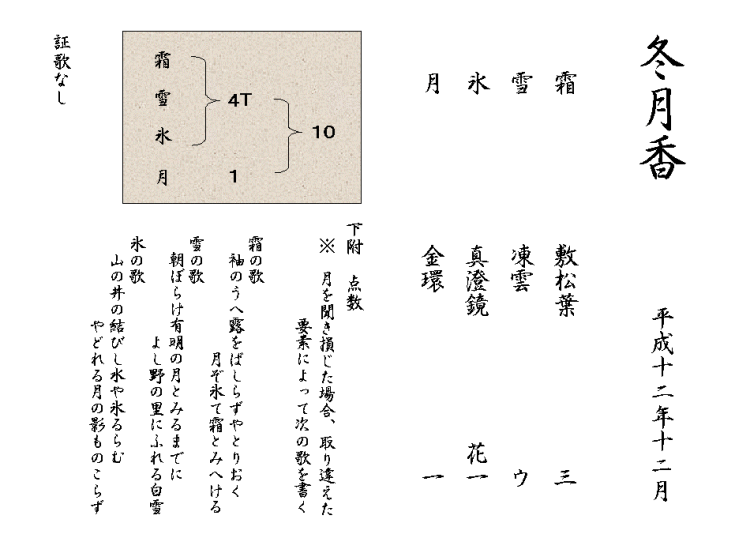
|
|
説明 |
|
香木は4種用意します。
要素名は、「霜」「雪」「氷」と「月」です。
香名と木所は、景色のために書きましたので、季節等に因んだものを自由に組んでください。
「霜」「雪」「氷」はそれぞれ4包(計12包)作り、そのうち1包ずつを試香として焚き出します。
残った「霜」「雪」「氷」の各3包(計9包)に「月」1包を加えて計10包を打ち交ぜます。
本香は、10炉焚き出します。
答えは、要素名を出た順序に10個書き記します。
下附は、「月」を聞き誤った場合にのみ「月」と取り違えた要素に因んだ和歌を1首書き添え、その下に点数を書き込みます。
全部当たりは「皆」となり和歌はありません。「月」を聞き当てて、その他に間違いがある場合も点数だけ記載します。
私は、冬の月が大好きです。
冬の月は、青白く冴え冴えとして、ときに月暈(げつうん)を従え、晴天の夜空は、群青色に深く、遠く、満天の星をはらんで、「いつUFOが出てくるのか?」と思われるほどミステリアスです。また、周りに目をやると、キラキラと小さな輝きを放つ
「霜」や辺り一面を淡く照らし出す「雪」、そして万象を反映する「氷」と月の光が様々に変化して溢れています。(こんな夜、私の脳裏には、ドビュッシーの「月の光」と萩原朔太郎の「月に吠える」の情景が浮かんできます。)さて、今月の組香は
「冬月香」です。「月」と言えば「秋」と相場が決まっているような感じですが、ここでは、月の光と「霜」「雪」「氷」という水の化身 が放つ光を結びつけて、「冬景色の中に本当の月を探す」冬の組香としています。組香の構造自体は、最も基本的な
「有試十答えは、要素名を出た順序に書くのですが、
この組香の特徴は「下附のしかた」にあります。普通の「有試十下附する和歌をご覧ください。
は、「袖の上の露を知らずにそのまま留まっていたら、月が凍ってしまって霜にみえたよ。」(新続古今和歌集 前大納言為定)
霜の歌
雪の歌
氷の歌
どの歌にも共通して言えることは、
「月を何かと見間違った、または月が何かに見えた」ということではないでしょうか。少なくとも霜の歌と雪の歌はご賛同いただけるものと思います。「氷の歌」は、(おそらく心変わりか何かをした女性への失恋の歌なのだと思いますが)「月が見えなくなってしまった」と言っており、氷に月が映っている情景を詠んだ歌ではありません。これでは、話の辻褄が合わなくなりますから、ちょっと調べてみましたところ、「山の井のむすびし水や結ぶらんこほれる月の影もにごらず」(土御門院百首)という歌がみつかりました。この歌では、「月の姿が濁らないほど凍った」と氷に月が映っている情景が詠まれています。この歌を氷の歌の異本同歌と仮定すると、証歌のテーマは一致するのですが・・・曲解でしょうか?しかし、出典不明の
※ 証歌を書き写す際に「土御門院百首」の底本が違っていれば生じそうなことですが、いずれ、根拠はないことなので、参考意見とさせていただきます。
話が脇道に逸れました。<m(__)m>
この組香のテーマは、
「霜の輝きも、雪の薄明りも、氷の反映もある景色の中から月の光を見出す」ことだと思います。しかし、この組香で作者が一番心を砕いた趣向はおそらく「月の見紛い方」によって組香のテーマとその情景を成立させることだったと考えられます。そのため、作者の意を汲む香組者は連衆のレベルに応じて、判別の難易度を調整しなければなりません。簡単にすれば「四種香」や「有試十誤りにこだわった組香には、「関守香」のように絶対に誤った答えを書かなければならないというルールのものもあります。また、通常の香席では、最初から「全部答えを間違えるよ。」と宣言し、全問不正解すると最も高位となる「無太郎聞き」(むたろうぎき)というルールもあります。「誤りがあって尚更楽しい」という香席は、最も高尚な遊びの世界と言えましょう。
冬は、月も星も冴え冴え・・・天体観測のシーズンです。
暖かくして夜空を望み「月に吠えて」みてはいかがでしょうか。
Marry Chiristmas & Happy New Century!
組香の解釈は、香席の景色を見渡すための一助に過ぎません。
最も尊重されるものは、皆さん自身が自由に思い浮かべる「心の風景」です。
![]()
