十一月の組香
時雨を題材とした最もシンプルな組香です。
庵の屋根に落ちる木の葉と時雨の音を聞き比べてみてください。
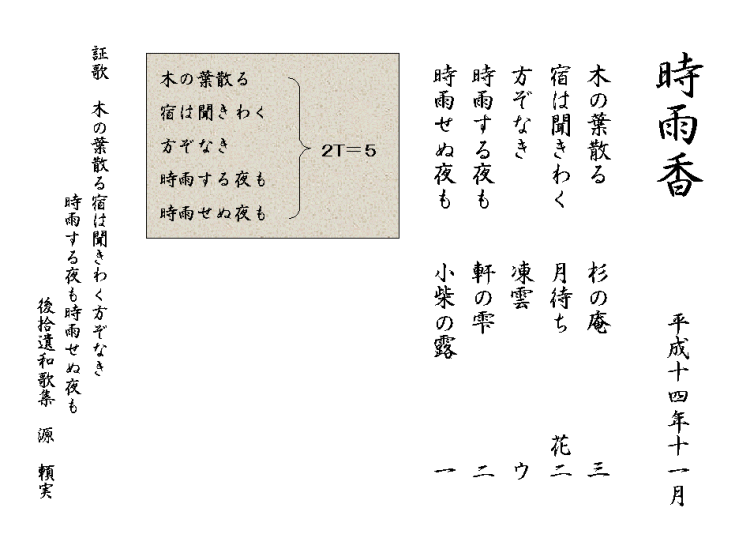
|
|
説明 |
|
香木は、5種用意します。
要素名は、「木の葉散る」「宿は聞きわく」「方ぞなき」「時雨する夜も」「時雨せぬ夜も」です。
香名と木所は、景色のために書きましたので、要素名に因んだものを自由に組んでください。
「木の葉散る」「宿は聞きわく」「方ぞなき」「時雨する夜も」「時雨せぬ夜も」は、それぞれ2包(計10包)作ります。
そのうち各1包ずつ(計5包)を試香として焚き出します。
残った「木の葉散る」「宿は聞きわく」「方ぞなき」「時雨する夜も」「時雨せぬ夜も」各1包ずつ(計5包)打ち交ぜます。
本香は、5炉焚き出します。
答えは、要素名を出た順に書き記します。
下附は当れば「皆」、その他は点数で書き記します。
朝晩の冷え込みに目覚めることが多くなり、初霜の冴えた朝がもう直ぐ到来と言ったところです。朝日に照り出される煌びやかな霜柱の輝きは、冴え冴えとして初冬の寒さを忘れるほど美しい風景ですね。
先日、秋田を訪れた際に「時雨」に遭いました。大粒の冷たい雨が突然降ったため、最初は雨宿りしていたのですが、10分過ぎでも治まる気配がないので、「え〜い!ままよ。」とばかりにアーケードの端からホテルの玄関までびしょ濡れで走り出しました。しかし、走り出すのはスーツ姿の男性ばかり、逃げ帰ったホテルの窓から見ていると、「秋田人」と思しき方々は携帯メールなどしながら座り込み、一向に動こうとしないのです。結局、降り始めから15分ぐらいで雨は上がり、彼らはまるで何事もなかったように歩み出しました。そのときに「あぁ、これが天気の変わりやすい日本海側の条理かぁ。」とようやく気づいた訳です。この土地の人と同じように時節と雲行き、降り方などから判断して「時雨」であるという認識があれば、焦ることなく待つことができたわけですね。「自然の顔色を伺い、対話しながらしなやかに生きる」里人の知恵を思い出させられました。
今月は、晩秋の定番「時雨香」(しぐれこう)をご紹介いたしましょう。
この組香の証歌「木の葉散る・・・」は、「(風が吹き)木の葉が時雨のように舞い落ちるこの家では、時雨の音なのか落葉の音なのか聞き分ける術もない。時雨が降る夜も降らない夜も・・・」という意味です。これは、源頼実(みなもとのよりざね)の作とされ、後拾遺和歌集をはじめたくさんの歌集に掲載されている秀歌です。『袋草紙』によれば、この歌は西宮広田社で詠まれましたが、当座は誰も驚きませんでした。後日、頼実がいつものように住吉に参詣して「秀歌を得られるように」と祈願したところ、夢に神が現われて「もう秀歌は詠み終えた。あの落葉の歌がそうではないか。」とのお告げがあり、その後、この歌は秀歌の誉れをほしいままにしたということです。
作者の源頼実は、正四位下美濃守頼国(よりくに)の息子として1015年に生まれました。親族には、叔母の相模、叔父の頼家、弟の頼綱・国房・師光ら勅撰集歌人が名を連ねています。源師房の土御門邸に頻繁に出入りし、1038年から師房主催歌合等に出詠しています。住吉に参詣して秀歌一首と引き換えに命を差し出す祈請をしたなど、歌道執心の逸話が前述の『袋草紙』や『今鏡』等に残されています。歌風は、田園や山村に題材を求めた叙景的なものが多く、藤原範永・平棟仲・藤原経衡・源頼実・源頼家・源兼長ととも「和歌六人党」の一人として精力的に歌作に励みました。勅撰集では後拾遺和歌集に初出し、晩年には家集『頼実集』を編纂しますが、「其の身六位なる時夭亡す。」との神のお告げのとおり(?)1044年に三十歳の若さで亡くなってしまいます。
まず、時雨(しぐれ)について理解を深めてもらうことといたしまょう。
「時雨」・・・は主に晩秋から初冬にかけての季節に断続的に降っては止む通り雨のことです。時雨の語源は「すぐる(過)」から来ているとも言われており、特に11月は時雨が多いので、別名「時雨月」と言います。「晩秋の憂いに満ちた夕暮れに、降り始めたと思ったらいつの間にか止み、止んだかと思うとまた降り始める。何となく身にしみる雨が紅葉を散らし、落葉を濡らす。」・・・こんな情景は、情趣を重んじる中古の人々に特別な感情を芽生えさせるのに好適だったのでしょう、時雨を織り込んだ歌は数知れず存在します。時雨を冠した文化遺産には、藤原定家の閑居と伝えられる「時雨亭(しぐれのちん)」をはじめ、豊臣秀吉の茶室「時雨亭(時雨亭)」もあり、芭蕉の忌日10月12日は、その季節から「時雨忌」と呼ばれます。また、時雨は、晩秋から冬に限ったものでもなく、広義には季節により春時雨、夏時雨、秋時雨と使い分けされ、時間帯により卯の時雨、夕時雨、小夜時雨などの言葉もあります。更に、雨とは直接関係のない蝉時雨、虫時雨、落葉時雨、木の葉時雨、川音の時雨、時雨羹、時雨煮、時雨饅頭など語彙も多く、涙のこぼれそうな気持を「時雨心地」、涙がこぼれてしまったのを「袖時雨」など心象を表す言葉にも用いられています。
次にこの組香は、証歌である「木の葉散る・・・」の歌を、句ごとに5分割してそれを要素名に据えただけというもっともシンプルな構造で作られています。この手法は、最も創作し易いため「這花香」や「萬歳香」など多くの組香に例が見られ、作香の基本とされています。しかし、それだけに組香の精神的支柱である証歌の役割が多くの比重を占めますので、作者はしっかりと吟味した秀歌を選ばなければなりません。一方、連衆も証歌に対する深い解釈と心象風景の形成をあらかじめ行い、十分に証歌の世界を味わうことが重要となってきます。
要素名は証歌の各句なので、これをシャッフルして焚き出すことでそれぞれの句がランダムに並んで、景色の違った七五調の歌に生まれ変わります。同様の形式を取る組香は、この景色の微妙な違いも聞香の結果とともに味わう趣向となっています。しかし、この組香の証歌については、確かに秀歌ですが要素名の元歌とするには、若干の支障があったように思えます。それは、「(宿は)聞きわく方ぞなき」という一文を2つの句に分け「宿は聞きわく」「方ぞなき」としたために、ランダムに接続すると意味の通らない場合が出て来るからです。例えば「木の葉散る方ぞなき時雨する夜も時雨せぬ夜も宿は聞きわく」(木の葉の散るところもない。時雨の降る夜も時雨降らない夜も宿は(それを)聞き分ける)のようにちょっと逆説的な意味にもなる可能性もあります。その点「這花香」の「難波津に・・・」や「萬歳香」の「君が代は・・・」は各句がそれぞれ独立していて、意味合いも似通っており、シャッフルしても証歌全体の主旨は変わりません。
さて、「これでは、あまりに簡単だ」という方のために、別の「時雨香」をご紹介しましょう。
こちらは、要素名を句とせず、単に「一」「二」「三」「四」「五」と匿名化します。
各要素は、各2包ずつ(計10包)作ります。
作った10包を「一」「二」「三」「四」「五」、「一」「二」「三」「四」「五」と2結びにします。
試香は無しで、最初の1結びを打ち交ぜて5炉焚き出します。(A段)
最初の5炉の出た順に従い、もともとの要素名は無視して「一」「二」「三」「四」「五」と付番をします。これを「本座の名目」(ほんざのみょうもく)と言います。
次ぎの1結びを打ち交ぜて5炉焚き出します。(B段)
B段については、A段で付番した本座の名目に従って、同香と判断した香の番号で答えます。
すなわち、A段の答えは全員「一」「二」「三」「四」「五」です。B段はそれに対応した同香の番号、例えば「三」「一」「四」「五」「二」というようになります。
この形式は、一見複雑そうに見えますが、A段⇒「シャッフルされた試香」だと思えば大差はありません。どちらの組香も「時雨する夜」と「時雨せぬ夜」の2つに組香の舞台を分け、「それぞれの夜に聞き耳を立てて、木の葉の音か時雨の音か聞き分ける」ことが趣向となっているのだろうと思います。
これらの組香の景色には、時雨が降る、降らないにかかわらず「木の葉」が散っていると考えていいでしょう。そのため、「時雨が降る夜の木の葉」「時雨が降らない夜の木の葉」という景色の味わい方もあると思います。組香の主役は「時雨」ですが、「木の葉=落葉」も脇役として大きな取扱がなされてしかるべきと考えます。この組香は、試香やA段が「時雨せぬ夜」で各要素を聞き分け易く作ってあり、あらかじめ「木の葉」の音を聞き覚えてから、本香やB段の「時雨する夜」で本当の聞き分けをさせるという趣向ではないかと思います。
秋になり、大陸性高気圧の勢力が大きくなると、北西季節風が大陸の冷たい空気を運んできます。その頃、日本海はまだ海面温度が暖かいので、海面に接した風は下から暖まり対流が始まります。対流は雲を生み、小さな雲が列になって到来し、陸地で上昇します。この縞になった雲が時に雨を降らせ、時雨となるのです。このことさえ知っていれば、大粒の雨にスーツを濡らすこともなかったでしょうに・・・。
秋嵐で落ちた毬栗が松の枝元でマツボックリのように居座っている。
おもしろい風景をみました。
今夜は、時雨も降らないし、木の葉も落ちないと思っていると
翌朝には初雪や初霜が降りているのでしょうね。
組香の解釈は、香席の景色を見渡すための一助に過ぎません。
最も尊重されるものは、皆さん自身が自由に思い浮かべる「心の風景」です。
![]()
Copyright, kazz921 All Right Reserved
無断模写
・転写を禁じます。