三月の組香
後鳥羽院の三躰和歌をテーマとした組香です。
七首の引歌の景色を味わいながら聞いてみましょう。
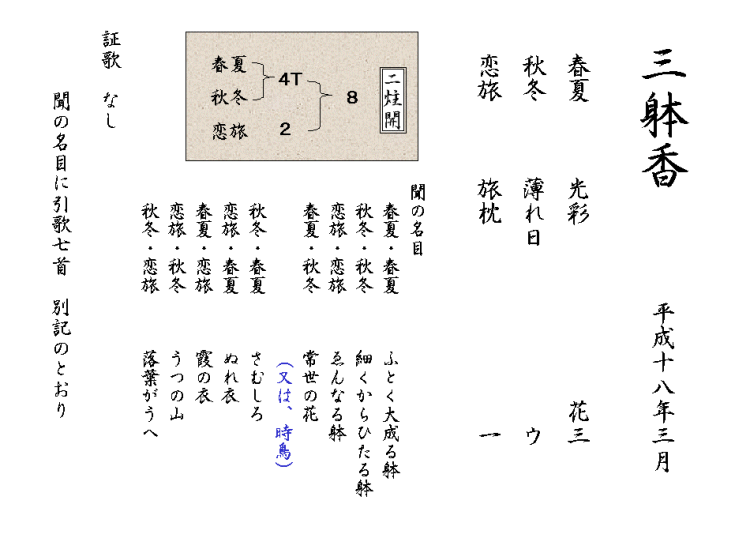
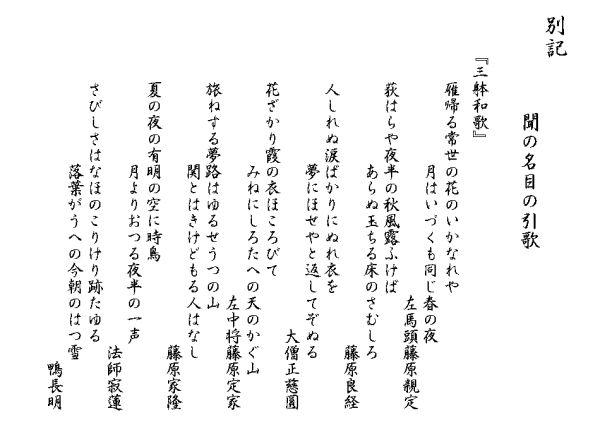
※ このコラムではフォントがないため「
|
|
説明 |
|
香木は、3種用意します。
要素名は、「春夏(しゅんか)」「秋冬(しゅうとう)」と「恋旅(れんりょ)」です。
香名と木所は、景色のために書きましたので、季節や組香の趣旨に因んだものを自由に組んでください。
「春夏」「秋冬」は各4包、「恋旅」は2包作ります。(計10包)
「春夏」「秋冬」のうち各1包をそれぞれ試香として焚き出します。(計2包)
残った「春夏」「秋冬」各3包に「恋旅」2包を加え、打ち交ぜて焚き出します。(計8包)
本香は、「二*柱開(にちゅうびらき)」で8炉廻ります。
※ 「二*柱開」とは、「香炉が2炉廻る毎に回答し、香記に記録する」やり方です。
以下8.〜10.を4回繰り返します。
連衆は、2炉ごとに要素名を聞き合わせ、「聞の名目(ききのみょうもく)」と見合わせて香札を1枚打ちます。
香元は、2炉ごとに香包を開き、正解を宣言します。
執筆は、各自の回答を香記に書き記し、当ったものに合点を掛けます。
下附は、点数で書き記します。 (8点満点)
「桃花春風に笑う」・・・残雪の中にも春風の香りが漂う花笑みの季節となりました。
冬篭りが終わり、生命の息吹が満ちて、すべてが陽極に向かって歩みを始める3月に私は生まれました。東大寺のお水取りのニュースを見ると、まるで「行く年来る年」の除夜の鐘のように「また一年生きたんだなぁ。」と感じます。私自身、「季節的には5月が一番好きだ」という話は以前から書いているとおりですが、やはり「誕生月」というものは特別です。「春っ子」だから、特に季節感と同調するのかもしれませんが、一年という時の廻りの中で、自分のバイオリズムが一旦原点に戻るような、「一陽来復」の感を覚えざるを得ません。
とはいえ、精神や肉体が新しくリセットされる訳ではないので、バイオリズムのサインカーブは振幅を広げたり、全体的に右上がりに波打ったりすることはなく、むしろその逆となります。人生を香席に例えると、「最後の香炉が廻り始めた頃合い」でしょうか、そろそろ「下り坂」というものが見えて来て、「香満ちました。」と達成感に満ちた気持ちで香席の終焉を迎えるための思念も廻りはじめます。まだまだ、一休さんの「冥土の旅の一里塚・・・」ほど悲観的ではありませんが、脳が「無限の未来」を想定しづらくなる老変にかかって来たことは間違いないようです。今年も「めでたくもあり、めでたくもなし。」と淡々と歳を取り「うれしい」という気持ちは、流石にどこからも湧いて来ないといったところが正直な感想・・・まっ、これが「人生の秋」なんでしょうね。一休さんのドクロの杖には「人間は必ず死んで、こんな姿になるのだから一生懸命生きようじゃないか」というメッセージが込められていました。人間、長く生きていますと死ぬことを忘れてしまって、いつまでも生きていられるような気になりますが、誰しも明日生きていられる保証はどこにもないのが「現(うつつ)」というものです。刹那の積み重ねを悔いを残さず、大切にしたいものですね。
身体に較べれば、心と言うものは自由なもので、「春に人生の秋を感じ」、それでも「秋に恋し」、それでも「春に別れ」、それでも「旅に春秋を愛で」、そして「いつも恋に旅する」・・・千変万化で時節によって陰陽が定まることもないようです。2度と廻らない四季があるとすれば、それは「人生の四季」でしょう。「まだ初秋」だとは思っていますが、せいせい長く楽しみたいものです。
今月は、「六儀香」に続き、和歌の風体をテーマにした「三躰香」(さんたいこう)をご紹介いたしましょう。
「三躰香」は、『三十組之目録』、『御家流組香集(礼)』、『香道真葛原(上)』等に掲載のある組香です。『三十組之目録』には、「後水尾院様御撰 和歌三躰香」と記載がありますので、当時、殿中でも楽しまれた由緒正しい組香であることがわかります。今回は、3冊とも大同小異で見解は統一されていますので、もっとも記述内容が詳しい『三十組之目録』を出典としてご紹介いたします。
まず、「和歌三躰」とは、いったい何なのでしょう?昨年「三暁香」の際にもご紹介しましたとおり、「三シリーズ」には、枚挙に暇が無く「三友(松、竹、梅)」、「三教(儒、仏、道)」、「三才(天、地、人)」、「三徳(智、仁、勇)」、「三道(儒、仏、神)」・・・等たくさんの名数が存在しています。しかし、名数辞典には「三体」⇒「書体・生け花における真、行、草」。「猿楽における老体、女体、軍体」程度しか掲載がありません。
和歌の「三躰」を解明しない間は話が進まないため、いろいろと考えを廻らせてみましたら、『三十組之目録』に「三躰の和歌」と称して7首の和歌が記載されていました。これらが掲載されている歌集を一つ一つ調べていきましたら、『三躰和歌』という歌集(歌会の記録)にすべて掲載されていることがわかりました。
『三躰和歌』は、建仁2年(1202)に後鳥羽院が「歌のさましれるほどをご覧ずべきため」と発起して給題し、2日後の「六首歌会」で和歌所に詠進、披露された和歌のことです。3月22日に行われた歌会では院をはじめ、藤原良経、慈圓、藤原定家、藤原家隆、寂蓮、鴨長明らの和歌所寄人たちが「春」「夏」「秋」「冬」「恋」「旅」を歌題としてそれぞれ6首ずつ詠進しています。招請を受けていた寄人のうち、藤原有家と藤原雅経は辞退したため、歌集には7名×6首=42首が掲載されており、そのうち5首は、後鳥羽院が勅宣した『新古今和歌集』に掲載されています。伝本は数少なく、作者名順に編集したものと、課題順にまとめたものと2種類があり、文学史的には、新古今時代の審美的様式の精妙な解説例として、また、「定家十体」などの風体分類との関係からも重要な資料とされています。
まず、『三躰和歌』における「三躰」とは、歌会の際に歌題となった「春」「夏」「秋」「冬」「恋」「旅」の6題を3種にまとめて「春夏」、「秋冬」、「恋旅」に配した「歌のさま」だということが、序文によって知ることが出来ます。
三躰和歌の序には・・・
|
・・・と書かれており、和歌の風体として「このように詠め」とあらかじめ指定されていたようです。そして、この「此二(このふたつ)」とまとめられた「春夏」「秋冬」「恋旅」の「三躰」が、組香の景色を構成する要素となります。
次に、この組香の構造は、和歌の定番である「季の歌」を「地の香」として扱い、「春夏」「秋冬」各4包のうち1包を試香として焚き出します。「恋旅」は2包作り「客香」とします。これは各要素を織り交ぜ、「季節の舞台」に「想いの景色」を載せていく趣向なのでしょう。このまま、普通の後開(のちびらき)にしてしまえば、答えは8つとなりますが、それでは、各要素が順不同に香記に入り混じってしまって景色が混乱するでしょう。そこで、この組香では、本香を「二*柱開き」として、連衆の心象風景を2つずつに区切って味わえるようにしてあります。さらに「聞きの名目」を用いることによって、それらの景色を一旦、国文学的に転化させ、香記には4つの歌言葉となって現れるようにしています。
この組香では、「晴なる会」以外では香札を用いず、手記録紙を各自4枚使用して「二*柱開」を行っていたようです。そのため「記紙一度々むつかしければ後開にても聞くなり。」とあり、1枚の手記録紙に4つの名目を一度に書いて提出しても良いことになっています。
さて、この組香には、二*柱開には付き物の「聞の名目」があります。8つの要素名から2つを取る組合せは9通りあり、それぞれに『三躰和歌』の序文や7首の和歌の1句が以下のとおり配されています。
| 香の出 | 聞の名目 | 引歌(詠人、歌番) | 分類 |
| 春夏・春夏 | 太く大成る躰
(ふとくおおいなるてい) |
「ふとくおほきによむべし」(序文) | |
| 秋冬・秋冬 | 細く涸びたる躰
(ほそくからびたるてい) |
「からびほそくよむべし」(序文) | |
| 恋旅・恋旅 | 艶なる躰
(えんなるてい) |
「ことに艶によむべし」(序文) | |
| 春夏・秋冬 | 常世の花 | 雁帰る常世の花のいかなれや月はいづくも同じ春の夜(左馬頭藤原親定 院御製 1) | 春 |
| 秋冬・春夏 | さむしろ | 荻はらや夜半に秋風露ふけばあらぬ玉ちる床のさむしろ(左大臣 9) | 秋 |
| 恋旅・春夏 | ぬれ衣(ころも) | 人しれぬ涙ばかりにぬれ衣を夢にほせやと返してぞぬる(前大僧正 17) | 恋 |
| 春夏・恋旅 | 霞の衣 | 花ざかり霞の衣ほころびてみねにしろたへの天のかぐ山(定家朝臣 19) | 春 |
| 恋旅・秋冬 | うつの山 | 旅ねする夢路はゆるせうつの山関とはきけどもる人はなし(家隆朝臣 30) | 旅 |
| 春夏・秋冬 | ほととぎす | 夏の夜の有明の空に時鳥月よりおつる夜半の一声(寂蓮 32) | 夏 |
| 秋冬・恋旅 | 落葉がうへ | さびしさはなほのこりけり跡たゆる落葉がうへの今朝のはつ雪(鴨長明 40) | 冬 |
以上のとおり、同じ要素名の組合せでは、序文に則って「和歌の風体」で答え、違う要素名の組合せでは、「和歌の一句」で答えることとなっています。
ここで、「春夏・秋冬」の香の出に対して「常世の花」と「ほととぎす」2つの名目が配されていることに疑問を感じた方も多いと思います。このことについて、出典では「常世か、ほととぎすか」、『御家流組香集(礼)』では「常世の花か、ほととぎす」、『香道真葛原(上)』では「常世の花 又はほととぎす」と記載があり、一貫して2つのうちどちらかを選択するように記述されています。この自由選択性がこの組香の最大の特徴でもあり、「謎」でもあります。もしかすると我々の人知の及ばないところで「最大の趣向」となっているのかもし れませんし、本当に「時宜に合わせてお好きにどうぞ」ということなのかもしれません。いずれ、浅学無知な私には、単純に6つの香の出に対して7首の和歌を採用しなければならなかった際に生じた「構成上の歪(ひずみ)」ではないかと思えます。
つまり、作者が9通りの香の出に名目をつける場合、まず最初にしたことは同じ要素名の組合せ3通りを「三躰」で表すことだったろうと思います。次に残る6通りの香の出に名目を配する訳ですが、『三躰和歌』の詠み人が7名いる為に各自掲載順に1首ずつを採用すると1つ歌が余ってしまうのです。おそらく、作者は登場順に掲載された『三躰和歌』の書を典拠としており、詠人の登場順に歌の一句を引用しようと考えたのでしょう。その作業を再現するため対照表にしてみると、「最初の4首は香の出の最初の1文字と分類の季節が一致し、後ろから3首は香の出の2文字目と一致する」という法則性が発見されました。これは、作者が「香の出のうち最初の要素名を優先させて景色を配した」ことを物語っています。
| 香の出 | 聞の名目 | 分類 |
| ★春夏・秋冬 | 常世の花 | ★春 |
| 秋冬・春夏 | さむしろ | 秋 |
| 恋旅・春夏 | ぬれ衣(ころも) | 恋 |
| 春夏・恋旅 | 霞の衣 | ★春 |
| 恋旅・秋冬 | うつの山 | 旅 |
| ★春夏・秋冬 | ほととぎす | 夏 |
| 秋冬・恋旅 | 落葉がうへ | 冬 |
この表は、一見綺麗に見えますが、先ほどの「春夏・秋冬」の香の出に対して「常世の花」と「ほととぎす」2つの名目が存在するという歪みがあって初めて成り立っています。また、分類の方から見ると「春」の歌である「常世の花」と「霞の衣」が重複しています。順序からして「春夏・恋旅」には「霞の衣(春)」ではなく「夏」の歌を用いるべきと考えれば、定家の歌を「霞の衣」から「夏歌」の「五月雨のふるの神杉すぎがてに木だかくなのる郭公かな 20」に変えることもで考えられたでしょう。期せずして「聞の名目」も同じ「ほととぎす」で組むことができますが、今度は寂連の夏歌と重複してしまいます。どちらにしろ席が空くことはなく、このフルーツバスケット問題は解決しません。
そこで、おそらく作者は、『三躰和歌』7名の詠人の誰を除外してもこの組香の意図が損なわれることを慮り、この件を香席を楽しむ連衆の判断に 委ねることとしたのでしょう。敢えて推測すれば、一義的に四季の風景である「春夏・秋冬」の香の出に対して「常世の花」という普遍的な季節感のある言葉を用いることとし、副次的に夏の風景である「ほととぎす」を用意して時宜に応じて選択させ、香人の感性を刺激することを考えたのかもしれません。この組香は、四季を通じて行えますので、仮に夏に行った場合「夏の名目」が全く現れないのでは寂しいものです。その際には「ほととぎす」と答えるという ローカル・ルールを定めればいいと思います。いずれ、季節感を深めたり、香気の景色を単調にしないための工夫として連衆が自由に選択することができるというのは楽しいことです。
続いて、記録は「二*柱開」ですので、2炉ごとに香元が正解を宣言し、執筆は全員の答えを記録し、当たりに 合点を掛けます。例えば、香元が「秋冬」「秋冬」と宣言すれば、香の出の部分には「秋冬」「秋冬」と横に並べて記録し、連衆の答えのうち「細くからびたる躰」と書いた人のみに 合点を掛けます。
最後に、点数については、出典の記載例によれば、名目の当たりにつき2点と換算し、8点満点となります。「客香」を含む名目への加点や「片当たり1点」等のルールはありませんので、点数は常に偶数となります。下附は点数をそのまま記載します。一方、『香道真葛原(上)』の記載例では、執筆は当った人の答えのみ記載し、外れた人は空白とします。当たり外れの区別が自然につきますので 合点は掛けません。また、名目の当たりが1点と換算され、4点満点となっています。その他のルールは出典と同じです。
「三躰香」は四季を通じて催すことのできる組香です。是非一度「三躰和歌」も紐解かれてみてください。
東大寺のお水取りで閼伽井屋(あかいや)から汲まれた水は「香水」と言われますね。
本尊にお供えするための「根本香水」は・・・
自然蒸発した分だけを注ぎ足して保存しているので「1254年もの」ということです。
組香の解釈は、香席の景色を見渡すための一助に過ぎません。
最も尊重されるものは、皆さん自身が自由に思い浮かべる「心の風景」です。
![]()

Copyright, kazz921 All Right Reserved
無断模写・転写を禁じます。