五月の組香
四季の訪れを鳥獣の声に感じる組香です。
5種の香を同じ要素名で本香に打ち交ぜるところが特徴です。
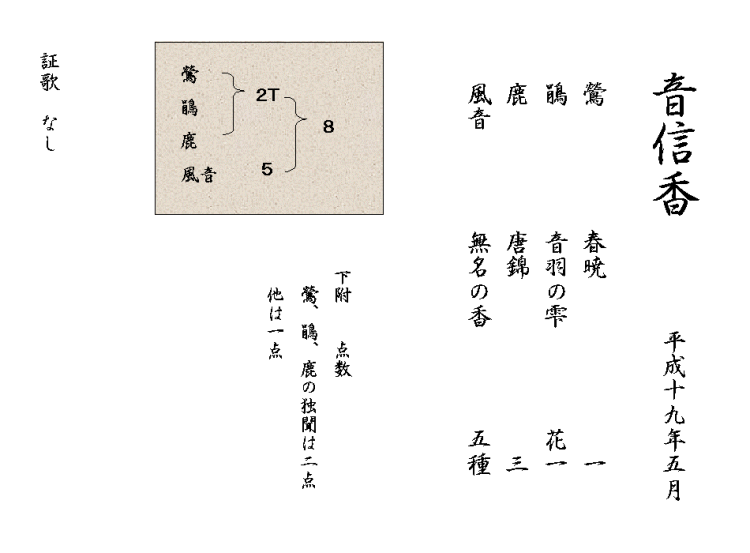
|
|
説明 |
|
香木は、8種用意します。
要素名は、「鶯(うぐいす)」「鵑(ほととぎす)」「鹿(しか)」と「風音(かぜのおと)」です。
香名と木所は、景色のために書きましたので、季節や組香の趣旨に因んだものを自由に組んでください。
「鶯」「鵑」「鹿」は各2包、「風音」は5包を別香でを用意します。(計11包)
まず、「鶯」「鵑」「鹿」の各1包を試香として焚き出します。(計3包)
次に、残った「鶯」「鵑」「鹿」の各1包と「風音」の5包を打ち交ぜます。(計8包)
答えは、名乗紙に香の出の順に要素名で8つ書き記します。
点数は、「鶯」「鵑」「鹿」の独聞(ひとりぎき)のみ2点、その他は1点です。
下附は、点数で記載します。(8点満点、最高11点)
勝負は、点数の最も多い上席の方が勝ちとなります。
日ごとに遠山の景色が濃緑や茶色から新緑にかわりつつあります。
先月は、東福門院樣の御遠忌御法会のために京都に旅行し、初夏のような陽気の中、心豊かに「都のすぎゆく春」を満喫することができました。空港から京都に向かう道すがら、既に山は新緑でしたし、上鳥羽の大橋の上からは満開の菜の花が見えて、「都の桜には間に合うのか?」とハラハラで京都駅に降り立ちましたが、鴨川沿いでは、新緑の柳と山桜の「都の錦」に迎えられ、まずは無事に一つ目の本懐を遂げました。
今回の上洛では、前回からの積み残しだった「米川常白居士」の墓に参り、香席での「百発百中」を祈願するという目的もありました。向かった黒谷「金戒光明寺」は既に散桜となっていましたが、三門前に咲き残っていた「白桜」が、とても良い香りがしたので、木陰にしばし佇んで、平安神宮の大鳥居越しに広がる都の風景を眺めていました。墓参りを済ませてから訪れた「真如堂」では、京都での鶯の「初音」を聞きました。田舎の鶯は友達が少ないので「最初のうちは訛る」という話は以前書きましたが、さすがに京都の鶯は、どこもかしこも「正しく」、しかもなんとも「心和むかわいらしい風情」で鳴いており、これならば風雅人ならずとも心動かされるだろうなと思いました。帰り道の横手にお社があり、桜が満開だったので足を踏み入れましたら、折りよく風がそよぎ、花吹雪が舞いました。私は思わず「おぉ、このために来たんだよぅ。」と叫んでしまいました。京都の花暦はさすがにみちのくより1ヶ月あまり早いようで、藤や射干(シャガ)が咲いていることにも驚きました。
翌日は、「米川常白さん」を「東福門院樣」に引き合わせる形で御法会の席に伺いました。しかし、このところ書物ばかりで香気から遠ざかっており、「香人」とは言えない生活をしたたことが見透かされたようで、惨憺たる成績に終わってしまいました。このことは、私の不精進を戒め「香人は、香気に帰るべし」という啓示を天上のお二人からいただいたような気がしています。憔悴しきった私を慰めてくれたのは、町屋レストランでのおいしい料理と「伽羅」という名のバー、そして、夜半に伺った円山公園の枝垂れ桜でした。ライトアップ最終日の週末ともあって、花の宴も酣(たけなわ)の中、老木を見上げていますと、幾度も樹木医のお世話になっている風体にもかかわらず「凛」として威風を保っている姿に「鼻腔センサーの老化」に対する懸念や不安など吹き飛び、「伽羅聞き」への意欲が湧きました。
最終日には、平安神宮での献茶式を拝観し、庭園を歩きながら有名な紅枝垂れ桜を愛でました。水上回廊と池の水面、岸に咲く可憐な枝垂桜は、光源氏の六条院もおそらくこのようなところで、舟など繰り出しながら、園遊したのだろうと想像でき、月夜であれば朧月夜の君が何処から出てきてもおかしくないというほどの景色でした。最後の最後、帰る道すがらに寄りましたお香屋さんでは、ある老師のご相伴で「今様の伽羅」をたくさん聞かせていただく機会にも恵まれました。これは、私にとっては「香気のタイムスリップ」と言えるもので、前日の香席で「伽羅」すら聞き当てられなかった私の「香気スケール」にとって、大きな補正データとなりました。
今回の京都の旅は、「百発百中の祈願から、求道の懈怠に対する戒めをいただき、最後には伽羅聞きに帰る」という、なんとも奇遇な巡り合わせの多い旅でした。また、肩書きを「香人」から「香道研究家」と変えた、「不遜な名刺」を携えて伺った今回の上洛でしたが、その名刺を打ち捨てる決心のついた旅でもありました。これら旅のシーンにそれぞれご同行くださった皆様方には、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。<m(__)m>
さて、今月は、四季香シリーズ第二弾。お香で季節のたよりを知る「音信香」(おとづれこう)をご紹介しましょう。
「音信香」は、大枝流芳の『香道千代乃秋(下二)』に「新組香十品」として掲載のある組香です。組香の作者は「流芳組」と記載のあることから、オリジナルの組香であることがわかります。同名異組の「音信香」は三條西尭山著の『組香の鑑賞』にみられ、現在では、こちらの方が一般的に催されていますが、これは厳密には「(替)音信香」であり、後世にアレンジされたものであることがわかっています。「(替)音信香」は、アレンジが加わっただけに、シンプルながら季節感に富み、雅趣豊かな組香となっており、オリジナルがその名を譲っても仕方ないと思われるほどの出来なのですが、「オリジナルを知らずして新組を語る無かれ」ということもありますので、今回は『香道千代乃秋』を出典、『組香の鑑賞』を別書として、その対比を交えながら筆を進めたいと思います。
まず、この組香の名は、出典に「音信(おとづれ)」と読み仮名が振ってありますので、間違いの無いところです。現代語では「音信(おんしん)」と読むことが一般的であり、意味は「手紙=便りをすること」になってしまいます。しかし、この組香の趣旨を「手紙香」にしてしまっては、後々の景色と似合わなくなってしまいます。この件については、別書でも「この音信というのは、私共のご機嫌伺いの手紙のことではないようです。」と冒頭に打ち消していますので、同音の「訪れ」
と解釈しみました。すると、「たずねてくること」「到来」「音をたてること」「物事の動静」などといった、組香の景色にふさわしい意味がたくさん出てきました。作者の大枝流芳も自然の移ろいと季節の「おとずれ」をこの組香に表現したかったことは、後の要素名からも明らかですので、「音信→訪れ」の意味で、この字を当てたものと思われます。
次に、この組香の要素名は「鶯」「鵑」「鹿」と「風音」となっています。言うまでも無く「鶯は春」「鵑は夏」「鹿は秋」を表す風物として取り上げられていることは間違いありません。また、そこから「春花」や「新緑」「紅葉」へと自然に心象風景が広がっていくことも期待していると思います。先ほどの「おとずれ」の意味に各要素を結びつければ、それぞれの季節が到来し、「鶯が庭木の枝にたずねて来て、初音を聞かせる。」「新緑の山路には杜鵑がたずねてきて忍び音を漏らす。」「秋の庵では鹿がたずねてきて落葉や小枝を踏み折る音が聞こえる。」と、単に「到来」「訪問」「音」だけではない、様々な「おとずれ」の景色を複合的に鑑賞することができます。
ここで、「春と夏と秋の景色があるのに、冬がないのは物足りない。」と誰しもそう思うでしょう。この発想から「風音」を「木枯」という「冬の風物」に解釈し直したのが、別書に掲載のある「(替)音信香」の発想の端緒となっていると思います。「(替)音信香」では、要素名の「鶯」「鵑」「鹿」「風音」をそれぞれ「春」「夏」「秋」「冬」に当てはめて取り扱います。そして、香筵が開催される季節によって「客香」を入れ替えるという趣向となっています。つまり、夏に「替音信香」を催すならば、「鶯(春)」「鹿(秋)」「風音(冬)」は「地の香」として各2包(うち1包は試香)作り、「鵑(夏)」は「客香」として5包を焚き出します。この形式をとれば、「当節」の季節感を多く味わうことができ、四季にふさわしい組香として汎用が効きますので、とても良く考えられたアレンジだと感心します。
一方、出典では「風音」について「風音と名付け、試みなし。(ウにはあらず)」と注記してあり、「客香」として取り扱わないことを指示しています。作者は、この組香において「風音」は、「鶯」「鵑」「鹿」の季節をつなぐものとして最も抽象的で美しく解釈すべきものだと示唆しているように思えます。「風」は、季節を問わずに吹きますし、「東風」「春風」「花吹雪」「青嵐」「涼風」「野分」「木枯」など、いろいろな形に変化して、季節の栞(シンボル)である「鶯」「鵑」「鹿」を更に細やかな時間の経過や季節感でつなぎ、季節の連綿を表現するために使われているのだと思います。そして、「冬の風物」である「木枯」もそのどこかに必ず含まれているというのは、自明のこととして取り扱うべきだと思います。
ここで、理想的な香の出を想定すると「鶯」「鵑」「鹿」が順番に繋がらずに出てくれるといいと思います。そうすると「風音(東風)が吹き「鶯」が鳴くと「風音(花吹雪)」が散り、「風音(青嵐)」が吹けば「鵑」が鳴き、「風音(涼風)」が吹けば「鹿」が訪れ、「風音(木枯)」の季節となる・・・という季節の連綿が成り立ちます。このように「風音」について「鶯」「鵑」「鹿」に従属する単なる庭先の周辺風景としてだけではなく、一年の季節の流れを繋ぐ風物と解釈すれば、組香の景色は壮大なものになると思います。
次に、この組香の香数は、「2+2+2+5=11包」であり、本香は「1+1+1+5=8包」です。この香数に関しては、名数的な解釈はありません。一方、香種に関しては、要素名が4種であるにもかかわらず、出典の香組の欄に「風音 無銘五種」と記載があるため、香種は「8種」となるという大きな特徴があります。「風音」については、前述のとおり試香がなくとも「客香」とは扱いません。どのような香が焚かれても、試香で焚かれたもの以外は「風音」と回答しますので、香種が違っても混乱することはないでしょう。また、「六国五味」の観点から言えば木所(きどころ)が重複してしまうことは避けられないので、「鶯」「鵑」「鹿」に比べて多少品格の下がる無銘の香を5種類取り混ぜて用意するのが良いでしょう。さらに、どうしても「冬」の「木枯」的な風合いを香気の中に織り込んで「四季」を完成したいと思われる方は、「風音」の1つにそのような「貴品」を隠し入れることも一つの楽しみかもしれません。
続いて、この組香の構造は至って単純です。前述のとおり試香のある「鶯」「鵑」「鹿」各1包を主体に、客香とはしない「風音」5包を加えて打ち交ぜて8炉焚き出す形ですので、あくまで試香と聞き合わせて「鶯」「鵑」「鹿」を聞き当てることが組香の主旨となります。「風音」を5種5香にすることは、「星合香」の「仇星(あだぼし)」の5種5香に類例を見ることが出来ます。もっとも「仇星」は「牽牛」と「織女」をわかりにくくするためだけに「聞き捨て」にされる香ですので、「風音」の方が、景色としては存在感があります。また、前述のとおり「季節ごとの風」として各別に鑑賞することも可能であるため、「5種」であるということに重要な意味を織り交ぜることもできます。
答えは、名乗紙を使用して、要素名を出た順に8つ書き記します。記録は、各自の答えをすべて記載し、当たりに
合点を掛けます。点数は、各要素とも当たりにつき1点となっています。出典にも「鶯、鵑、鹿の香、専ら聞くべし」と記載があり、「鶯」「鵑」「鹿」の独聞(ひとりぎき⇒連中のうち正解者が1人だった場合)については2点と加点要素があります。平常時の満点は、全問正解の8点ですが、独聞の加点がすべてに加わると11点まで望むことが出来ます。
私は、手に入った香木のうち「ちょっとこれは付銘にはふさわしくないなぁ〜?」というものを「標本」として保存しており、こういうものを仲間で持ち合って「駄香合せ」なるものを催したいと常々思っています。「駄香合せ」は、各自が持ち寄った「駄香」について、その欠点や手に入れた時のエピソード等も含めて、「己が失敗」を語り合い、笑い合い、「そうでもないじゃない。」と気に入ったものは交換などしながら、最後に最も「駄香」にふさわしい香木を皆で選んで、それにふさわしい銘を付ける(「鼻ひしぎ」とか「せきばらい」とか・・・)という香席です。これは、ある程度達観した香人の間でしか出来ない「自虐的な遊び」ですが、長年「香馬鹿」を続けてきた御仁には、自慢でもあり、終始微笑みの絶えない面白い香席になろうかと思います。今回ご紹介しました「風音」の5種5香も、どこまで香木の品位を落とすかにもよりますが、仲間内ならば「亭主の失敗話を肴に一座建立する」のも悪くない試みかと思います。
皆さんも風薫る5月に「風の音」や「風の色」などを思い返す機会にしてみてはいかがでしょうか?
「春鹿」「孕鹿(はらみじか)」と鹿は春にも愛でられるもののようですが、
「秋の鶯」や「冬の杜鵑」はどうしているのでしょうか?
「鶯」は叢に居を移して笹鳴きして暮らし、「杜鵑」は・・・杜鵑草に姿を変えるようです。(ウソ)
組香の解釈は、香席の景色を見渡すための一助に過ぎません。
最も尊重されるものは、皆さん自身が自由に思い浮かべる「心の風景」です。
![]()
Copyright, kazz921 All Right Reserved
無断模写・転写を禁じます。