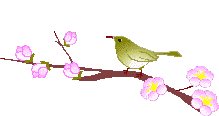
二月の組香
![]()
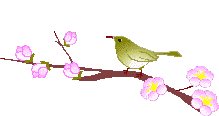
『源氏物語』「匂宮」の帖から発想を得た組香です。
お香の組合せから季節の花の香りを心に結びましょう。
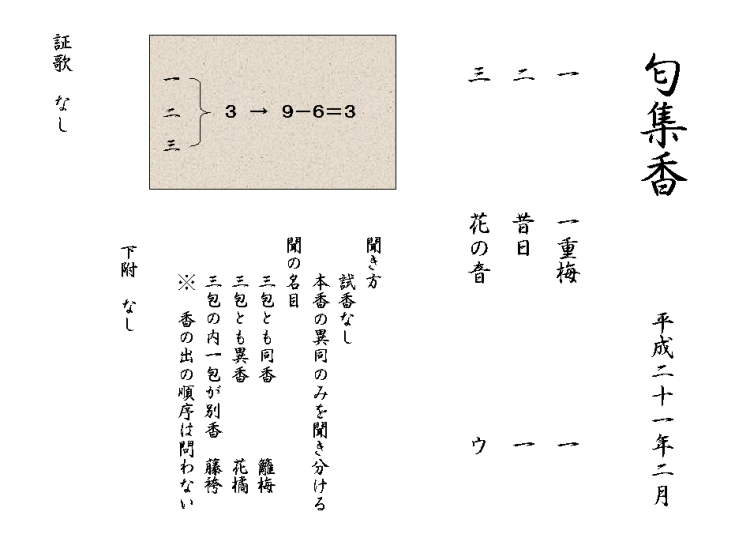
|
|
説明 |
|
香木は3種用意します。
要素名は、「一」「二」「三」です。
香名と木所は、景色のために書きましたので、季節や組香の趣旨に因んだものを自由に組んでください。
「一」「二」「三」は、それぞれ3包作ります。(計9包)
この組香に「試香」はありません。
「一」「二」「三」の各3包を打ち交ぜて、任意に6包引き去ります。
残った3包をさらに打ち交ぜて順に焚き出します。(計3包)
本香は、3炉廻ります。
連衆は、出された香の香りの異同だけを頼りに、「何種類の香りが出たか」を判別します。
答えは、香の出の順番に関わらず、「聞の名目」を名乗紙に1つだけ書き記します。
記録は、各自の答えを全て書き写し、当たりに 合点を掛けます。
この組香に点数、下附はありません。
勝負は、正解者のうち上席の方の勝ちとなります。
「一陽来復」とは冬至のことですが、気温の面では今頃から陽気の兆しが目に見えて来ますね。
先月、「香の文化史」を学生さんに講釈した際に、「朝シャンした彼女の髪からカグワシイ○○○がする。」「焼きたてのクッキーからコウバシイ○○○がした。」のような穴埋め問答をしてみました。「『香』はおしなべて良いイメージ(精神的満足)を司り、『匂』は良くも悪くも幅広く(精神・物理・生理的な満足から不満まで)使われ、 『臭』は悪いイメージ(生理的嫌悪)を司る。」と結論付けるための導入だったのですが、若者はどのような形容詞を付けても一様に「におい」と答えるので、「かおり」という言葉を彼らから引き出すことの難しさを痛感しました。かろうじて「かおり」と答えるものは「花」や「香水」ぐらいで、それも比較的「わざとらしい」刺激の方が「かおり」とイメージしやすいようで
す。自然で淡い本来の「かほり」は、「いいにおい」か「関知せず」に判別されるようであり、むしろ、現代では衛生意識の高さから「くさい」の方が出やすい言葉となっていました。
生来「鼻と右脳」が敏感だった私が、初めて「かおり」を意識したのも、実は「人工香」からでした。それは、小学校当時に売り出された明治屋の「バニラエッセンス」です。プリンやホットケーキを自宅で作ることができる「○○ミックス」という魔法の粉が店頭に現れ、粉を練る際に1〜2滴垂らすと香りが増して、より「それらしく」なったものです。私はその甘い香りの虜になり、台所に並んだ「フレーバー」の小瓶を失敬しては、「パヒューム」のように翫んでいたものでした。
純粋なエッセンスにはじめて出会ったのは大学生の頃、男の子らしく「オレンジピール」や「レモン」などの柑橘系が好きでした。最初に爪楊枝と古くなったリトマス試験紙で「調香」した香水「オレンジギャル」は、今でも私の車の中ダッシュボードに入っており、色香も琥珀色に変わって「オレンジオバサン」になっています。就職した頃からは、映画の「時をかける少女」で主人公の原田知世がタイムスリップするシーンや物語中のキーワードとして「ラベンダー」が使われていたのをきっかけに、花のエッセンスも集めはじめました。そうして、エッセンスに傾注し「調香」からより魔術生のある「アロマテラピー」の勉強を始めるようになりましたが、当時、日本で求められる「精油」は、大変高価なものでした。そこで、独身貴族のピークの頃、エジプトに買い付け旅行をして「バラ」「レンゲ」「ハス」の精油や「ムスク」や「アンバー」等を持ち帰ったものです。そのうち、日本でも「アロマテラピー」が爛熟する時代(第一期ブームは20年前)となりましたが、その一方で、「洋物」に閉塞感を感じた私は「和物」に転向して、現在
に至るわけです。このように、相手にする素材が変わっても「かおり」を集め、四季が発する旬の香りを「クンクン」して、右脳を満たす習性は、子供の頃からまったく変っていません。
今回の特別講義にあたって、担当教授が「今度は、香りのするものをたくさん持っている人を呼んでくる」と学生に予告したら、「ふ〜ん。究極のオタクだね。」と言われたそうです。(言い得て妙です。^_^;)確かに形のない得体の知れないものを集めては、「クンクン」して楽しむオジサンというのは、そのように写りますよね。この「褒め言葉」に気を良くした私は、開口一番「皆さんこんにちは、究極のオタクです。」とぶちかまして「掴みはOK!」、そこから先は、「匂いの出る講義」・・・オタク・ネタを面白おかしく、鼻
と右脳で理解してもらえたようでした。
近年、味覚の貧困化が取り沙汰され、「しょっぱくないから味がない。」「味がないからマヨネーズ・・・」といった風潮もあります。また、食品管理の厳しい現代において、「渋い」という味覚を実感している若者はどの位いるのでしょうか?嗅覚の世界でも「賦香(ふこう)」技術の発達と利用の拡大で、巷に香りが蔓延し、香りは「するもの」(受動的)で「嗅ぐもの」(能動的)では無くなったような風潮があります。昔は、物の善し悪しや好き嫌い、生命の危機までも「嗅ぐ」ことで察知していた人間の優れた感覚器官が、過度の「管理社会」の「あらかじめ情報」によって無力化し、宝の持ち腐れになっているような気がしてなりません。もう一度、自分の五感を使って事物に当たり、自分自身で見極められるよう訓練することが、現代人にとって必要なのではないかと感じています。
今月は、『源氏物語』に登場する「匂宮」のかおりコレクション「匂集香」(においあつめこう)をご紹介いたしましょう。
「匂集香」は、大枝流芳の『香道千代乃秋(下二)』に掲載のある組香です。小引の題号の下には「流芳組」とありますので、大枝流芳が創作したオリジナルの組香であることがわかります。この組香は、「盤物」(ばんもの:ゲーム盤を必要とする組香)の多い「流芳組」の中で、珍しく香札も香盤も必要としない簡潔な組香で、『香道千代乃秋』全巻の中でも異彩を放っています。今回も、オリジナルの組香ですので、『香道千代乃秋(下二)』を出典として筆を進めたいと思います。
まず、「匂集香」には証歌はありません。ただし、小引の冒頭に「三の宮わざと好みて、春は、まがきの梅をかざし御身にふれ、夏は花橘をあつめ香をなつかしみ、秋はかれゆくふじばかまを匂わす。紅菊までもにおいをあつめ給うといえる。源氏物語兵部卿の御ことをうつす。匂いは香に縁あればなり。」と組香の趣旨が書かれています。
ここでいう「三の宮」とは、『源氏物語』に登場する4番目の帝である「今上帝(きんじょうてい)」の第三皇子である「匂宮」を指しています。因みに、組香の原典となる「匂兵部卿(匂宮)」の帖には、冒頭に光源氏の正妻で薫の母でもある「女三の宮」が登場しますが、彼女を示すものではありません。
『源氏物語』の第42帖「匂兵部卿」の帖は、「幻」の帖で光源氏の落日をイメージさせた後、(光源氏の死の場面を記述したのではないかとされる「雲隠」を挟んで)光源氏の死の直後から物語が語られ始めます。「匂兵部卿」の物語を改めて紐解きますと、「薫は14歳の2月に、院の御所で元服して侍従の職に就き、それからの彼は、風貌に秀でたところは無いにもかかわらず、優れた文武の才覚とその身体から香る香気で公私にわたる栄達をみせ、冷泉院からも寵遇されるようになった」と書いてあります。このことから、「匂兵部卿」の帖の時候は、2月を司るとされ、今月のご紹介となっているわけです。
それ以降、『宇治十帖』の物語全編を通して、匂宮と薫はともにライバルとしてに競い合うこととなります。中でも匂宮の競争心は旺盛で、原典では、「兵部卿宮なむ、異事よりも挑ましく思して、それは、わざとよろづのすぐれたる移しをしめたまひ、朝夕のことわざに合はせいとなみ、御前の前栽にも、春は梅の花園を眺めたまひ、秋は世の人のめづる女郎花、小牡鹿の妻にすめる萩の露にも、をさをさ御心移したまはず、老を忘るる菊に、衰へゆく藤袴、ものげなきわれもかうなどは、いとすさまじき霜枯れのころほひまで思し捨てずなど、わざとめきて、香にめづる思ひをなむ、立てて好ましうおはしける。」
訳:「兵部卿宮は、他のことよりも競争心をお持ちになって、それは、わざといろいろな優れたの(香)を焚き染めなさり、朝夕の仕事として(香)合わせに勤しまれ、お庭先の植え込みでも、春は梅の花園を眺めなさり、秋は世間の人が愛する女郎花や、小牡鹿が妻とするような萩の露にも、少しもお心を移しなさらず、老を忘れる菊に、衰えゆく藤袴、何の取柄もない吾亦紅などは、とてもすさまじい霜枯れの頃までお忘れにならないなどというふうに、ことさらめいて、香を愛する思いを、取り立てて好んでいらっしゃるのであった。」
・・・と匂宮が薫の発する自然の香りに対抗して、盛んに香を焚き染め「薫物の調合」や季節の草花の「匂集め」に執着したと書いてあります。この「匂宮の匂集め」がこの組香のテーマとなっています。
次に、この組香の要素名は「一」「二」「三」と匿名化されています。これは、後の「聞の名目」で景色を結ぶ際の素材として扱うため、それまでは香に特別なイメージを持たせないようにする工夫です。特にこの組香では、「9包のうち6包を任意に引き去る」という大胆な所作があるため、本香に全ての要素が現れることはあまりありません。そのため、要素にあらかじめ景色を付けてしまうと、かえって出 現しなかった要素(景色)の分だけ「さみしい」組香となったり、組香の趣旨が崩れてしまうこともあります。そういう意味で、各要素をニュートラルな「素材」として用いるのは妥当な選択かと思います。
続いて、この組香の香種、香数については「香3種、本香3香」となっています。これについては、簡潔な組香を創作する意識で「最小単位」を意識したものと考えるのが一般的でしょうが、私は、要素名と本香数が同じく「三」であることからして、作者の頭の中に「三の君」の「三」に掛ける意識があったのではないかと推察しています。また、私は、香数の流れについても、本香を9包用意するところまでは、匂宮の「匂集め」の情景、そして、その素材を打ち交ぜて3包の香を残すところは、匂宮が「香を合わせる」情景を表したのではないかと思っています。我々も種々の練香を「畳む」際に、まず、香料をたくさん集め、レシピにしたがって、必要な素材を選びます。また、自分なりの秘法として季節の花の花粉を調合することなどもあるでしょう。ここに上げられた3つの要素が具体的に甘草や薫陸、麝香等の「香料」であるということではないのですが、後々、それが「梅」や「橘」「藤袴」の香りを構成する「なにものか」であるとイメージすればよろしいかと思います。そのような『なにものか』を集めて、そこから取捨選択し、『ひとつの香り』を結んでいくという匂宮の「合香」の過程が、この組香のストーリーではないかと思います。
さて、この組香の構造は至って単純です。各要素は3包ずつ作り、合計9包を打ち交ぜて、そこから6包を任意に引き去ります。すると残された本香は3包となり、これを順番に焚き出すだけです。この組香には、試香がありませんので、連衆は1炉目の香を頼りに2炉目がそれと「同じか?違うか?」、3炉目は、前の2つと「同じか?違うか?」のみを判別します。
ここで、実際にこの所作で香元から焚き出される本香の「要素名パターン」を全部書き出してみましょう。
| 区分 |
要素の組合せ |
|||||
| 全部同香 | 一、一、一 | 二、二、二 | 三、三、三 | |||
| 全部異香 | 一、二、三 | 一、三、二 | 二、一、三 | 二、三、一 | 三、一、二 | 三、二、一 |
| 一部異香 | 一、一、二 | 一、一、三 | 一、二、一 | 一、三、一 | 一、二、二 | 一、三、三 |
| 二、二、一 | 二、二、三 | 二、一、二 | 二、三、二 | 二、一、一 | 二、三、三 | |
| 三、三、一 | 三、三、二 | 三、一、三 | 三、二、三 | 三、一、一 | 三、二、二 | |
このように、要素名と香の出の順序を考慮すると全部で27通りとなります。しかし、この組香では、連衆は「香の異同だけを判別」すればいいので、例えば「十*柱香」の際のように、1炉目を仮に「〇」とメモしておき、2炉目が1炉目と同じ香りだったら「〇」、違っていたら「△」とし、3炉目が「〇」と同じだったら「〇」、「△」と同じだったら「△」、どれとも違っていたら「×」と記号化しておくとわかりやすいと思います。(一番目の香を「一」と数字化するやり方もありますが、要素名の「一」と混同しやすいので注意しましょう。)
すると、メモに記載される記号の「異同パターン」は、次の5パターンに単純化されます。
|
区分 |
記号の組合せ |
||
| 全部同香 | 〇、〇、〇 | ||
| 全部異香 | 〇、△、× | ||
| 一部異香 | 〇、〇、△ | 〇、△、〇 | 〇、△、△ |
本香が廻り終えましたら、連衆は、このメモと「聞の名目」と見合わせて答えを導き出します。
出典には・・・
「三包とも同香と聞かば、籬梅(まがきのうめ)と書き付くべし。」
「三包とも異香と聞かば、花橘(はなたちばな)と書き付くべし。」
「三包の内一包が別香と聞かば、真蘭(ふじばかま⇒藤袴)と書き付くべし。」
・・・と3種の名目が用意されています。
また、出典には「同香の次第は、かまいなし。ただ、一包別の香あるかなきかをよくきくべし。」と記載されており、「香がどのような順序で出たかは問わない」こととされています。
このことから、先ほど5つあった「異同パターン」を「順不同」にすると、さらに3パターンに単純化できますので、連衆は下表にある3種類の「区分」と「聞の名目」の対応うち1つを選んで回答することとなります。
|
区分 |
記号の組合せ |
聞の名目 |
||
| 全部同香 | 〇、〇、〇 | 籬梅 | ||
| 全部異香 | 〇、△、× | 花橘 | ||
| 一部異香 | 〇、〇、△ | 〇、△、〇 | 〇、△、△ | 藤袴 |
そうしてみると、「籬梅」「花橘」「藤袴」の出現確率は、「要素名パターン」の表を母数にしますので、圧倒的に「藤袴」が多く(18/27=2/3)、次に「花橘」(6/27=2/9)、最後に「籬梅」(3/27=1/9)となることがわかります。
また、香の出と聞の名目の対応理由については、「全部同香は、梅が最も淡麗で香気がスッキリしているからか?」「全部異香は、花橘が最も濃厚で複雑な夏の香りだからか?」「それでは、一部異香とされた藤袴はその中間なのか?」などと思い巡らしてみましたが、明確な解釈は見つかりませんでした。おそらくこれは、「区分」に従った「季節」の序列で、春⇒梅、夏⇒橘、秋⇒藤袴と対応させただけなのではないかと思います。
一方、この組香の弱点は「春の組香なのに景色に秋の花が出やすい。」ということと、「春の組香なので、籬梅を出現させようとすると、連衆はせっかく用意した3種の香の1種類しか聞くことができない。」というところにあろうかと思います。出典の香組が「はるの夜」「玉川」「むもれ木(埋木)」となっており、香記の香の出も「籬梅」が例示されていることから、作者も間違いなく「春の組香」を想定している筈なのですが、香記の景色がなかなか伴わないのは惜しいことです。そこで、季節に応じて聞の名目を入れ替えるのも一考かと思います。例えば、春には最も出現しやすい一部異香を「籬梅」とし、最も出現しにくい全部同香を「藤袴」とするなどのアレンジがあってもよろしいかと思われます。また、全部異香を「籬梅」に据えて、香元が「引き去り」に作為を加えると、春の千草の香りが「籬梅」に集約され季節感と連衆の満足度も一層上がるかもしれません。(邪道ですが、演出とヤラセは紙一重ですので・・・)
ここで、出典には、匂宮が「梅」を「かざし(簪)」にして身に付け、「花橘」「藤袴」「紅菊」の香りを好んで集めたというように記載されていますが、原典となる『源氏物語』では、「梅」は花園を眺めるだけ、夏の「花橘」は無く、秋は「藤袴」と「吾亦紅」が登場しますが、「老いを忘れる菊」が「紅菊」と特定はされていません。特に「花橘」については、夏の記述も花の記述もないので、原典と出典との間に違いがあることをあらかじめ認識しておきましょう。このことは、組香創作当時に大枝流芳が取材した写本や伝聞の問題ではないかと思われます。江戸時代の『源氏物語』手鑑は、大名家のお姫様の嫁入り道具として書き写される程度のもので、一般に流通することは少なかった筈です。そうなると、いかな京都の粋人として名高い大枝流芳であっても、その「原典」に触れる機会は少なかったのではないかと推察されます。おそらく流芳は、庶民用に分かりやすく編集された『源氏物語』のダイジェスト版か、かなりの人の手を経た写本を手にして、「匂集香」創作したのではないかと思います。いずれ、「春は梅」「夏は橘」「秋は藤袴」というのは、現在人にとってもイメージしやすい景色ですので、これはこれでよろしいかと思います。
最後に、この組香の記録は、執筆が連衆の答えを全て書き写し、香元に香の出を請い、香元が正解を宣言し ましたら、当たった名目の右肩に正点「ヽヽ」を掛けます。これは「3要素を含めて聞の名目自体が当たった」という意味で、一般の「ウ」が当たった場合に付けられる加点要素の「二点」とは趣きが異なります。また、この組香は、香の出の順序を問わないため「3要素のうちのこの部分だけは当たっている」として傍点「ヽ」を付す「片当たり」はありません。さらに、点数も下附もないので、この「正点」のみが各自の成績を表し、勝負は「聞の名目」の正解者のうち上席の方が勝ちとなります。
「匂集香」は、『源氏物語』に因んだ組香で文学的支柱もしっかりしており雅趣にも富んでいます。そして、ありがたいことに「試香なし。本香三炷。香の異同のみを判別する」という簡潔な組香でもありますので、素人さん向けの大寄せや時間が制約されている当座の席に適しているかと思います。皆様も是非、お試しください。
宇治十帖で「薫」が「かおる」、「匂宮」が「におう」とネーミングされた段階で、
紫式部の中で両者の優劣は決まっていたのでしょうね。
組香の解釈は、香席の景色を見渡すための一助に過ぎません。
最も尊重されるものは、皆さん自身が自由に思い浮かべる「心の風景」です。
![]()
Copyright, kazz921 All Right Reserved
無断模写・転写を禁じます。