
四月の組香

小野小町と深草少将の「百夜通い」を景色とした盤物の組香です。
双方の人形が行き合った後の「押し合い」が特徴です。
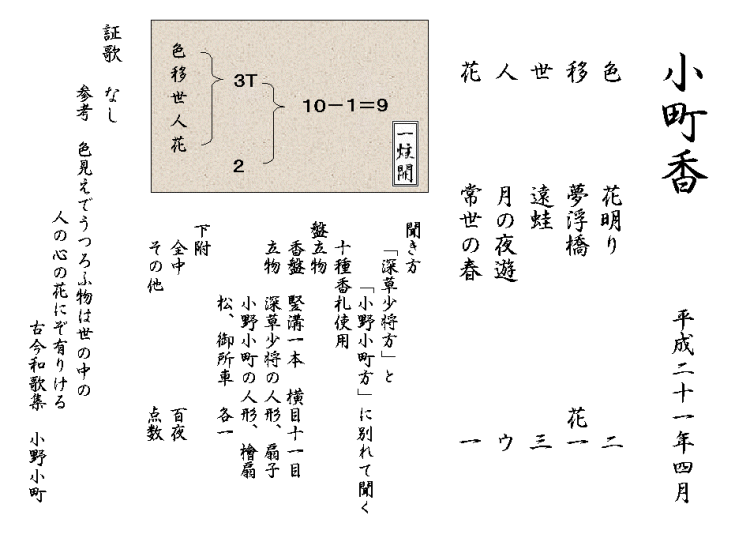
※ このコラムではフォントがないため「![]() 」を「
」を「
|
|
説明 |
|
香木は5種用意します。
要素名は、「色(いろ)」「移(うつり)」「世(よ)」「人(ひと)」と「花(はな)」です。
香名と木所は、景色のために書きましたので、季節や組香の趣旨に因んだものを自由に組んでください。
「色」「移」「世」「人」は各3包作り、「花」は2包作ります。(計15包)
連衆は、あらかじめ「深草少将方(ふかくさのしょうしょうがた)」と「小野小町方(おののこまちがた)」の二手に別れます。
「色」「移」「世」「人」は、それぞれ1包を試香として焚き出します。(計4包)
残った「色」「移」「世」「人」の各2包に「花」2包を加えて打ち交ぜ、その中から任意に1包引き去ります。(計9包)
引き去った1包は、総包に戻します。(捨て香)
本香は、「一*柱開(いっちゅうびらき)」で9炉回ります。
−以降9番から11番までを10回繰り返します。−
連衆は1炉ごとに答えを「香札」で投票します。
香元が正解を宣言します。
執筆は香記に当たった答えのみ書き記し、客香の当たりのみ答えの右肩に2点を掛けます。
盤者は、所定の方法で勝ち点の多い方の人形を進め、行き会った場所からは押し合いをします。(委細後述)
盤上の勝負は、香が全て焚き終わった時点で人形の押し込んでいる方の勝ちとなります。
下附は、全問正解の場合「百夜」と書き記し、その他は点数で書き記します。
記録上の勝負は、勝ち方の最高得点者のうち、上席の方が勝ちとなります。
人生の節目に咲いていることの多い桜は、見ているといろいろな想いが廻りますね。
小さい頃、朝寝坊をしていると、よく母から「春眠暁を覚えず!」と諫められるように言われたものでした。誰しもそうだと思いますが春暁の布団の中は「天国」です。先月、娘からプレゼントされた『AB型の説明書(文芸社)』によれば、AB型は「三度の飯より寝るのが好き」らしいですが、正にそのとおり! 暖かくてフワフワして、ウトウトして、寝返りをうつたび「シアワセ〜」がこみ上げて来ます。
また、私は「鍵っ子」だったため、病気をすれば枕元に「葡萄液」と「桃缶」を置かれて、家で1日中寝ている羽目になるのですが、これも私にとってはシアワセな時間でした。友達が学校で勉強をしている時間に、こちらは家で悠々自適という「背徳感」。それに加えて、空想好きの私は、天上のシミからドラマを作ってみたり、宇宙の星間物質を想像したり、12色の絵の具で「金色」を出すレシピを考えたり、人を意のままに動かせる香水を考えたり・・・「荒唐無稽な錬金術師」みたいなことをしていると、あっという間に夕方になるのでした。
私が、このコラムの構想を練るのも、大抵は「休日の朝の寝床の中」です。昔は、深夜にホトトギスの声を聞きながら書いていたのですが、頭は鬼気として冴えるものの、夜に書く文章はどうも扇情的になりやすいのです。「恋文も夜中に書くな。」とよく言われまずが、こういったコラムも翌日見て”コッ恥ずかしく”なり、全面推敲ということが何度かありました。現在は、平日と同じ頃に目覚めて、ボヤボヤ、ゴロゴロしながら構想し、起承転結が決まったところで「よっしゃ!」とおもむろに起き上がって、午前中に書き上げてしまうといった感じになっています。
大人になってから、「早く起きろ!」のかわりに母から言われていた言葉の意味がやっとわかりました。
「春眠不覺曉 處處聞啼鳥 夜来風雨聲 花落知多少 (孟浩然「春暁」)」
(春眠暁を覚えず 処処啼鳥を聞く 夜来風雨の声 花落つること知んぬ多少ぞ )
正にこの感じですよね〜♪ カーテン越しに淡い色の付いた光が部屋の壁を染めて、雨上がりには鳥の声、朝の気配を全て味わい尽くせるような心豊かな時間・・・あとは、「あぁ、腹減った。」が無ければ、いつまでも布団の中に居たいような気がします。もしかすると、母は「春は誰でも眠いものだから、お前だけ怠けていてはイカンよ。」という叱咤の中に「暖かくて、眠くて、気持ち良いのはよくわかるよ。でもね・・・お腹いっぱいもシアワセだよ〜。」という優しい気持ちを込めて言ってくれていたのかなと思っています。
この詩で「雨上がりに落ちる花」とは、おそらく「梅」なのでしょうけれども、当地において「春眠暁を覚えず」を感じられるのは彼岸過ぎですので、もう「桜」の季節です。一雨ごとに蕾を膨らませて、ある雨上がりの朝に「ぽっ」と咲き始めた「桜の香り」が漂ってくると、花の満開より心躍るものがあり、私にとっては寝床の中の「春爛漫」なのです。それから、桜は花のピークを迎え、一雨ごとに色あせ、花吹雪となって舞い散り、花筏となって水面に浮かぶまで楽しめます。人の命もその年代によって、「愛でる視点」を変えていけば、意外に長く楽しめるものかもしれませんね。
今月は、小野小町の「モテ期」とその後の「憂い」が錯綜する「小町香」(こまちこう)をご紹介いたしましょう
「小町香」は、『聞香秘録』の最終巻「香道春曙抄(全)」に掲載のある「盤物(ばんもの)」の組香です。『聞香秘録』は、金鈴斎居由が、諸家を訪ね、香書や伝書の組香を写し取った200組に及ぶ組香書の集大成といえます。そのため、多くの場合、大枝流芳の組香書や御家流組香書に類例を見ることができますが、「小町香」については、他書に同名の組香は見つかっていません。いずれ、金鈴斎居由が巻末で「探諸家 集成写」といっているので、居由の創作したオリジナルとは考えにくく、光源氏と朧月夜の「舞楽香」をアレンジした比較的新しい組香として、何れかの伝書に掲載されていたのではないかと思っています。今回は、「香道春曙抄(全)」を出典として筆を進めたいと思います。
まず、この組香に証歌の記載はありませんが、題号と要素名から「色見えでうつろふ物は世の中の人の心の花にぞ有りける(小野小町:古今和歌集797)」をテーマとして創作された組香であることは間違いないでしょう。歌の意味は、「(花は色に見えて移ろうものだが)色には見えず移ろうものは、人の心に咲く花だったのだなぁ。」ということでです。最近入手した『女小学』では「それ人の心、惟(これ)あやふしとは、聖人の御言葉なり。たとい常に色香にめでじ、味わいにもふけるまじ・・・あやうきものは人の心と知るべし」との文の後にこの歌が引用されており、人の心の無常観を女性に教えるための教訓として扱われています。
この歌は、百人一首で有名な「花の色はうつりにけりないたづらにわが身世にふるながめせしまに(小野小町:古今和歌集113)」の続編といった雰囲気があります。春の長雨に色あせた桜を見て、女独りで世渡りをして来たいろいろなことが思い返され・・・色恋沙汰で忙しかった「世の中」に、一度も実を結ぶこと無く、咲いては散っていった幾多の「心の花」を淡く、儚く、惜しんでいるという景色が見えます。どちらも、吐息の聞こえるような内省の歌というところでしょうが、「色見えで・・・」の方は、少し気を取り直して外に目を向け「移ろいやすい人の心」にもカタルシスを求めた分だけ客観的に見えます。この組香は、これらの歌を基に「どんな男に言い寄られてもなびかなかったという絶世の美女」小野小町が、女の盛りを過ぎて、取り戻すべくもない 過去を物憂げに懐かしんでいるという心情を背景に、「昔日の出来事」を盤上の景色で表現しているのだとと思います。
詠人の「小野小町」は、絶世の美女として有名な平安歌人で、六歌仙、三十六歌仙に名を連ねている「謎の才媛」です。彼女の生没年や出自は不明で、『古今和歌集』の歌人目録では、「出羽郡司娘」とされていますが、出羽郡司良真(よしざね)の娘で小野篁(たかむら)の孫とも、出羽守小野滝雄の子とする説などもあります。彼女の「生誕の地」、「終焉の地」を宣言している地域は全国各地に点在していますが、私としては東北の中で最も美人度が高い地域と確信をしている「秋田県湯沢市小野」(旧雄勝町)が、少なくとも出生地であり、もしかすると終焉の地でもあると信じたいものです。彼女は、仁明天皇(833)や文徳天皇(850)の頃、後宮に「更衣」として仕えていたという説が有力ですが、その生涯は、詠まれた歌や伝説から、断片的にしか伺うことはできません。いずれ、「絶世の美女」としての地位は揺るぎなく、彼女の生涯にまつわる伝説は、後世、能や浄瑠璃などで脚色され、「小町物」として定着していますし、「小町」という名前は、現在でも「美しいもの」の代名詞として利用され、数学の「小町算」にまで及んでいます。そして私は、彼女の「女として決してのめりこんでいない清廉な恋歌」とでも言いましょうか、クールでプラトニックな作風がとても好きです。
次に、この組香の要素名は「色」「移」「世」「人」と「花」となっており、証歌を分解して各句の頭文字を当てはめる(色見えで 移ろふ物は 世の中の 人の心の 花にぞ有りける)という原則的な手法をとっています。一般的に盤物の組香では、「一」「二」「三」「四」「五」と要素名が匿名化されてしてしまいますが、この組香では、出典の香組の段に「一ノ香 色と名付け 三包 内壱包試」のように記載されており、それぞれの要素に景色を付けています。
これは、要素名を「一」「二」「三」「四」「五」と匿名化すると、「小町香」という題号だけでは、出典には明記されていない 「証歌」をどこからも連想することはできなくなるので、小野小町の物憂げな心情や昔日の出来事との関連も連衆には伝わらないこととなるからです。そうすれば、この組香は、単に「小野小町の人形」が盤上を行き来する聞き当てゲーム(男性の人形も登場するので恋の鞘当てゲーム)としか理解されなくなってしまいます。作者は、敢えて要素名に景色を与えることによって、内包された証歌を連想させ、小野小町の現在の心情を背景とした上で、盤上の景色に昔日の思い出を写しており、これは秀逸な工夫だと思います。また、各要素を単なる「頭文字」として取り扱わず、「人」は小野小町が思い浮かべている「かの人」、客香となっている「花」は実を結ばなかった小野小町自身であると解釈すると、心象風景にも深みが出ると思います。
この組香はあらかじめ連衆を「深草少将方」と「小野小町方」の二手に分けて聞き比べをする一蓮托生対戦型ゲームです。ここで、小町が恋の鞘当てをして来た数ある「かの人」の中から、「深草少将」にスポットライトが当たります。
ここで登場する「深草少将」とは、世阿弥などの能作者たちが創作した小町伝説「百夜通い(ももよがよい)」に登場する伝説上の人物です。彼は、小野小町に熱心に求愛するのですが、小町はそのことを鬱陶しく思っていたため、何とか諦めさせようと「私のもとへ百夜通ったなら、あなたの意のままになりましょう。」と彼に告げます。それを真に受けた深草少将は、それから毎晩、彼女の邸宅へ通いますが、この道のりを通い詰めて99日目の満願前夜、彼は大雪のため雪に埋もれて凍死してしまいます。
因みに、現在、彼の邸宅跡とされている、墨染(京都市伏見区)の「欣浄寺」(ごんじょうじ)から、小町の邸宅跡といわれている山科小野(京都市山科区)の「随心院」(ずいしんいん)までは、 距離にして5〜6kmの道のりです。深草少将の邸宅跡とされる欣浄寺には「通う深草百夜の情け、小町恋しい涙の水は、今も湧きます欣浄寺(西条八十)」の看板が立ち、小野小町と深草少将供養塔が並んで立てられているほか、少将遺愛の「墨染の井戸」や小野小町が姿を映したという「姿見の池」があり、池の横には「少将の通い道」が残されています。両院とも一見、「町中の小さなお寺」という風情ですが、彼らの悲恋の伝説が今でも息づいているようです。
続いて、この組香の構造は、「色」「移」「世」「人」は各3包作り、「花」を2包作ります。そのうち「色」「移」「世」「人」は、それぞれ1包を試香として焚き出します。ここまでは一般的な十*柱焚きの盤物と構造が似通っていますが、この組香では、残った「色」「移」「世」「人」の各2包に「花」2包を加えて打ち交ぜ、その中から「任意に1包引き去る」という所作が加わります。この所作によって、本香数は「9包」となり、焚かれる香が全部2包ずつではなく、「1つだけしか出ない香がある」という変化がもたらされます。私は、この本香の欠落を「百夜通いの最後の一日」なのではないかと思っています。そして、「最終日に深草少将が渡しそこねた文」が捨て香となった1包であり、随心院の「文塚」に納められることのなかった、彼の「思い残し」であると解釈しています。
そうして、本香は、「一*柱開」で9炉回りますので、連衆は1炉ごとに答えを「香札」で投票します。回答に使用される香札については出典に「香札は十*柱香札を用ゆべし。左の通り、一人前十枚なり。」とあり、要素名と香札の対応が次のように示されています。
「色」に「一」の札と「月一」の札
「移」に「二」の札と「月二」の札
「世」に「三」の札と「月三」の札
「人」に「客」の札 二枚
「花」に「花一」の札と「花二」の札
このように、札の配置を見ましても、「色」「移」「夜」の回答に「月札」を用いて組香の舞台が「夜」であること、「人」に「客札」を用いて「人の訪れ」のあること、そして、主役(客香)である「花」に敢えて「花札」を用いることによって、「花に夜訪れる人」という景色が醸し出しされており、連衆が、自然に「百夜通い」の景色を連想するように配慮されていることがお解かりかと思います。
さて、この組香では、「小町香盤」という専用のゲーム盤を用います。これは、細長い盤の真ん中に人形の滑る溝があり、その両側に11間の目盛りが付いているもので、イメージは「舞楽香盤」におよそ似たものですが、中央に勝敗を決する「勝負場」の無いのが特徴です。立物(コマ)として使用する人形は「深草少将」と「小野小町」であり、これらが二手に分かれたグループのシンボルとなります。置物は「松の木」とその下に「御所車」が飾れれますが、これは深草少将が乗って来たものかと思われます。このように、盤上の景色は、小野小町の邸宅に深草少将が通ってきた場面が連想されるものであり、小野小町が証歌を詠んだ際に、ふと思い起こした「昔日の出来事」を表しているのではないかと思っています。
本香は、「一*柱開」のため、「本香一炉」が焚き出され、香炉と各自の回答が戻ってきたところで、香元が正解を宣言して答えの当否が決まります。ここで執筆は、香元から宣言される正解を「香の出」の欄に記載し、各自から投票された香「札の裏」を見て当たり札のみ選び出し、今度は「札の表」を見て、その札の紋と各自の名乗りの紋を見比べて、当った人の回答欄にのみ要素名を書き記します。(例:香の出が「色」ならば札裏が「一」か「月一」の札のみ集めておき、札表に「老松」があれば、「老松」と名乗った人の回答欄に「色」と書きます。)
その際、「花」のあたりについては加点要素があり、2点と換算しますので要素名の右肩に「ヽヽ」と掛けます。その他の当たりは、記載されたこと自体が当たりを示しますので合点は
掛けません。一方、外れた人の回答欄には何も書かず「白闕(はくけつ)」とします。
そうして、1炉(一回戦)が焚き終わった時点で、各グループの点数を一旦合計します。
人形の進みは「消し合い」という方式を取ります。これは、双方の総得点の同点部分を消しあって、差分のみを勝ち点とするやり方です。例えば、1炉目が終わって「深草少将方」のメンバーの総得点が「5点」であり、「小野小町方」の総得点が「3点」であった場合は、その差分は「2点」ですので、盤者は、勝ち方である「深草少将」の人形を「2間」進めます。両方とも同点の場合は、差分が「ゼロ」ですので人形は動かしません。
これを1炉ごとに9回繰り返しますが、途中で双方の人形が行き合い(鉢合わせして)、進むことが出来なくなることがあります。これについて出典には「左右人形、行合たる時、左右とも同じ聞数なれば人形は動かず、何れにても聞数多き方の人形進み、聞数のすくなき方の人形後退す。」とあり、勝ち方の進む分だけ、負け方が退くこととなります。この点が「舞楽香」のように「早く勝負場にたどり着けば香が焚き終わらなくても盤上の勝負は終り」というものと異なるところで、最後の香が焚き終わるまで盤上の勝負を楽しむことが出来ます。また、この「押し合い」方式は、「決して寄り添うことのない二人の押し問答の景色」が良く表現されていると思います。実戦では、この人形同士の「押し合い」が長く続けば続くほど「今宵こそ、想いを遂げさせてくれぇ〜(深草)」「なりませぬ。なりませぬぅ。(小町)」のような情景が見えて微笑ましい雰囲気になるかと思います。
そうして、盤上の勝負は、本香がすべて焚き終わったところで、盤上を多く進んでいる(押し込んでいる)方が「勝ち方」となります。また、出典では、「進み少なき方の人形持ちたる扇を取り、松の枝にかける」とあり、小野小町方が負ければ「檜扇」を深草少将方が負ければ「扇」を松の枝に掛けます。この「ちょっとした意地悪」が負け方に対する罰盃の代わりとなっています。
最後に、各自の得点を合計して下附します。この下附については「小町香之記」の記載例の枠外に「皆聞には百夜と書く。」とあり、下附では全問正解を表す「百夜」が書き記されます。これは、伝説の主旨とは異なるのですが、深草少将の「百夜通い」が満願したことを示すのでしょう。その他は、点数で「〇点」と書き記します。記録上の勝負については、この下附をもとに個人賞が決まるのですが、「一蓮托生対戦型ゲーム」ですので、自分だけ全問正解「百夜」であっても、所属するグループが「負け方」となってしまえば勝者にはなれません。そのため、たとえ「八点」であっても、勝ち方の最高得点者のうち上席の方が記録上の勝者となります。
「小町香」は、春の盛りというよりは、「残花」・・・それも「夜」のイメージの強い組香ですが、「花の宴」に疲れた心をしみじみと癒してくれる「思い出しの組香」かと思います。中年を過ぎれば男女の別なく、ふと訪れる「昔日の想い」や「後悔の念」・・・小野小町に擬えて思い起こしてみてはいかがでしょうか?
とかく美人は、その容貌ゆえに真心の交わりに恵まれない傾向にあるようで・・・
彼女の晩年は数奇な運命に苛まれ、非常に惨めな最後を送ったとされています。
ながめして人の通いも絶えしかど散りて浮かぶも花にぞあるかし(921詠)
組香の解釈は、香席の景色を見渡すための一助に過ぎません。
最も尊重されるものは、皆さん自身が自由に思い浮かべる「心の風景」です。
![]()

Copyright, kazz921 All Right Reserved
無断模写・転写を禁じます。