十一月の組香

たった一つの試香を頼りに全てを聞き当てる組香です。
聞き当ての手掛りが順次展開していくように工夫されているところが秀逸です。
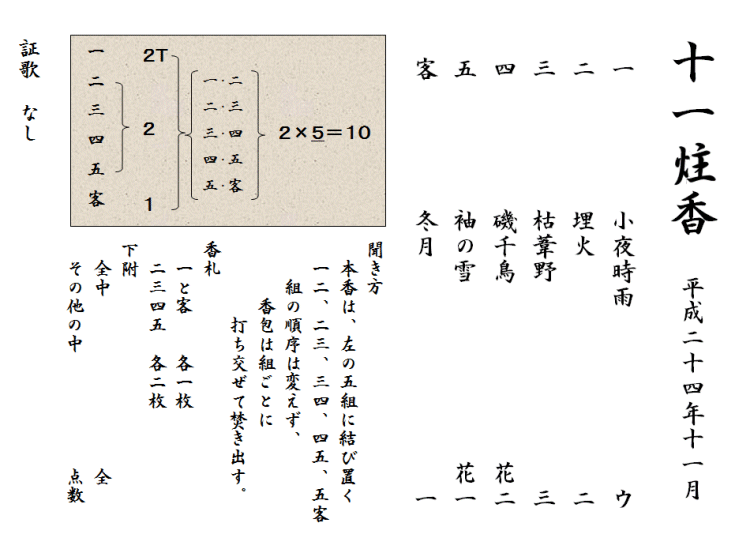
![]() 」を「*柱」と表記しています。
」を「*柱」と表記しています。
|
|
説明 |
|
-
香木は6種用意します。
-
要素名は、「一」「二」「三」「四」「五」」と「客」です。
-
香名と木所は、景色のために書きましたので、季節等に因んだものを自由に組んでください。
-
「一」「二」「三」「四」「五」は各2包、「客」は1包作ります。(計11包)
-
このうち試香とする「一」の1包を除いて、「一・二」「二・三」「三・四」「四・五」「五・客」と2包ずつ5組に分けます。
-
各組の2つの香包は、あらかじめ前後を打ち交ぜてから結び置きします。(2×5=10包)
-
5組の結びには、焚き出す順番を間違えないように、組ごとに「一」「二」「三」「四」「五」と結び紙等に番号を振っておきます。
-
まず、「一」のうち1包を試香として焚き出します。
-
本香は、組ごとに2包ずつ5組焚き出されます。(計10包)
-
香元は、「一の組」の結びを解き、2つの香包を再度打ち交ぜて焚き出します。
-
香元は、2つの香炉に続いて、「一」「二」と炉の番号が表書きされた「折居(おりすえ)」を2枚廻します。
-
その後、順次「二の組」から「五の組」までを同様に焚き出し、折居を添えます。
-
連衆は、「一の組」のうちから試香と聞き合わせて同香を「一」と判別し、聞いたことのない異香を「二」とします。
-
連衆は、廻された2枚の折居に出た順序に香札(こうふだ)を投票します。
-
その後は、前の組で焚き出されたことのある要素を頼りに順次「同香」「異香」を判別します。(委細後述)
-
回収された折居は、順次開いて「札盤(ふだばん)」 の上に香札を伏せて、各自分を縦に並べて置きます。
-
本香が焚き終わったら、執筆は、各自の香札を開き、香記の回答欄に全員の回答を書き写します。
-
香元が、正解を宣言し、執筆は当たりの要素に「点」を掛けます。
-
点数は、各要素の当りにつき1点とします。
-
下附は、全問正解者は「全」、その他は点数を漢数字で書き記します。
-
勝負は、正解者のうち、上席の方の勝ちとなります。
久屋大通りのケヤキの色づきに仙台を思う季節となりました。
先月は、大須の大道町人祭があり、大勢のパフォーマーやそれを目当ての観客で賑わいました。今年は岐阜県の羽島市にあった「真福寺(大須観音)」を徳川家康が名古屋城下に移してから400年にあたり、秘仏である観音様も御開帳の年となっています。今回で35周年を迎えた町人祭で「一生に一回」と言われる実行委員長になられたのは、三味線屋の六代目で、 祭りのポスターを書いたのはTattoo Artist(日本風に言えば「彫師」)というのですから、大須商店街の幅の広さに感心せざるを得ません。もともと、大須は遊郭や芝居、娯楽場で賑わった庶民文化の拠点のような地域でしたから、以前の門前商店街よりも、現在の「なんでもアリアリ」の方が、本来の姿に近いのかもしれません。
ここで繰り広げられる「大道芸」は、日本の伝統芸、ジャグリング、パントマイム、ロービング、ストリートミュージック、舞踊等、ざっと数えて45組の「芸人」たちが出演していますが、事務局は招へいやスケジューリング調整等はするものの、当日のギャラは全てが観客が投げる「投げ銭」のみということです。ある意味、遠方から大勢で参加する芸人にとってはギャンブルであり、一方で自分の「芸」を先入観無く、純粋に「絶対評価」してくれる観客との真剣勝負という「心洗」の場でもあるわけです。あるジャグラーは「大道芸では、自分が先輩だからと言って、後輩は場所を譲ってくれないし、その場所を得たからと言って御銭が揚がるとは限らない。だから、怪我をしようが入院しようが『だれにもできない芸』を目指すんです。」と言っていました。これは、商店街が「市場」だった頃にも言えることで、「この辺では誰も売っていないものを売る」ことが勝利につながり、そのために物通や貿易が生まれ 「商い=飽きない」に通じたのだと思います。私は、こういう気概を持った人たちが、日本の芸と経済を支えるのだと思っています。
さて、先日大阪市の橋下市長と文楽協会・文楽技芸員との意見交換のニュースが物議を醸しだしていましたが、やはり協会側の言い分は、役人の私から見ても既得権に胡坐を書いた似非芸人の戯言にしか聞こえませんでした。彼らは、なにか「日本の伝統芸能は保護されて当たり前、そうじゃなければ辞めちゃうよ。」と日本人に対して匕首を突き付けている気がしました。また、重要無形文化財保持者(人間国宝)が満足な暮らしをしていないみたいな話もありましたが、求道者が食えないのは当たり前のことです。所謂「工芸技術」系の人間国宝は、作品を作れば高価で売れるようになるので一生食うに困りませんが、「芸能」系の人間国宝は、マスコミや舞台に露出できる歌舞伎以外は五十歩百歩なのではないでしょうか。部門による差異はノーベル賞受賞者でも同じですし、オリンピックのメダリストはもっと如実に個人の資質がその後の生活を左右します。ただし、人間国宝には国から特別助成金として年間200万円が毎年支給されますし、芸術院会員となると年間250万円の報酬が得られます。これを「不労所得」と思われては国民が困るのです。重要無形文化財保持者の選定には、その芸を支える「団体」と「活躍の場」の盤石さを審査していますので、人間国宝は、「その芸道の存亡を国に託された立場」であり、自分を受賞まで引き上げてくれた協会の組織維持のみならず、技芸員や若手の育成も、その食い扶持となる「芸能」のあり方についても責任を負っていると思わなければなりません。こと「人形劇」であれば、世界中に常設劇場があり、世代を超えて毎日ひっきりなしにお客が訪れるところもあります。そういうものが真に「国民に根差した文化」であり、「なぜ大衆芸能であった文楽がそうならなかったのか?」は「なぜ黒子が人間国宝になりうるのか?」以上に疑問に思います。
結局、大衆と古典芸能を隔てる「権威の垣根」は、「年寄が体を壊して、正論を吐いた若造が謝る」という日本伝統の美意識で守られましたが、こういう騒動を見るにつけ、「木戸銭」や「投げ銭」一本で生活している芸人の潔さや、任意団体ながら「家元制度」という人脈・金脈のシステムを築いて、生きながらえている芸道の生命力の強さを再確認します。
私自身は、「滅ぶべきは滅びよ」というスタンスで、最も思い入れのある「香道」についても同じ気持ちでいます。むしろ、昨今は香木の品質が悟るに値しないものに劣化しつつあるので「滅びゆく者へのレクイエム」に近い活動をしているのか?とさえ思うことはあります。昭和初期の香道は、貴族文化の権威もあり、悟るべき香木も潤沢に出て来ましたから、折からの侘び寂び・高尚・雅の風に乗り、右肩上がりの経済にも支えられながら諸派を形成するほど拡大してきました。しかし、既に経済は混迷の度合いを深め、高みを望む香人は富裕層のサロンに回帰する動きもあります。一方、職業香人は、江戸後期の爛熟時代のように「和香木」を使って、所作 ・式法の伝授に走り、時代に迎合しつつ生きながらえる術を模索する必要に迫られるかもしれません。 いずれ、昭和初期に日の出の勢いだった「香道界」が、支える方々の高齢化と少ないお弟子を取り合うことになるために世代交代が滞るというジレンマに陥っていることは目にも明らかです。私はこのような趨勢を俯瞰するしか術はないのですが、香道の行く末を担う方たちにも「霜月」の到来をお告げしておきたいと思います。
今月は、一を聞いて十を知る修練の香「十一*柱香」(じゅういっちゅうこう)をご紹介いたしましょう。
「十一*柱香」は、早稲田大学図書館本の『外組八十七組(第六)』に掲載のある組香です。この筆者不詳で書写年不明の9冊9巻の組香書は 、とても読みやすい筆跡で書かれており、組香のラインナップも「外組」というだけあって目新しいものが多くあり、これから紹介したい組香書のひとつです。今回は、「十一月」に「十一*柱香」という駄洒落めいた発想から掲載を決めたものの、読み込 んでみれば、その内に秘められた作者の創意に感銘する部分が多々ある組香でしたので、これを出典として書き進めたいと思います。
まず、この組香の題号は「十一*柱香」となっています。香道を嗜んでおられる方ならば「あぁ、十*柱香みたいなものね。」と聞き方などは直ぐに察しがつく筈です。「十*柱香」は、組香の元祖で、最も古くは室町時代、応永3年(1416年)に歌合の御座で「十種香」が行われたとの記述が後崇光院の日記である『看聞御記』に見られますし、香祖として名高い三條西実隆の日記である『実隆公記』には文亀元年(1501年)4月10日に「十*柱香開筵」の記述があります。こうして始まった「十*柱香」が様々な創意を加えられて発展、継承、変化してきたものが現存する組香だと言えます。北小路功光著の『香道への招待』には、 組香発生の初動として「十*柱香」をアレンジした所謂「替十*柱香」が10組ほど紹介されていますが、その多くは試香の有無や要素の数を問わず「要素名が一、二、三、ウと匿名化 」されていること、「全体香数や本香数のどちらかが10」であることが共通点となっています。例えば、皆さんご存知の「有試十*柱香」は、試香が3つありますので全体香数は (4+4+4+1=)13で、本香数が(3+3+3+1=)10となるものが一般的ですが、全体香数が(3+3+3+1=) 10でそこから試香を焚き出すために本香数が(2+2+2+1=)7となる組香にも「十*柱香」という題号が付されています。
そうして、この組香は、小記録をしげしげ眺めると全体香数が(2+2+2+2+2+1=)11となっていますが、本香数は(1+2+2+2+2+1=)10となっていますので、「なぜ、これは十*柱香と呼ばれなかったのか?」が疑問として浮かび上がります。私が思うにこの組香は、最初に焚かれる「一」の試香が大変大きな役割を演じており、作者が「一を聞いて十を知る組香」という意味を込めて、本香とは別格に数に加え「十と一*柱香」と意識させかったのではないかと思います。また、 出典の前の「五種十香 試香なし」の組香を「二*柱十*柱香」(二*柱ずつの十*柱香)と題して記載してありますので、卑近には、巷に「十*柱香」が多すぎるため、「十と一*柱香」を意識してネーミングで独自性を表したのかもしれません。
次に、この組香の要素名は「一」「二」「三」「四」「五」「客」と匿名化されており、こ の点では「十*柱香」と共通しています。香種は6種となっていますので、小記録を見るなり「十*柱香」を知っておられる方は、その要素名の多さに驚くことでしょう。前述の「二*柱十*柱香」の香5種が「替十*柱香」の仲間では最多ですから、これに「客」1香を加えたことを「十*一柱香」と表しているのかもしれないという推測も 考えられます。このように香種が多いと「香組」も大変で腐心されると思いますが、後述する構造を考えると当日の組香の難易度を決める大事な作業となりますので、十分に時間をかけて組まれることをお勧めします。
続いて、この組香の構造は、大変興味深いものです。まず、香木は「一」「二」「三」「四」「五」は各2包、「客」は1包用意します。次に、出典には、「右一の香一包試香として、残十包を左の通りむすび合わせ置くなり。」とあり、香拵え(こう こしらえ)の段階で試香として焚き出す「一」を1包除いて、「一・二」、「二・三」、「三・四」、「四・五」、「五・客」と2包ずつ5組に結び置きします。その際には「前後打ち交ぜて結ぶなり。」とあり、組になった2包をあらかじめ打ち交ぜてから結ぶよう指定されています。さらに出典では「結び紙に一、二、三、四、五と番付をすべし。」とあり、それぞれの組には焚き順を間違えないように結び紙に小さく組番を 書き付けて置くこととなっています。「結び紙」を用いない場合は、香包の右肩に小さく組番を書き付けて置く方法もあるでしょう。また、番号自体が無粋と思われる方は、各組の前後だけ判らなければ良いので、試香の「一」を別にして、各組ごとに香包の色を変えても問題 ないかと思います。この組合せ指定の結び置きの所作がこの組香の重要な特徴の1つと言えます。
さて、香席では、まず香元が別にしてあった試香として「一」を焚き出します。連衆はこれを深く聞き込んで、万が一にでも聞き誤らないようにしなくてはなりません。試香が焚き終わりますと、香元は「一の組」の結びを解き、もう一度打ち交ぜます。このことは出典に指定された所作ではありませんが、香拵えの際にいくら打ち交ぜても、「今、この場で前後を打ち交ぜましたよ。」という所作を見せないと連衆が「一・二は、順番を変えずに出て来る」と誤解するので、結局は手前座で打ち交ぜることが必要だと思います。打ち交ぜが終わりましたら、本香包を仮置きし、最初の2炉を順に焚き出していきます。この 組香のポイントは、「組の順序は変えず、香包は組ごとに打ち交ぜて焚き出す」というところです。
ここで、「この組香には試香が1種しかないのに5種もある客香をどうして判別するのか?」という疑問が湧くことでしょう。その答えは前述の結び置きにあります。「一・二」、「二・三」、「三・四」、「四・五」、「五・客」と結ばれた各組の要素は、「客」以外は試香の時から連結しています。「一の組」では、試香で「一」が出ていますので、聞き合わせる同香は「一」となり、それ以外の異香は「二」と推量できます。「二の組」では、先ほど異香であった「二」の同香を聞き合わせ、異香の「三」を割り出します。このことは、出典に「初の一の香、試して覚え置く故、本香一番目のうちに一種異なりたる香出るを二の札打つべし。扨て、二番の内、二の香と思わば二の札打ち、別香と聞かば三の札打つべし。」との記載があり、その後も順次、「前の組で焚かれた異香」を「次の組の同香」と聞き合わせて、判別を続けていくこととされています。このように香の異同が連綿していくため、「最初に聞く試香の聞き込みが非常に重要」となるわけです。この連綿構造がこの組香の最大の特徴であり真骨頂となっています。
連衆は、こうして焚き出された香を前の組との香の異 同を判別しながら聞きすすみます。回答については、出典に「札打つべし」とあるように専用の「香札」を使用します。札については、出典に「札の表、常のごとし。裏、一 一枚、二 二枚、三 二枚、四 二枚、五 二枚、客一枚なり。」との記載があります。 仮に、出典のとおりに行うのであれば、香元が「一の組」の2つの香炉に添えて、「一」「二」と表書きされた「折居」を2枚廻します。連衆は、2つの香炉を聞き、異同を判別してから、試香と同じ香が出た折居に「一」の札を打ち、違う香の出た折居に「二」の札を打ちます。「二の組」では、「三」「四」と表書きされた折居に「二」「三」の札を投票します。折居の表書きは香炉の番号として「一」から「十」までありますので、最初のうちは要素名と混同しないよう注意が必要です。また、 出典には「二*柱開」等の記載はないため、 回収された折居の香札は、一度(盤者がいる場合は盤者が、いない場合は執筆が)、札盤に各自ごとに縦に伏せて並べて置き、本香が焚き終わってから香札を開き、執筆が香記に書写する方式が順当でしょう。現在では専用の香札を作ることは難しく、香種が多いため「十種香札」を流用することも難しいので、 香炉が全部回ってから名乗紙に全ての答えを書き記して提出する「後開き」で催行するのがよろしいかと思います。
因みに「札の表、常のごとし」とは、 各自の名乗となる「札の紋」を「○松」「○竹」「○梅」「○桜」「○柳」と季節と草木を合わせた二文字の類 にすることかと思います。なお、出典の「十一*柱香之記」の記載例を見ますと、この組香では名乗(札の紋)の右肩に連衆の名前を併記する形式をとっています。
この組香は、かなり難度が高く上級者向けであるとも言えます。十*柱香も ある意味「香の異同」を聞き分ける修練として行われるものですから、それの極みとも言えるでしょう。それでも「こんな組香は難しくて判らないわ。」という方のために「香の陰陽」を交互 にラインナップしておくことを組香者にお勧めします。そうすれば、各組ごとに焚かれる香の印象が陰陽でもはっきりするので、香の異同の判別にそれほど苦労しなくて済むのではないでしょうか。五味は各流派によっても区々ですが、陰陽は押しなべて同じなので、これは流派に関わらず使える手法かと思います。(今回の小記録はそのように香組しています。)
この組香の記録に関しては 、「十*柱香」と同様のイメージでとらえていただいて結構かと思います。 本香が焚き終わりましたら、札盤の香札を開いて、執筆は答えを全て書き写し、香元に正解を請います。香元が正解を宣言しましたら、執筆は香の出の欄に要素名を出た順に縦一列に書き記し、横に見合わせて当った要素名に合点を掛けます。点数は、要素名の当りにつき1点と換算します。独聞や「客」の当りに関する加点要素はありません。下附は、全問正解には「全」、その他は点数を漢数字で書き記します。
最後に勝負は、最高得点者のうち上席の方の勝ちとなります。
昔の宗匠は「香道の真髄はその式法にあり、組香などは稽古を面白く続けるための道具に過ぎない。ましてや組香の成績など何も頓着することはない。」と言われましたが、連衆の身になれば、当否一つ一つに頓着しますし、競争心もないわけではなく、香記も欲しい!というのが正直なところだと思います。文学的な脚色もなく、一見無味乾燥にも思える 元祖「十*柱香」ですが、単純な「香の異同の聞き分け」にこだわる修練を踏んだ方が、その先の「鑑賞」という道が豊かに開かれるのも事実です。皆様も「十一*柱」で一本の綱を渡るようなスリリングな聞き当てゲームを極めてみませんか?
「伝統」の核の部分を残しつつ
「迎合」ではない「異化」を受け入れるのも文化を担う者の定めかもしれません。
小春日の君が袖香ぞ匂いたつまどろみぶりて深くそを聞く(921詠)
組香の解釈は、香席の景色を見渡すための一助に過ぎません。
最も尊重されるものは、皆さん自身が自由に思い浮かべる「心の風景」です。
![]()
Copyright, kazz921 All Right Reserved
無断模写・転写を禁じます。
