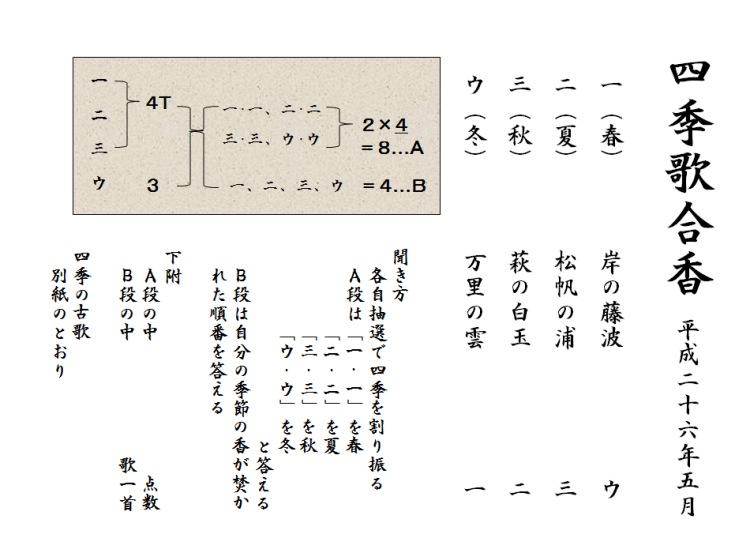
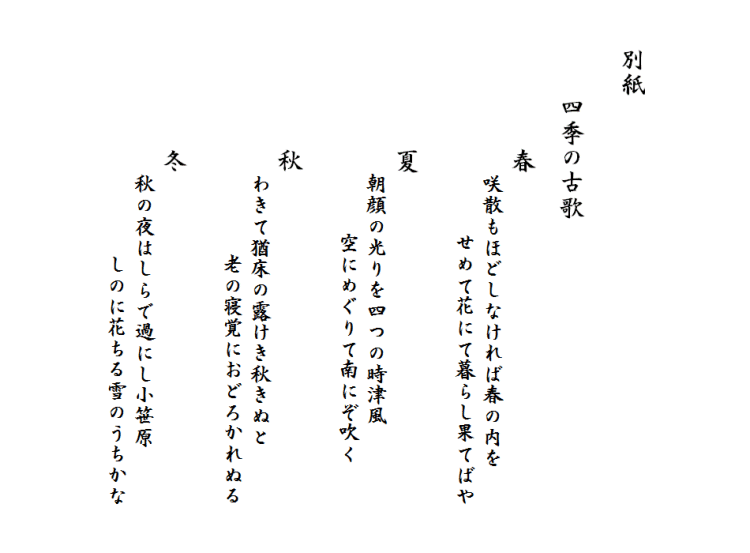
|
|
説明 |
|
香木は、4種用意します。
要素名は、「一(春)」「二(夏)」「三(秋)」と「ウ(冬)」です。
香名と木所は、景色のために書きましたので、季節や組香の趣旨に因んだものを自由に組んでください。
「一」「 二」「三」は各4包、「ウ」は3包を用意します。(計 15包)
あらかじめ席入りの際に抽選等で「春」「夏」「秋」「冬」の担当を決め、「春夏秋冬」の順に着座します。
「一」「二」「三」の各1包を試香として焚き出します。(計3包)
手元に残った「 一」「二」「三」と「ウ」の各3包を下記の通り5組に分けて結び置きします。
「一・一」、「二・二」、「三・三」、「ウ・ウ」(2包×4組)
「一、二、三、ウ」(4包×1組)
まず、「一・一」、「二・二」、「三・三」、「ウ・ウ」を組ごとに打ち交ぜて、順に焚き出します。(2包×4組)
本香A段は、8炉廻ります 。
次に、「一、二、三、ウ」を打ち交ぜて、順に焚き出します。(4包×1組)
本香B段は、4炉廻ります 。
本香A段の回答は、「一・一」は「春」、「二・二」は「夏」、「三・三」は「秋」、「ウ・ウ」は「冬」と名目を4つ名乗紙に書き記して提出します。
本香B段の回答は、 4炉のうち自分の担当する季節の香が焚かれた順番の「番号」を1つ同じ名乗紙に書き記して提出します。
本香A段の点数は、 名目の当たりにつき1点とします。(4点満点)
本香B段は、 番号が当たった場合のみ、季節の歌1首を書き記します。(委細後述)
下附は、本香A段の点数と本香B段の歌が書き付されます。
勝負は、正解数の最も多い上席の方の勝ちとなります。
早起き鳥の声しげく、寝覚めを急かされる季節となりました。
朝起きますと空は清々しく晴れていて、洗濯好きの私などは一日中洗剤の匂いにまぎれて、寝具などの厚物を洗うのが、連休の楽しみとなっています。先月、岩倉市の五条川に桜を見に行った際、桜花の舞い散る川面に鯉のぼりを木枠に張って浮かべ、刷毛で糊を落とす「のんぼり洗い」を見ることが出来ました。岩倉市には「旗屋中島屋代助商店」という古い幟屋(のぼりや)があり、近くの五条川で「大寒」の頃から寒晒しの作業をしています。桜まつりの時期には、観光客向けに鯉のぼりを晒しており、伝統技術の物珍しさも手伝って「五条川の原風景」として多くの人に親しまれています。
鯉のぼりの起源については、以前にご紹介したことがありますが、端午の節句には「菖蒲」ということで、菖蒲が「尚武」を祈る行事になり、武家では武具や旗指物を虫干しがわりに飾っていたのですが、これを豪商等が真似をして、武具の模造品を作って内飾りとし、旗指物の代わりに中国の「登竜門」の謂れから「鯉」を外飾りとして掲げるようになって、江戸中期の町人文化に定着したようです。愛知県は、武家文化の根強い土地柄ですし、お雛様の産地としても有名ですので、そこから内飾りの五月人形が派生し、外飾りの鯉のぼりも作られるようになったのでしょう、 今では「鯉のぼり日本一」の埼玉県加須市に次ぐ生産量を誇っているようです。
鯉のぼりは、「男児の初節句に母方の実家が買い求めて贈る」というところは、お雛様と同じですが、内飾りと外飾りがあるので、両家で分担しても良いようです。 また、いつまで掲げて置くものかと思いましたら、「5月5日の1か月前、遅くとも1週間前に掲げましょう。(日本鯉のぼり協会)」とあり、一説には二十四節季の「清明(4月4日頃)に掲げる」というものもありますので、目安としてはこの辺かなと思います。片付ける時期については、「5月末までは掲げておきましょう。」ということですので、お雛様のように「早く片付けないとお嫁の貰い手がなくなる」というような決まりはないようです。お雛様には「早く仕舞わないと梅雨になり、お人形にカビが生える」という謂れもありましたが、旧暦5月は初めから梅雨時期なので、末頃まで飾って梅雨明けに仕舞おうということなのかもしれません。
もう一つ、「鯉のぼりは何歳まで飾るか」については、子供の健康な成長と立身出世を願って飾るものという由来からして、「初節句から元服(15歳)までが限度」ということでした。女子は、結婚適齢が引き上げられ、現代でも「お嫁に行くまで」お雛様を飾っておけますが、男子は昔の立身適齢を堅持したままとなっていたのは不思議でした。現代の男子は、鯉のぼりの掲揚を恥ずかしがる割には、いつまでたっても立身出世を願わない「お子ちゃま」なので、毎年、鯉のぼりを立ててやりたい親心もあっていいかなと思います。いずれ、5月の風にたなびく鯉のぼりの姿をもう少し目にしたい昨今ではあります。
今月は、歌人に成り代わって季節の歌を詠む「四季歌合香」(しきうたあわせこう)をご紹介いたしましょう。
「四季歌合香」は、聞香秘録の『香道後撰集(下)』に掲載のある組香です。同名の組香は志野流香道目録の分冊と見られる『三十組目録』(大阪府立図書館本)にも掲載があり、現代書では有賀要延著の『香と仏教』にも掲載されています。これらについては、点法や記録法等に微妙な相違はあるものの、基本的な構造や表そうとする景色 も同じと言っていいでしょう。志野流の三十組ということは初伝前に習得する基本的な組香ということになりますが、『三十組目録』に掲載された組香はなかなか複雑な趣向の凝らされている組香です。 また、同名異組では、聞香秘録の『香道しのすすき(下)』に「後陽成院御作」の組香も残されており、こちらは要素名が「春」「夏」「秋」「冬」「恋」の五種組となっています。今回は、「宝暦三年酉正月」(1753)と最も古い『香道後撰集』を出典とし、『三十組目録』や『香と仏教』の記述も織り交ぜながらご紹介したいと思います。
まず、この組香に証歌はありませんが、出典には各自の成績を表す際に用いられる「四季の古歌」が以下のとおり4首掲載されています。赤字で示した部分については、伝書によって微妙に用字の異なるものがありますので、①『香道後撰集(下)』、②『三十組目録』、③『香と仏教』として併記しておきましょう。
春
① 咲散(さきちる)もほどしなければ春の内をせめて花にて暮らし果てばや
② 咲散(さきちる)もほどしなければ春の内をせめて花にも暮らし果てばや
③ さきちるもふとしなければ春のうちをせめて花にぞくらしはてばや
夏
① 朝顔の光りを四つの時津風空にめぐりて南にぞ吹く
② 朝顔の光りを四つの時津風空にめぐりて南へぞ吹く
③ 朝々のひかりをたづの時津風空にめぐりて南にぞ吹く
秋
① わきて猶(なお)床の露けき秋きぬと老の寝覚におどろかれぬる
② わきて猶(なお)床の露けき時来ぬと老の寝覚におどろかれぬる
③ わきてなほ床の露けき時きぬと花のねざめぞおどろかれぬる
冬
① 秋の夜はしらで過(すぎ)にし小笹原しのに花ちる雪のうちかな
② 秋の色はしらで過(すぎ)にし小笹原しのに花ちる雪のうちかな
③ 秋の色はしらで過(すぎ)にし小篠原しのに花ちる雪のうちかな
それでも、「私の習っているものと違うぞ」と感じる方がいるかもしれませんが、『国歌大観』によっても原典や詠人に尋ね当たりませんでしたので、どれが正当と言い切ることはできませんでしたのであしからずご了承ください 。
次に、この組香の要素名は「一」「二」「三」と「ウ」となっていますが、出典では「一 春と名付」と各々の要素に付記されていますので、各要素がそれぞれ「春」「夏」「秋」「冬」を表すことは自明となります。他書では「この時点」で季節と要素を紐付けする記載はありませんが、後段で同じように関連づけられることになります。
さて、この組香の構造は、香種は4種、全体香数は15香、本香数は12炉となります。まず「一」「二」「三」を4包ずつ、「ウ」は3包作ります。このうち「一」「二」「三」は各1包を試香として焚き出します。すると各要素とも3包ずつ残りますので、まず、「一」「二」「三」「ウ」の各1包ずつ引き去って1組に結び置きしましょう。そして残った8包を「一・一」「二・二」「三・三」「ウ・ウ」と同香2包を4組にして結び置きします。
これについて出典では「右試み終りて、本香春夏秋冬3包づつの内、壱包づつ取り除き、残る二包づつ四結を打ち合せ…」と記載がありますが、「二包づつ」の組み合わせ方については記載がなく、「四季 歌合香之記」の香の出をみて推測するしかありません。一方、『三十組目録』には「一と一結び合わせて春の香とし、二と二の香を合わせて夏の香とし・・・」と『香と仏教』では、「・・・三と三と結びて秋。ウとウと結びて冬」と結び合わせ方が指定されています。他書については、要素名は匿名のままでしたが、本香の組合せの時点で季節との紐付けがなされるようになっています。
ここで、この組香は、自分の担当する季節(以下「我が季」)をあらかじめ決めて置くこととなっています。出典では「先ず名乗紙に春夏秋冬四季の文字を一字宛書きて、富のごとく連中取るなり、当りにしたがひ四季誰々に座を組むなり。」とあり、名乗紙に書いた季節の文字をくじ引きすることで「我が季」が決まり、席次も「春夏秋冬」の順に座ることが指定されています。この点『香と仏教』では、「記紙の内に四季の歌を一首ずつ人数分書いて・・・。」とあり、なお雅趣に富むものとなっています。このように、この組香は「四季の古歌」をモチーフにして、連衆があたかも歌人としてそれを詠んだかのような状況を作り「歌合」をするということが趣旨となっています。
因みに、この組香は、四季を割り当てることから最低催行人員は4人名となり、追加分は春夏秋冬を順に使いまわす形で良いようです。私はなんとなく「客香」を聞き当てなければならない「冬の人」が不利なような気がしてなりませんがいかがでしょうか。
続いて、本香A段は、最初に作った2包4組を「組ごとに打ち交ぜて」8包を順に焚き出します。結びを解いても同香の組ですので打ち交ぜる必要はありません。連衆はこれを聞き、2炉ごとに季節を定めて名乗紙に「春」「夏」「秋」「冬」の4文字を出た順に書き記します。「どうして同じ香を結びつけるのか?」「お香がもったいない!」とお思いの方もいらっしゃるでしょう 。これは和歌の各季節の「上の句」「下の句」が正しく構成されているということを表しているものと思われます。「情趣のためには香の消費量などなんのその」で催行できた時代がうらやましいですね。
そうして、本香B段は「一」「二」「三」「ウ」を打ち交ぜて順に4包焚き出します。連衆は「我が季」の香りだと思うものを探し当て、その他の香は聞き捨て、「我が季」が焚き出された順番を漢数字で書き記します。
本香が焚き終わり、名乗紙が戻って来ましたら、執筆は、各自の答えを全て香記に書き写します。その際、出典では各自の名乗を「春座」「夏座」「秋座」「冬座」と仮名にして書き付けてありますが、『三十組目録』では、各自の名前の右肩に季節名を小さく書き付けています。これについては、後者の方が人数の増減に対応しやすく現実的かなと思います。
答えの書き写しがおわり、執筆が正解を請う仕草をしましたら、香元は香包を開いて正解を宣言します。A段では同香が出るのがわかっているのですが、 「上の句」「下の句」をあらわすものですから、正解は省略せず逐一宣言しましょう。正解が宣言されましたら、執筆は香の出の欄に正解を書き写します。その際、出典の「四季歌合香之記」の記載例によれば、A段の4組はそれぞれ要素名を横に並べて2列4段に書き、B段はその下に1列に書き記します。また、B段の答えの上には「後」という文字を記載して区別しているところが他書にはない特徴です。
そして、執筆は要素名の組合せから正解の季節を定め、各自の答えの右肩に合点を付していきます。答えの季節名の構成には2つのが要素名含まれていますが、出典では合点は通常の点とし「長点」を付していません。また、この組香では独聞、客香の聞き当て等に加点要素はありません。
この組香の下附については、やはり書物によって異なります。出典では、A段の解答欄の下にまず得点を記載します。この時、A段の点数は季節名の当たり1つにつき1点と換算し、全問正解は「四」です。そして、B段の正解者には「四季の古歌」から「我が季」の歌を1首書き記して当ったことを示します。出典によれば、各自の記録は、上から「名乗(仮名)、A段の答え、A段の点数、B段の当たりを示す和歌1首」と4段で記載されます。
一方『三十組目録』では、同じくA段の解答欄の下に得点を記載しますが、その下には、A段で「我が季」を当てれば季節の歌の上の句、B段で「我が季」を当てれば季節の歌の下の句が記載され、両方聞き当てると1首書き記されます。さらに、B段の聞き当たりを1点として、その下に最終得点を書き記し、全問正解すれば「全」と下附されます。
さらに『三十組目録』では、「春・夏、秋 ・冬等、二人一組となり、『我が季』を聞き当てた数で勝負を競う対抗戦」というルールもあります。例えば、春座と夏座の対決の場合、春座の方がA段・B段ともに「我が季」を聞き当て、夏座の人はB段のみしか「我が季」聞き当てていないと「春座の方」に総合点とは関係なしに下段の点数の上に「勝」の文字が付記されます。また、「我が季」を聞き当てた数が同数かどちらも聞き当らなかった「引き分け」の場合は、両者に「持」の文字が付記されます。因みにこのルールでは「負」は記載しないこととなっています。このように二人一組の対戦が同じ香席の中で繰り広げられるというのは、面白い趣向だと思います。
そして、『三十組目録』の場合の各自の記録は、上から「季節と名前、A段の答え、A段の点数、我が季の聞き当てを表す上の句と下の句、二人勝負の記録、B段の当否を含めた最終得点」と6段構えになるというわけです。
最後に勝負は、総合点の最も高い方のうち上席の方の勝ちとなります。
新暦の5月は、空気が乾燥してお香には向かない季節ですが、各要素を2つずつ聞くことができれば間違いも少ないかと思います。少し贅沢ですが、皆様も香木を少し多めに切って「四季歌合香」で初夏の歌 会を催してみませんか?
歌合は基本的に「遊び」ですが、昔は出世にも大きく関わる行事でした。
私も現代人としては、よく歌を詠む方なのですが・・・
禄高が「鯉の滝のぼり」ということは、とうとうありませんでしたね。
一声を待ちて更けぬる片袖に君にしあればいかが過ぐべき(921詠)
組香の解釈は、香席の景色を見渡すための一助に過ぎません。
最も尊重されるものは、皆さん自身が自由に思い浮かべる「心の風景」です。
![]()
Copyright, kazz921 All Right Reserved
無断模写・転写を禁じます。