九月の組香
![]()
![]()
春と秋とが情趣の深さを比べるという組香です。
春秋の優劣が決まったところで季節に因んだ和歌を書き添えます。
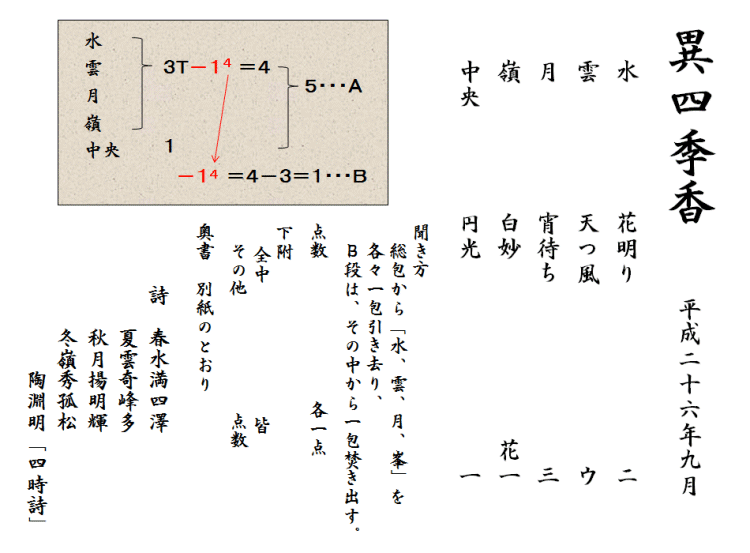
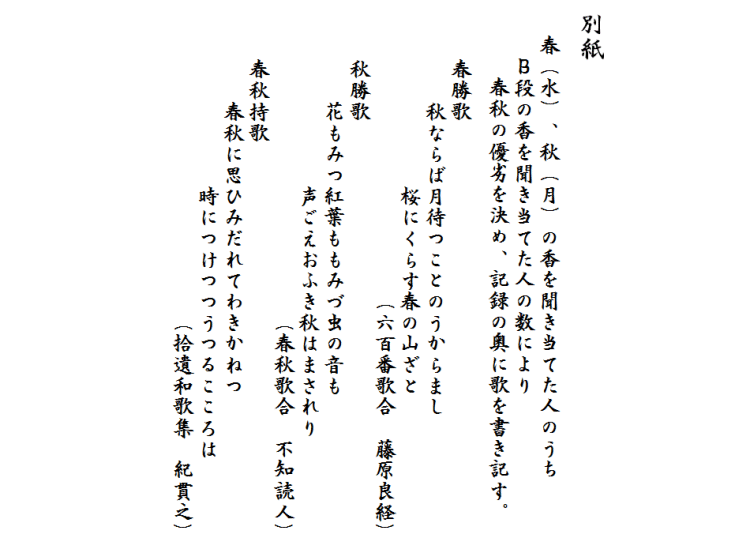
|
|
説明 |
|
-
香木は5種用意します。
-
要素名は、「水」「雲」「月」「嶺」と「中央」です。
-
香名と木所は、景色のために書きましたので、季節や組香の趣旨に因んだものを自由に組んでください。
-
「水」「雲」「月」「嶺」は各3包作り、「中央」は1包作ります。(計13包)
-
「水」「雲」「月」「嶺」のうち各1包を試香として焚き出します。(計4包)
-
また、「水」「雲」「月」「嶺」のうち各1包を引き去り、結び置きします。(−14=4包)
-
手元に残った「水」「雲」「月」「嶺」のうち各1包に「中央」を加え、打ち交ぜて焚き出します。(計5包)
-
本香A段は、5炉廻ります。
-
続いて、結び置きした「水」「雲」「月」「嶺」各1包を打ち交ぜて任意に3包を引き去り、手元に残った1包を焚き出します。(4−3=1包)
-
本香B段は、1炉廻ります。
-
連衆は、試香と聞きあわせて名乗紙に要素名を6個書き記します。 (A段5+B段1=6)
-
執筆は香記に連衆の答えを全て書き写します。
-
香元は、香包を開いて、それぞれ正解を宣言します。
-
執筆は、香の出から正解の名目を定め、当たった答えの右肩に点を掛けます。
-
点数は、要素名の当たりにつき1点とします。
-
下附は、全問正解には「皆」、その他は点数で書き記します。
-
本香A段のうち、「水」のみが当たった人(春方)と「月」のみが当った人(秋方)とに分けます。
-
双方でB段の正解者数を比べて優劣を決め、勝方となった季節の和歌を奥に書き記します。
-
勝負は、個人戦で、最高得点者のうち、上席の方の勝ちとなります。
猛暑も去り、降り続く秋雨にも心を癒される季節となりました。
『香筵雅遊』も おかげさまで開設1 7周年を迎えました。皆様方には日頃のご愛顧に感謝申し上げます。「今月の組香」も今月で193組目となり、順調に行けば来年春には200組目を迎えることとなりそうです。 単身赴任中のため、諸事・雑事の多い日常に加え、「覚えながら忘れていく」老いさらばえた頭脳も心許ない限りですが、もともとパソコン仕事で始めたことですので、眼が見え、手が動く限りは書き続けて参りたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
今年の夏も猛暑続きで、最高気温が35℃を下回れば「涼しい」、最低気温が28℃を下回れば「今夜は寝られる」と思えるような日々でした。そのような中、台風の影響もあって風雨が続く週末があると、被害にあわれた方には大変申し訳なくも「今日はいい天気だな。」と呟いてしまう私がいました。銀の竹が地面に突き刺さるような雨の日は、一日中出歩くこともなく、平日の仕事で火照った心身を癒し、落ち着いた心から生まれてくる「よしなしごと」を思いめぐらし、書き綴るなどして暮らします。また、溜まった歪みを掻き回して「まとも」に戻ろうとしているエネルギッシュな地球の姿を見るのも嫌いではなく、自分自身も「まとも」に戻っていく気がします。晴れた週末となりますと、少々疲れても各地のお祭りや花火 大会に出かけてしまう性格ですので、「晴遊雨寝」程度のグウタラ感が老年の身体には丁度いいペースというところでしょう。
名古屋は、大きな川に囲まれ水害の記憶もあることから、住民の多くは「降雨」に対して非常に敏感で、雨の降る日は押しなべて「天気が悪い」と言います。しかし、東北人の私は、外出しているときに雨に見舞われれば、「都合が悪い」とは感じますが、雨の日を「天気が悪い」と思ったことはありません。晴天は清々しく心も晴々しますので、私自身も一般的な挨拶としての「いいお天気ですね。」は、晴れの時に使います。一方、雨の日でも傘の似合う麗人や物知り顔の文化人の方には「結構なお湿りですね。」を使います。(どう見ても晴れを期待して生きているゴルフ焼けやビール好きの人には決して使いません。)人間だれしも「晴れが続けば雨が欲しい。雨が続けば晴れが欲しい。」と思っており、結局「いいお天気」とは、その人にとって「今、都合の良いお天気」のことを示す相対的なものなのだと思います。
その点、プロの気象予報士は、雨は全ての人に悪いものだとは限らないことを心得ていて、雨でも「天気が悪い」とは言わないそうです。事実、中東の遊牧民は、太陽の日差しと乾燥が過酷な土地なので、雨降りのことを「いい天気」と言います。また、東北や北陸も冬場に過酷な天候が続きますので、晴天でなくとも雪や風が無く、日中の気温が0℃前後の過ごしやすい日であれば、少々曇っていても「いい天気」と言い、辛抱強い分だけ「いい天気」の幅が広くなります。一方、雨が降るべき時に降らないと収穫に影響する農家の方でも、日照りが続いて収穫に影響がありそうな時は、「いい天気すぎて困るよね〜」と晴れを肯定した言い廻しになり、流石に雨を「いい天気」と は言わずにに「いいお湿りだね〜」程度に止まりとなります。やはり、生命を育み、作物を育てる根幹となる「お天道様」に向かって「悪い」とは、なかなか言えないのが人類共通の心情ということでしょう。
陽光の対極にあるような雨も地球の大切な循環から生まれる「恵みの雨」で、そこからもたらされる「水」は森羅万象にとって無くてはならないものです。地球上に生息している限り、太陽と水に「良し悪し」は付けられないのは当たり前です。すべての天気は「どこかの誰かにとって、いい天気」なので、自分の立ち位置と都合だけで「いい天気」を決めず、「日々是好日」と思って、その日なりの楽しみ方を見つけるのも人生を無駄に暮らさない秘訣ではないでしょうか。日本には四季があり、「春夏秋冬」もそれぞれに趣がありますので、我執(恒常・不変の自我)を捨てて、その季節に向いた暮らし方をすれば、日本人の人生は4倍楽しいということにもなります。
今月は、四季を要素に春と秋とが趣きを競う合う「異四季香」(い_しきこう)をご紹介いたしましょう。
「異四季香」は、聞香秘録『香道春雨記(全)』に掲載のある組香です。題号の下には「東福門院御作」とあり、御水尾天皇とともに香道を嗜んだことで有名な東福門院和子樣が創作された組香であることがわかります。題号に「異」と付くということは、オリジナルの「四季香」があったのだろうと思い、蔵書群を調べてみましたところ「四季香」と名のつく組香は複数あり、どれも魅力的なものでした。まず、同じ聞香秘録の『香道春の山(全)』の「四季香」は香4種で要素名が「子の日」「七夕」「ウ」「客」となっており、基本的には春秋の景色の対比で作られていますが、要素名の組み合わせによって結ばれる「聞の名目」が四季の景色に展開するものでした。次に米川流香道『奥の橘(月の巻)』の「四季香」は、香5種で要素名が「春」「夏」「秋」「冬」「客」となっており、試香がないため所定のとおり結び合わせた2包の初後の香の数から、最終的に「初香に3つ出たものは春」「2つ出たものは夏」等と要素名を推量する難度の高いものでした。さらに、近代の刊行本となりますと東福門院作のものが「四季香」となっており、有賀要延著の『組香と仏教』は、『香道春雨記(全)』とほぼ同様の記述です が、杉本文太郎の『香道』は要素名が「春水」「夏雲」「秋月」「冬峯」「詩」「歌」と香種香数も変わり、聞き方や記録法も異なっており、派生組の様相を呈していま した。
「四季香」は『御家流香道要略集』では「十八組」、『香道伝授目録(御家流)』の「三十組」に属する基本的な組香であったことがわかるのですが、組香の小引が残されておらず内容は判りませんでした。ここからは私見ですが、金鈴斎居由が諸家の伝本を書写して『聞香秘録』を編纂していく際、同じ宝暦三年(1753年)に別の香道家から伝書を借り受けた居由は、前巻の『香道春の山』(藤井氏伝)で「四季香」の題号を使ってしまったため、次巻の『香道春雨記』(蜂谷氏伝)では「異」を付けて区別したのではないかと思います。ところが、『香道春雨記』の「異四季香」は、もともと「東福門院御作」のブランドを持っており、志野流宗家となる蜂谷氏の伝承であることとが相まって、時代を経ていく間に「四季香」として志野・御家両流に一般化したのではないかと思っています。このようなことから、今回は『香道春雨記』を出典として、他書との相違にも言及しつつ書き進めて参りたいと思います。
まず、この組香には、景色の前提となる「詩」があります。漢詩を題材にして作られた組香は「重陽香(秋日東郊作…)」「徒然香(上陽白髪人…)」や「菊花香(花寒菊点叢…)」などが見られますが、出典では「陶淵明詩」として各要素名の下に一句ずつ下記の詩が書き記されています。
春水満四澤 (しゅんすいしたくにみち)
夏雲奇峰多 (かうんきほうおおし)
秋月揚明輝 (しゅうげつめいきをあげ)
冬嶺秀孤松 (とうれいこしょうひいず)
これは、中国晋代の詩人である陶淵明の「四時詩」と呼ばれる秀作です。「四時」とは「四季」のことで、この詩は、まるで和歌の折句のように「春・夏・秋・冬」を各句の筆頭に折りこんでいます。意味は、「春は雪解けの水が四方の沢に満ち、夏の雲が見せる変わった形の峰が多い、秋の月は明るく輝き、冬の嶺には一本の松がしっかりと立派に立っている。」というところでしょうか。この詩は、茶道の「一行物」としても重宝されていて、それぞれ季に応じた各句が床の間に掛けられたりしています。このように、この組香は「四時詩」を題材に、四季それぞれが見せる美観の素晴らしさをお香によって連衆の心に呼び起こすように作られています。
次に、この組香の要素名は、「水」「雲」「月」「嶺」と「中央」となっています。これは出典を見ると一目瞭然なのですが、それぞれが「春」「夏」「秋」「冬」に掛かり、各句の2文字目を構成している字です。この点について志野流系(藤野家)の伝書である『香道』では、要素名を「春水」「夏雲」「秋月」「冬峯」と2文字で配していますので最も端的に分かります。また、客香の「中央」について、五行思想から来る五色の「黄色」や五時(=節)の「土用」(立夏・立秋・立冬・立春近くに4回ある)のように「真中にある」「どれにも付く」と言ったニュートラルな存在として取り扱っています。
因みに『香道』では、四季の要素に「ウ」と「客」が加わり、これらはそれぞれ「詩」と「歌」を意味するものとして取り扱われていますので、表す景色が若干異なっています。
さて、この組香の構造は、香5種、全体香数13包、本香数6包となっています。まず、「水」「雲」「月」「嶺」を3包ずつ作り、「中央」は1包作ります。次に「水」「雲」「月」「嶺」の各1包を試香として焚き出します。すると手元には「水」「雲」「月」「嶺」が2包ずつ残りますので、このうち1包ずつ4香を引き去ります。そうして残った「水」「雲」「月」「嶺」の各1包に「中央」1包を加えて打ち交ぜ、本香A段を5炉焚き出します。本香A段を焚き終えたところで、先ほど引き去っておいた「水」「雲」「月」「嶺」の各1包を打ち交ぜ、この中から任意に3包を引き去り、最終的に手元に残った1包を本香B段として焚き出します。引き去った3包は総包に戻して「捨て香」とします。
本香が焚き終わりましたら、連衆は廻された名乗紙に本香A段5つとB段1つの答えを少し離して出た順に要素名で書き記します。名乗紙が帰って参りましたら、執筆はこれを開き、各自の回答を全て書き写します。書写が終わりましたら香元に正解を請い、香元は香包を開いて正解を宣言します。執筆は、正解を香記の香の出の欄に書き記し、当たった要素名の右肩に合点を掛けます。合点を 掛け終えましたら下附をします。点数は、客香である「中央」も含めて、要素名の聞き当たりを1点として漢数字で書き付します。全問正解については、「異四季香記」の記載例にないので「皆」とすべきか「八」とすべきか迷いましたが、御家流の基本の組香であれば「皆」とするのが順当かと思います。
因みに『香道』では、志野流系らしく「全」と下附してあり、さらに香席の設けられた季節に応じて「四時詩」の一句を傍らに書き付すという趣向も見られます。
続いて、この組香の香記に「詩」は記載せず、連衆の当たり具合によって和歌を一首奥書するという特徴があります。このことについて、出典では「さて、春の水、秋の月の香、両人にてもいくたり(幾人)にても春秋を聞き当る人は勝負を決させる也。夏、冬聞き当るばかりは構わず。勝負は、除き置きたる四包の香、一包取り出し焚き、聞き当てたるを春聞き当てたる人多ければ春を勝ちとす。秋も同じ。」とあり、「水」と「月」を聞き当てた人たちのうちB段の香を聞き当てている人の数により、春秋の勝負が決まるようになっています。
このことについてもう少し詳しく手順を示しますと、まず連衆のA段の成績を見て「水」と「月」が両方当った人と両方外れた人はB段の当否にかかわらず捨象します。これは、A段で「春」と「秋」とが必ず相殺されて「中立」になってしまうからです。次に「水」が当たって「月」を外した人を仮に「春方」のメンバーとし、「月」が当たって「水」を外した人を仮に「秋方」のメンバーにします。そして、「春方」と「秋方」との間で「B段の一*柱を聞き当てた人の数」を比較し、その人数が勝っている方が「勝ち方」となり、同数の場合は「持ち」となります。その結果により、下記の和歌を書き記すこととされています。
春勝歌
秋ならば月待つことのうからまし桜にくらす春の山ざと(夫木和歌抄1558 後京極摂政)
秋勝歌
花もみつ紅葉ももみづ虫の音も声ごえおほき秋はまされり(春秋歌合31 不知読人)
春秋持歌
春秋に思ひみだれてわきかねつ時につけつつうつる心は(拾遺和歌集509 紀貫之)
「秋ならば・・・」の歌は、建久3年(1193年)に藤原良経主催で催された『六百番歌合』のなかで「遅日」を詠題として詠まれた歌です。『六百番歌合』の129番には詠み人が「女房」とされていますが、後京極摂政である藤原良経が詠んだというのが定説です。
「花もみつ・・・」の歌は、応和3年7月2日(962年)に開催された『宰相中将君達春秋歌合』の31番に「女御のはるの御心よせふかかなりとて、あきの御方より、もみぢ、はな、むしなどものにいれて」という詞書に続いて「花も咲く紅葉ももみづ虫の音も声ごえおほく秋はまされり(あきの御方)」とあります。出典とは、下線部に2点ほど相違がありますがおそらく間違いないでしょう。
「宰相中将」とは一条摂政藤原伊尹(これただ)、「君達(きんだち)」は、親賢、惟賢、挙賢、義孝、義懐、冷泉院女御の懐子と言った彼の子女であり、秋に心を寄せる母親の桃円宮恵子女王と春に心を寄せる叔母の麗景殿女御荘子女王をそれぞれチームリーダとして歌の応酬を繰り返しています。身内の歌会だったため、詠み人はチーム名で「はるの御方」「あきの御方」となっており、誰が詠んだのかは判りませんので小記録には「不知読人」としています。
「春秋に・・・」の歌は、『拾遺和歌集(雑下)』の中で「あるところに春秋いづれかまさるととは給ひけるに、よみてたてまつりける。」という詞書に続いて詠まれており、紀貫之は、春秋に敢て勝敗を決するつもりはなく、春秋折々の情趣に捕らわれる心を詠みあげています。
因みに『香道』では、春秋持歌は同様ですが、春勝歌として「花鳥の色香匂いてひとこころ浮たつはるにしく時ぞなき」、秋勝歌として「花野ゆき紅葉かざしつ蟲の音もとりどり多き秋ぞまされる」と掲載されています。(いずれも『国家大観』に該当なし) さらに、『香道』と『香と仏教』の「四季香」は、連衆を「春方」「秋方」の2チームに分けて勝負を争う一蓮托生型対戦ゲームの趣向ですので、合計点での勝った方の歌が香記に記載されます。
この組香は、こ非常に煩瑣な「春秋の勝負」の決し方なのですが、「正解が出るまで誰が敵か味方かわからない」ところにワクワク感があり、流石に殿中遊びの達人である東福門院樣の作だけあって、良く工夫されていると思います。
最後に、春秋の勝負は、記録の奥に書く和歌を決めるだけのものですので、組香の勝負は個人戦に戻り、最高得点者のうち上席の方の勝ちとなります。
私は、冬枯れに向かう最後の彩りである紅葉をはじめ「もののあはれ」を感じる「秋に心を寄せる派」ですが、やはり萌えいずる新芽や咲き誇る花を見ると、春にも心を魅かれずにはいられません。皆さんも「異四季香」で紀貫之が「わきかねつ」と詠った春秋の趣をそれぞれに味わってみてはいかがでしょうか?
春に生まれて梅・桃・桜の下で死ぬのが望みの私ですが…
人恋しくてアンニュイなことが許される秋の方が「生きやすい」と感じます。
きりぎりす鳴きてとどまる千草原いつまで露の身を宿すらむ(921詠)
組香の解釈は、香席の景色を見渡すための一助に過ぎません。
最も尊重されるものは、皆さん自身が自由に思い浮かべる「心の風景」です。
![]()
Copyright, kazz921 All Right Reserved
無断模写・転写を禁じます。
