�w�Í��a�̏W�x�������Ɍf�ڂ��ꂽ�̐l�����`�[�t�ɂ����g���ł��B
�O�i�ƌ�i�ŗv�f���̗p�r�̕ς��Ƃ��낪�����ł��B
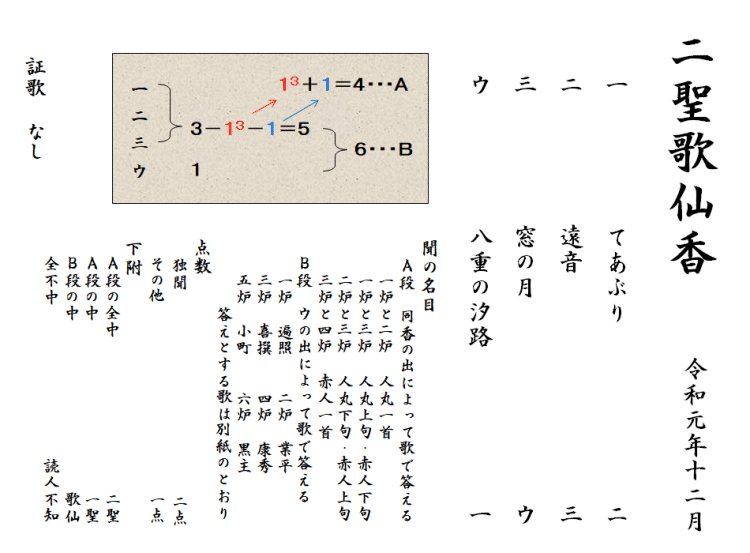
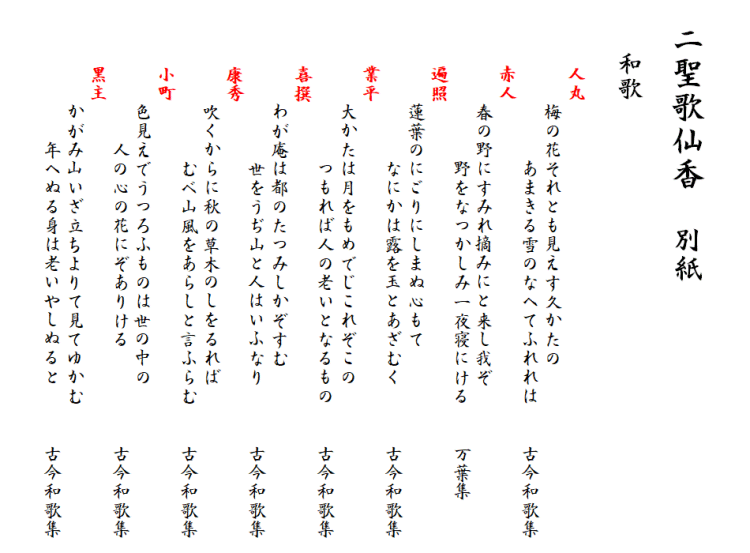
�����̃R�����ł̓t�H���g���Ȃ����߁u![]() �v���u*���v�ƕ\�L���Ă��܂��B
�v���u*���v�ƕ\�L���Ă��܂��B
|
|
���� |
|
���́A�S���p�ӂ��܂��B
�v�f���́A�u��v�u��v�u�O�v�Ɓu�E�v�ł��B
�����Ɩ؏��́A�i�F�̂��߂ɏ����܂����̂ŁA�G�߂�g���̎�|�Ɉ����̂����R�ɑg��ł��������B
�u��v�u��v�u�O�v�͊e�R���A�u�E�v�͂P�����܂��B(�v�P�R��)
�u��v�u��v�u�O�v�e�R��̂����A�P������������܂��B�i�|�P³���R��j
�c�����u��v�u��v�u�O�v���e�Q���ł������ĔC�ӂɂP����������܂��B�i�Q�~�R�|�P���T��j
�����������u��v�u��v�u�O�v�e�P��ɁA�O���U.�������������P��������đł������܂��B�i�R�{�P���S��j
�{���`�i���A���̂S�����Q��Q�g�i�u�`�{�̍��v�A�u�R�ӂ̍��v�j�ɕ������S�F�����o���܂��B
�A�O�́A�S�F�̂����A�������o���F�������ʂ��A����́u�̂̋�v�ʼn��܂��B�i�ύ�q�j
�{���a�i�́A�U.�Ŏc�����u��v�u��v�u�O�v���T��Ɂu�E�v�P��������đł������A�U�F�����o���܂��B
�A�O�́A���܂܂ň�x�����������Ƃ̂Ȃ��u�E�v���o���F���ʂ��A����́u�́v�ʼn��܂��B�i�ύ�q�j
�_���́AA�i���Г�����ɂ͂O�D�T�_�A��������͊e1�_�i�v2�_�j�A�a�i�̓�����͂P�_�Ƃ��A�ƕ��i�ЂƂ肬���j�͂��ꂼ��Q�_�Ɖ��Z���܂��B
�����́AA�i���Г�����ɂ́u�ꐹ�v�A��������́u�v�A�a�i�̓�����ɂ́u�̐�v�Ə��������܂��B
�����́A�ō����_�҂̂����A��Ȃ̕��̏����ƂȂ�܂��B
�@
�~�͂�̊X�H���ɖ���ԍ炭�G�߂ƂȂ�܂����B
�ߘa���N�̕������������Ă܂���܂����B�F�l�ɂƂ��āu�V�������v�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ƂȂ����ł��傤���H
���Ƃ������܂��ẮA�U���Ɂu�����̑g���v���Q�T�O�g�ڂ��}�������߁A�u�����ŏ���ɒ������Ǝv���Ă�����{�L�^�X�V��̈ꗢ�˂�u�����v�ƌ��߁A9���Ɂw�g���S�i(�~2.5)�x�������[�X�������܂����B���̌�A�u�c��]���͗��߂��u���������̓ǂ݉����ɐ�O���邩�H�v�Ƃ����I����������A�u�����̑g���v�̓L���̗ǂ��N��(�Q�T�U�g)�őł��~�߂ɂ��悤���Ɛ^���ɔY���̂ł��B������ڂ��̐������s���ł��邱�Ƃɂ��ẮA���łɐD�荞�ݍς݂ł����A���K��邩������Ȃ��V�X������������ттĂ���A�u�Ȃ�ׂ����C�Ŏ�̋Ă�����ɐ����ׂ����Ƃ͐��������B�v�Ƃ����C�����ɋ���Ă��܂����B
����Ȑ܂��܁A�C���^�[�l�b�g�̐��E�Ƀf�r���[�𐋂����u�������v�Ƃ����T�C�g�ɏo��A�����̖|�������X�� �s�����J����Ă��邱�ƂɋC�Â��܂����B����A�^�c�҂͔��R�Ƃ��Ȃ����̂́u����搶�̍���������v�u�����ɐe���މ�v�u�r���[�e�B�[�T�C�G���X�w��v�Ȃǂ̉��������c�̖�������A�u�A�Ɏɍ�����������v���ԈႢ�Ȃ��A���Ɠ����ӎ��������������̎u�m�̏W�܂�ł��邱�Ƃ��킩��܂����B���ɂ́A�������łɖ|�����Ă�����̂���������܂������A��������̂͂��A���̑����͐��앶�q�搶�ɃR�s�[�����������������Ɋ�Â����̂���������ł��B
���̂��ƂŁA�u�S�O�O�N���̍������𖢗��ɂȂ��v�Ƃ��������̌��ׂ̉���C�Ɍy���Ȃ�܂����B���Ƃ�葽��(����)�ɖ���(���)�ł����A�P�̖ڂ�葽���̖ڂŌ������� �|���̊m�x�������Ǝv���܂��B�܂��A���݂��Ɏ�ԉɂ����ďd��������̂������������̂ŁA�����|���̃��C�����[�g�͂�����ɂ����肷�邱�ƂƂ��܂����B
���̂悤�Ȃ킯�ŁA�u�����̑g���v�͂��܂܂łǂ���A�ڂ𑱂��邱�ƂƂ��āA�����̖|���͊������ӎ������ɐi�߂邱�Ƃɂ��܂����B�������A���ꂩ��͗ǂ��O����ł��܂������Ƃ���A�����|���ł������̂�����J���čs�����Ǝv���Ă��܂��B���N�́u�����ژ^�v�̃O���[�h�A�b�v�Ɍ�����҂ł��B
�����́A��܂Ƃ����̉̉r�ݏ���u�̐十�v�i�ɂ����������j�����Љ�����܂��傤�B
�u�̐十�v�́A�Đ여�w���̋k�i���j�x�Ɍf�ڂ̂���g���ł��B���̑g���͗p�����Ă���a�̂̌i�F���l�G�ɒʂ��Ă���A����̋G�ߊ��Ȃ��Ís�ł��܂��u�G�g�v�ƕ��ނ��ėǂ��ł��傤�B�u�̐�v�Ƃ����A�����Q�P�N�T�����u�Z�̐十�v�Ƃ����u���̉A�z�v��p�����������g�������Љ�Ă��܂����A������̑g�����Ȃ��Ȃ�����������ɕx��ł���A����ɂ����������₩�ȍ��L�̌i�F���Ր��ɐG��܂����B����͑��ɗޗ���Ȃ������w���̋k�x���o�T�Ƃ��āA�F����́u�Ε�̕����[�߁v�ɂӂ��킵���u�̉r�݂̍��v�����Љ�邱�ƂƂ������� ���傤�B
�܂��A���̑g���ɏ؉̂͂���܂���̂ŁA��|�𗝉����邽�߂��荆�ɉ��������������Ǝv���܂��B�u�v�Ƃ́A��l�̐��l�Ƃ����Ӗ��ŁA�Â��́A�I���O�̒����u���v�́u�����ƕ����v��u�����ƍE�q�v����[���Ă��܂����A�����ł����u�v�Ƃ��u��l�̉̐��v�Ƃ����Ӗ����u�`�{�l���C�v�Ɓu�R���Ԑl�v���w���Ă��܂��B��l�́w�Í��W�a�̏W�x�������̒����u�����̂��Ƃ̐l�܂�Ȃ������̂Ђ����Ȃ肯��B�i�����j�܂��A�R�̂ւ̂����l�Ƃ��Ӑl���肯��B�����ɂ��₵�����ւȂ肯��B�l�܂�͂����l�����݂ɂ��T�ނ��Ƃ������A�����l�͂ЂƂ܂낪�����ɂ��T�ނ��Ƃ������Ȃނ��肯��B�v�ƋI�єV�ɕ]����u�̂� ���v�Ƃ���܂����B���̌�l���C�́A���̉摜���Ղ��ĉ̓��̐��i���F�O����u�l���C�e��(�ЂƂ܂낦����)�v�Ƃ����V���̕��y�ɂ���āA��̂̐�����碉̂̐_��ւƏ��i���Ă����܂��B
����A�u�̐�v�Ƃ́A�D�ꂽ�̐l�̂��ƂŁA�������w�Í��a�̏W�x�̉��������u�m���Տ��v�u���ƕ��v�u�����N�G�v�u���@�t�v�u���쏬���v�u�唺����v�̂U���̉̐l�� �����A�̕����]���Ă����u�Z�̐�v�ƌ�����悤�ɂȂ�܂����B���̌���A�������C�́w�O�\�Z�l��x�Ɍf�ڂ���Ă��镽������̘a�̖̂��l�R�U�l���u�O�\�Z�̐�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ�A �u���ÎO�\�Z�̐�v��u���[�O�\�Z�̐�v�ȂǁA�ߐ��Ɏ��܂ŗl�X�ȁu�̐�v���I��Ă��܂����A�����ł����u�̐�v�Ƃ́u�Z�̐�v�̂U�����w���Ă��܂��B���̂悤�ɁA���̑g���́A�`�{�l���C�ƎR���Ԑl���u�v�Ƒm���Տ��A���ƕ��A�����N�G�A���@�t�A���쏬���A�唺������u�Z�̐�v�̌v�W���̉r�a�̂��i�F�ɎU��߂āA�������Ă��s������ƂȂ��Ă��܂��B
���ɁA�o�T�̍��g�̒i�ɂ��u�����\*�����̔@���v�Ƃ� �邾���ŗv�f�������������L����Ă��܂��A�{���̋L�q����A�\���͑S���قȂ�ɂ��ւ�炸�A�u��i�R��j�v�u��i�R��j�v�u�O�i�R��j�v�u�E�i�P��j�v�őg��ł��邱�Ƃ�������܂��B�v�f��������������Ă���̂́A�� �ɓ��������߂̑f�ނƂ��Ĉ����Ă��邽�߂ł���A���ꂪ�a�̂̌i�F�ɏ������Ă������ƂɂȂ�܂��B�������A�u��v�u��v�u�O�v�ɂ��ẮA�i�g�̑O��Ŏg�������قȂ�A�`�i�ł͕������Ă̂��߂̑f���Ƃ��ėp�����܂����A�a�i�ł́u�E�v�����Đh�����邽�߂̑f���ւƕω����܂��B���̂悤�ɁA�g���̑O��ŗv�f�̗p�r ���قȂ�Ƃ���́A���̑g���̍ő�̓����ƌ����܂��傤�B
���āA���̑g�����u�����\*�����̔@���v�ŁA����͂S��A�S�̍����E�{�����Ƃ��ɂP�O���ƂȂ��Ă��܂����A�����\���͎����ĕ��G�ł��B����ɂ��ďo�T�ɂ��u�{����A��A�O�A���O����u���A��̈�A��A�O�A�Z���ł����������āA�n�ߏ�������O������A�c��ܕ�փE���������A�Z��ł������A���̕��ɒu���A���߂̎l���ł������A����i�ɕ����ĕ����o���B������w�`�{�x�w�R�Ӂx�̓̍��Ƃ��ӂȂ�B�i�����j��̘Z*���́A�E�����F�Ƃ����ւw�@�t�x�̉̂�F�߂�c�i�����j�v�Ƃ���A���������Ă��A�����ɂ͗������������Ȃ��Ǝv���܂����̂ŁA�ӏ������ɂ��܂��B
�@ �u��v�u��v�u�O�v�͊e�R��A�u�E�v�͂P����܂��B
���g�ɂ��ẮA�o�T���u���̍���L�^�Ȃ����������͋����Ȃ��B�g�����l���A������Ђ��鍁�g�ނׂ��v�Ƃ���܂��̂ŁA�o���҂́A�����悤�ȍ��C��������I�����Ƃ��̐S�ł��B
�A �u��v�u��v�u�O�v�e�R��̂����A�P�����������܂��B�i�|�P³���R��j
�B �c�����u��v�u��v�u�O�v�e�Q���ł������ĔC�ӂɂP���������܂��B�i�Q�~�R�|�P���T�j
�C �����������u��v�u��v�u�O�v�e�P��ɇA�ň����������P��������đł������܂��B
����ɂ��A�{���`�i�ɂ́A�K���ǂꂩ�P�킪�Q�o��悤�ɂȂ��Ă��܂��B�i�R�{�P���S�j
�������āA�{���`�i�͂S�����Q��u�`�{�̍��v�A�u�R�ӂ̍��v�̂Q�g�ɕ����ĂS�F�����o���܂��B�����́A�o���̍��u�`�{�̂P�F�v�u�`�{�̂Q�F�v�A�u�R�ӂ̂P�F�v�u�R�ӂ̂Q�F�v�Ɛ錾���ĉƗǂ��ł��傤�B
�{���`�i�������o����܂�����A�A�O�͂ǂ̗v�f��������Ă��邩�͂킩��܂���̂ŁA�S�̍��̂��� �u�����v���o���F�������ʂ��܂��B�����́A�o�T���u���F�Ɠ�F�����ƕ����ΐl�ۂ̉̈���F��Ȃ�B���F�ƎO�F�����ƚk�ΐl�ۂ̏�̋�A�Ԑl�̏�̋��F�ߏo���B���A��F�ƎO�F�����ƕ����ΐl�ۂ̉��̋�A�Ԑl�̏�̋�Ə��ɔF�߂ďo���ׂ��v�Ƃ���A�{���`�i�́u�`�{�̂P�F�v�i���F�j�͐l���C�̏�̋�A�u�`�{�̂Q�F�v�i�Q�F�j�͉��̋�A�u�R�ӂ̂P�F�v�i�R�F�j�͐Ԑl�̏�̋�A�u�R�ӂ̂Q�F�v�i�S�F�j�͉��̋�ƑΉ����������Ƃ������Ă���܂��B�Ȃ��A�o�T�ɂ��u�O�F�Ǝl�F���� �E�E�E�v�ɂ��ċL�ڂ�����܂��A���ꂩ��@�����u�Ԑl�̉̈��v���L�����ׂ����Ǝv���܂��B
�����āA�{���a�i�́A�B�Ŏc�����u��v�u��v�u�O�v�̂T��Ɂu�E�v�������đł������ĂU�F�����o���܂��B
�A�O�́A������ǂ̍���������Ă��邩�͂킩��܂��A �{���`�i�ŏ��Ȃ��Ƃ��u��v�u��v�u�O�v�͈�x�����Ă��邽�߁A�u��x�����������Ƃ̂Ȃ�����v�ˁu�E�v�̏o���F���ʂ��܂��B�����ŕ����o�����u��v�u��v�u�O�v�́A�u�E�v���f�킹�邽�߂Ɏז�����u�������v�́u�w���v�̂悤�Ȗ�ڂ��Ă��܂��B
�������āA�{���a�i�̓����́A�u�E�v���P�F�ڂɏo���Ǝv���u�@�t�́c�i�ՏƁj�v�A�Q�F�ڂɏo��u�傩���́c�i�ƕ��j�v�A�R�F�ځu�䂪���ق́c�i���j�v�A�S�F�ځu��������Ɂc�i�N�G�j�v�A�T�F�ځu�F�����Łc�i�����j�v�A�U�F�ځu�����ݎR�c�i����j�v�̉̂������L���ĉ������Ƃ��L�ڂ���Ă���A�����ŏ��߂ďo�T���u�����Z�̐�Ƃ��Ӂv�Ə�������ł��܂��B
�A�O�̓����Ɏg�p�����a�͉̂��L�̒ʂ�A�w�Í��a�̏W�x�̉������Ɉ��p���ꂽ�a��������Ă��܂��B
�l���i�o�T�܂܁ːl���C�j
�~�̉Ԃ���Ƃ��������v���̂��܂����̂ȂւĂӂ��́i�Í��a�̏W334�j
�u�~�̉ԁA�ǂꂪ���ꂾ�������������Ȃ��A�i�v���́j�V��𔒂��܂点�āA�Ⴊ��ʂɍ~���Ă���̂ŁB�v
�w�Í��a�̏W�x�{���ɂ́u���̉̂́A����l�̂��͂��A�`�{�l�܂납�̂Ȃ� ��ݐl���炷�v�Ƃ̍���������܂����A�������ł́A�u�ЂƂ܂�v�̉̂Ƃ���Ă��܂��B���݂Ɂu���܂���v�́A�u�V����v�Ə����_�▶�Ȃǂ̂��߂ɋ܂邱�Ƃ������܂��B
�Ԑl
�t�̖�ɂ��݂�E�݂ɂƗ����䂼����Ȃ����݈��Q�ɂ���i���t�W8-1424�j
�u�t�̖��係�E�݂ɂ���ė������́A���̖�ɐS������A�Ƃ��Ƃ������߂����Ă��܂�����B�v
�Տ�
�͂����t�̂ɂ���ɂ��܂ʐS���ĂȂɂ��͘I���ʂƂ����ނ��i�Í��a�̏W165�j
�u�@�́A�������D���ɂ����Ă����܂�ʁi�����j�S���Ȃ��āA�Ȃ��I���ʂƋ\���Č�����̂��B�v
�ƕ�
���ق����͌������߂ł����ꂼ���̂���ΐl�̘V���ƂȂ���́i�Í��a�̏W879�j
�u�����܂��Ɍ����A���������ł�C�����Ȃ��A����͂܂�A���̌��Ƃ������̂������A�ς���ς����Đl�̘V���ɂȂ�����̂Ȃ̂�����B�v
���
�킪���͓s�̂��݂��������ސ��������R�Ɛl�͂��ӂȂ�i�Í��a�̏W983�j
�u���̈��͓s�̓���Ɂi�������ꂽ�R�̒���)���̂悤�ɏZ��ł���B���̐l�X�́i���̎R������������J���ē������j�w�F���R�x�i�J���R�j�ƌĂ�ł���B�v
�N�G
��������ɏH�̑��̂������ނR�������炵�ƌ��ӂ�ށi�Í��a�̏W249�j
�u���ꂪ���������܂��H�̑����ނ�Ă��܂��̂ŁA�Ȃ�قǎR���琁�����낷�����w���炵�x�ƌ����̂��낤�B�v
����
�F�����ł���ӂ��̂͐��̒��̐l�̐S�̉Ԃɂ����肯��i�Í��a�̏W797�j
�u�i���ʂ̉ԂȂ�ΐF�͖ڂɌ����ĕω�������̂Ȃ̂Ɂj�F�ɂ͂�����Ƃ͌������ɂ��낤���̂́A���̒��̐l�̐S�ɍ炭�Ԃ������̂ł��ˁv
����
���R�����������Č��Ă䂩�ޔN�ւʂ�g�͘V���₵�ʂ�Ɓi�Í��a�̏W899�j
�u�����i���̖��̒ʂ苾�ɉf���Ƃ����j���R�ɗ�������Č��čs�����B�N���d�˂��䂪�g�͘V�������낤���ƁB�v
�w�Í��a�̏W�x�{���ɂ́u���̉̂́A����l�̞H���A�唺���傪��B�v�Ƃ̍���������܂����A�������ł́A�u����ʂ��v�̉̂Ƃ���Ă��܂��B
�{���������I���܂�����A�A�O�́A���掆�ɓ����������i�ƂȂ�܂����A�����Ȗ��掆�ɘa�̂Q��S�������̂���ςł����A���M�����Â炢��������܂���̂ŁA�`�i�ł́A�����ƂȂ��̏�̋�i�T�����j�Ɖ��̋�i�V�����j�A�a�i�ł́A�����ƂȂ�a�̂̑���i�T�����j�݂̂������L���֖@���K�v��������܂���B�����͓����̃��[���ł����߂��������B
�A�O�������������L���A���掆���߂��ĎQ��܂�����A���M�͂�����J�������L�ɑS�����̓����������L���܂��B ������͏ȗ��������Ȃ��̂ŁA��ςȍ�ƂƂȂ�܂��B�������ɂ��ẮA�o�T���u�̐十�V�L�v�̋L�ڗ�ɂ��A�`�i�̓����͖���̉��A���L�̏㔼���ɂQ�s�ɏ����A�a�i�̓����́A��̋���R��͂R�s�A���̋�Q��͓K���ɂR�s�ɕ����āA���̉��̒i�ɏ����L����Ă��܂��B
���M���A������S�Ďʂ��I���܂�����A�����ɐ����𐿂��܂��B�������A������č�����J����������錾���܂��B���M�͂�����āA���̏o�̗��ɗv�f�������̂܂����L���܂��B���̍ہA�`�i�̍��̏o���A�u�`�{�̍��v�Ɓu�R�ӂ̍��v���Q�s�Q��ɏc���т��i����t�����������L���܂��B����A�a�i �̍��̏o�́A�R�s�Q��ɏc���т��i����t���������L���܂��B��������ł��̂Ő}�����܂��B
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| �@ | �@ | ���� �@ |
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �̐十�V�L |
| �@ | �@ ����Ȃ����݈��Q�ɂ��� |
�@ | �~�̉Ԃ���Ƃ��������v���� | �@ |
�O�B ���C |
���@ ���A |
||
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||
| �@ | �@ �@ ���̒��� |
�@ ����ӂ��̂� |
�F������ | �@ �@ �O�D |
�@ ���B �@ |
���@ | �@ |
�� �g |
| �@ | �@ | �@ �@ |
�@ | �@ | �@ | |||
| �@ | �@ �@ ���肯�� |
�@ �Ԃɂ� |
�l�̐S�� | �@ �@ �O�E |
�@ �E�C �@ |
���A | ||
| �@ | �@ | �@ | �@ |
���̏o�������I�����Ƃ���ŁA���M�͓��ۂ��ߓ���ɍ��_���|���܂��B����ɂ��ďo�T�ł��u�Z�̐�Ƃ��ɒ���͒��_��_���A�ƕ���_�Ȃ�B�ꐹ���蓖��͖T�_�ɂ�����Ȃ�B�v�Ƃ���A�`�i�͓������Ƃ��������ĂĂ���A�e�s�̑���ɒ��_���|���܂��i�Q�_�j�B�A�O�̒��ŗB��l�����Ă���Ίe�X�Q�_���|���܂��i�S�_�j�B�܂��A���������ĂĂ��Ȃ��Ƃ������L���ꂽ��̈�����������Ă���ΒZ���T�_���|���܂��i�O�D�T�_���Z�j�B����A�a�i�́A����������ɒ��_���|���A�ƕ��̏ꍇ�͂Q�_���|���܂��B��������ƁA�ō����_�́A�ƕ����S����̂U�_�ƂȂ�܂��B
���̑g���̉����́A�o�T���u�A�Z�̐�Ƃ�������Ή��֓A�Z�̐�Ə����Ȃ�B���蓖��͓Ə����A�̐哖��͉̐�Ə����B�ꐹ����͈ꐹ�Ə����B���͓ǐl���炸�Ə����Ȃ�B�v�Ƃ���A�e���̓��_�\���͂���܂���B�`�i�Œ��_���Q�{�|������u�v�A�T�_�P�{�Ȃ�u�ꐹ�v�A�a�i�̓�����́u�̐�v�Ɖ����������ƂƂ���Ă��܂��B����A�`�i�E�a�i�Ƃ��ɊO�ꂽ�ꍇ�́u�ǐl�s�m�v�Ɖ������܂��B�u�ꐹ�v�ɂ��ẮA������ ���Ă��炸�u���܂���E���ɏ�������̈�����������������v�̂悤�ȋC�����܂����A���̂悤�ȃ��b�L�[�|�C���g�����L�̌i�F�Ƃ������̂ł��傤�B
�Ō�������́A�ō����_�҂̂����A��Ȃ̕��̏����ƂȂ�܂��B�o�T�̍��L�ɂ͖T�_���Z���͋L�ڂ���Ă��炸�u�T�_�𐳓_�̔����ɂ���v�Ƃ����L����Ă͂��Ȃ��̂ł����A���������ł����u�ꐹ�v�Ɓu�̐�v�̝h�R���������ꍇ�A�S���������ĂĂ͂��Ȃ��u�ꐹ�v�ƃE�������Ă��u�̐�v���� ���P�_�Ƃ����̂͂��������̂ŁA�u�ꐹ�v�̖T�_�͒Z���|���A�_���͂O�D�T�_�Ɗ��Z���ׂ����Ǝv���܂��B
�Ȃ��A�o�T�{���̍Ō�ɂ��u���̍�����ɕ~���\*�����Ƃ��]���Ȃ�B�v�ƌ���ł���܂��B�u�~���v�Ƃ����{�̂����� �A�u�~�����v�Ƃ����g��������܂��B���̑g���́A�ȒP�Ɍ������u�a�̃x�[�X�̓������v�ŁA�Ⴆ�A�u�� �E���E�́E�܁E�v���T������v�f�ɍ���g�݁A���̏o�ɏ]���ē�������܋�Ƃ����̂��r��œ������Ƃ������̂ł��B���̑g���́A�㐼�@��i1638-1685�j���D��ōÍs���đ嗬�s�������̂́A�ǂ��̂��r�ނ��߂ɓ������킴�ƊԈႦ����A���ɐ������������߂ɒt�قȉ̂��r�肵�Ď���ɉ������A����̗쌳�@�@�c�i1654-1732�j���u�����E�̓��Ɋ��\�Ȃ�ł͂Ȃ��ׂ��łȂ��v�Ǝ~�߂������Ƃ�����b������܂��B���̑g�����u�~�����v�Ɩ��t�����̂́A��͂��u�l�̂��T������˂Ƃ��āA���Â̂��Ƃ̂͂Ƃ��Ȃ�肯��B�v�u��܂Ƃ����v�����Ƃ����g�������������ł��傤�B�������Ă݂�Ɓu�̐十�v�Ɂu�̉r�݂̏\*�����v�Ƃ����u�~���\*�����v�ƕʖ����t����ꂽ�̂����_���������������܂��B
�u�̐十�v�́A���L�����₩�Ŗʔ�������ɕx��ł��Ȃ���A�ӊO�ɕ����₷���g���ł��B�F�l���Z�̐�̉̍����ɎQ�Ȃ�������Ŋy����ł݂Ă͂������ł��傤���B
�@
�̂ł������u�o�������v�ŃR�����������Ă������̂ł���
�ŋ��͋x�������������u�������Ȃ��x���v��搉̂���������̂ł�����E�E�E
���N�́A�ӗ~���������āu���i�S�_�v���撣��܂��B
�����݂̊֘H�̐��[���炶�����ɉԍ炯�Â����̗t(�X�Q�P�r)
���N��1�N�����ǂ��肪�Ƃ��������܂����B
�ǂ����N�����}�����������B
�g���̉��߂́A���Ȃ̌i�F�����n�����߂̈ꏕ�ɉ߂��܂���B
�ł����d�������̂́A�F���g�����R�Ɏv�������ׂ�u�S�̕��i�v�ł��B
![]()
Copyright, kazz921 All Right Reserved
���f�͎ʁE�]�ʂ��ւ��܂��B