七月の組香
![]()

![]()
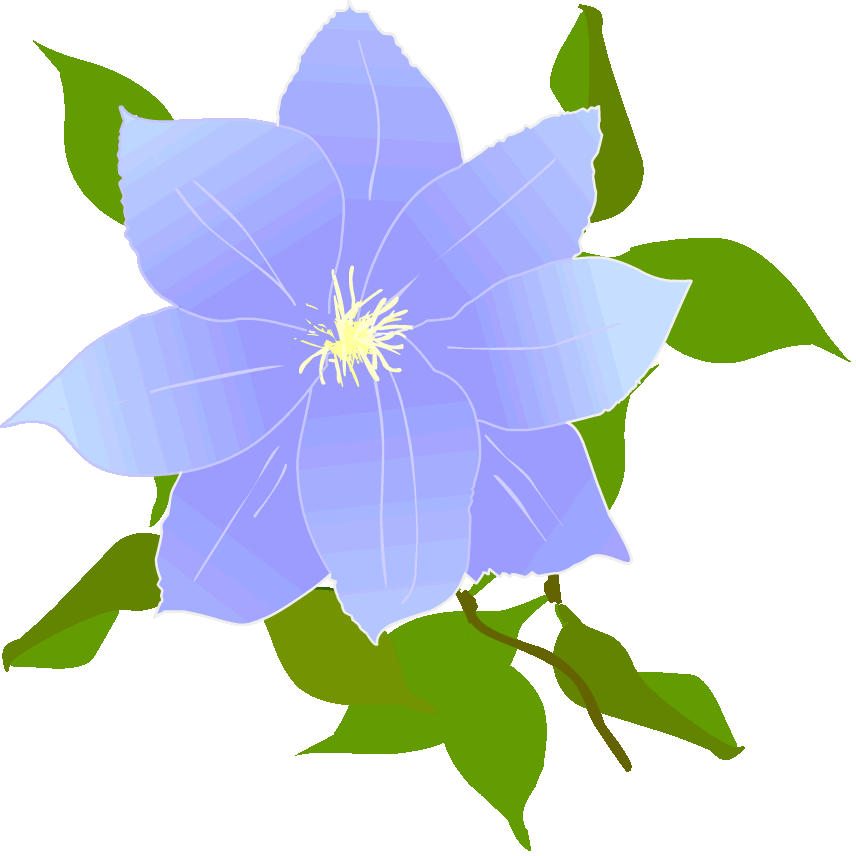
盛夏に氷室を思い涼む組香です。
氷に結び付けられた山人と宮人の景色を味わいましょう。
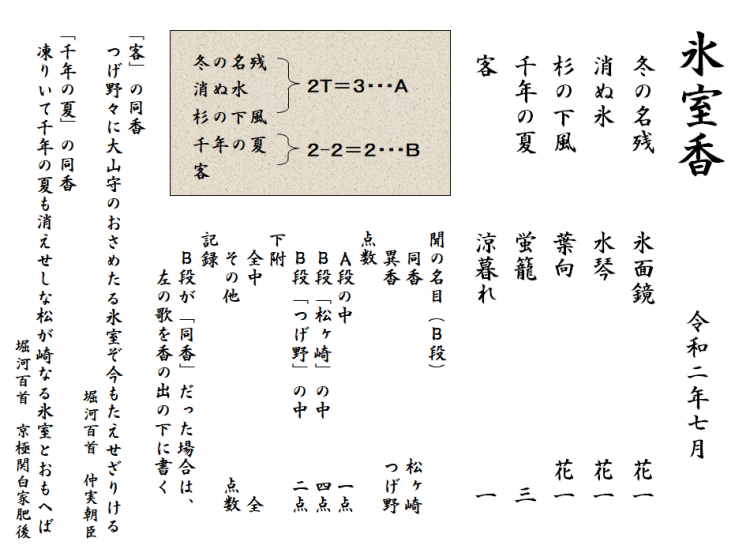
|
|
説明 |
|
-
香木は、5種用意します。
-
要素名は、「冬の名残(ふゆのなごり)」「消ぬ氷(きえぬこおり)」「杉の下風(すぎのしたかぜ)」「千年の夏(ちとせのなつ)」と「客」です。
-
香名と木所は、景色のために書きましたので、季節や組香の趣旨に因んだものを自由に組んでください。
-
「冬の名残」「消ぬ氷」「杉の下風」「千年の夏」「客」ともに2包ずつ作ります。(計10包)
-
まず、「冬の名残」「消ぬ氷」「杉の下風」の各1包を試香として焚き出します。(計 3包)
-
次に、「千年の夏」と「客」の各2包を打ち交ぜて、そこから任意に2包引き去ります。
-
引き去った2包は、「捨て香」として総包に戻、手元に残った2包は結び合わせておきます。
-
本香A段は、「冬の名残」「消ぬ氷」「杉の下風」の各1包を打ち交ぜて、3炉焚き出します。
-
連衆は試香と聞き合わせて、名乗紙にこれと思う要素名を出た順に3つ書き記します。
-
本香B段は、先ほど結んで置いた2包を焚き出します。
-
連衆は、2包とも同香が出たと思えば「松ヶ崎(まつがさき)」、異香が出たと思えば「つげ野(つげの)」と聞の名目を1つ書き記して答えます。
-
点数は、A段の当りは 各1点、B段「松ヶ崎」の当りは4点、「つげ野」の当りは2点とします。
-
下附は、全問正解には「全」、その他は点数を漢数字で書き附します。
-
B段の正解が「松ヶ崎(同香)」だった場合は、香の出の下に書き記します。(委細後述)
「客・客」の場合は「つげののに・・・」の歌、「千年の夏・千年の夏」の場合は「凍りゐて・・・」の歌
-
B段の正解が「つげ野(異香)」だった場合は、歌は書き記されません。
-
勝負は、最高得点者のうち上席の方の勝ちとなります。
縁側の涼風と氷菓が恋しい季節となりました。
近年の酷暑を反映してか、折からのスイーツブームが嵩じたものか、我が「夏のオアシス」だった「かき氷」が高級化して、かえって縁遠くなってきています。私の小学生の頃には、イチゴ、メロン、レモンが30円、練乳をかけると50円で、電話をすると店が出前もしてくれたものでした。現在、街角でたまに涼を求めて食べるだけの私にとっては、かき氷専門店の「千円〜3千円!?」といったメニューが、恐ろしく強気の値段設定に感じられます。
私が、初めて専門店のかき氷を食べたのは名古屋の大須でした。そのころ始まったばかり「天然かき氷」は、「いちご」「メロン」「マンゴー」「抹茶金時」という外連味の無いもので確か900円だったと思いますが、フルーツペーストや地元の抹茶など天然材料にこだわった「フワフワでツンとこない」もので、「なるほどな・・・」と唸る納得のお値打ちでした。
現代のかき氷店の多くは、厳選された材料を使ったオリジナルのシロップやトッピング、素材の奇抜な取り合わせ等で勝負していますが、もっとも基本的な売り物は「天然氷」です。天然氷は、山からの湧き水を水槽に溜めて、冬の間に自然の冷気で凍らせ、切り出した1枚の氷に複数「ふた氷」を乗せて積み重ね、杉のおがくず等で囲って「氷室(ひむろ)」に貯蔵します。自然の水と冷気を使った製氷は、一見「元値無し?」に見えますが、水槽の掃除から水、氷の管理・・・と意外に手間暇はかかるようです。そうしてできた氷は、1貫目(約4kg)で千円ぐらいですから、それほど楽な商売ではないのかもしれません。
天然氷がなぜ「フワフワでツンとこないのか?」は、ひとえに「ゆっくり凍らせる」ことにあるようです。そうすると水の中のミネラルや空気を追い出しながら固まるために不純物の少ない「0℃で固まり0℃で融ける氷」ができるというわけです。こうしてできた氷は、水の分子同士しっかり結びついた「硬い氷」になります。硬い氷は「細かく削る」ことができ、削った氷の中に「たくさんの空気を取り込める」ためにフワフワで口融けも良くなります。また、脳が痛いと感じるほど「冷たくない温度」で舌に触れ、すくに消えるため、ツンと来ないかき氷になるというわけです。もちろん、天然氷も保存や輸送をする際は-18度以下で温度管理しますが、使う時に「0度まで戻すことができる」というのがミソです。一方、冷蔵庫の氷は-18度で一気に凍らせるため不純物ごと凍ります。高校の化学で習ったように不純物が入っていれば凝固点も融解点も降下します。そのため、-10℃ぐらいで溶け始める氷からは「シャリシャリでツンとくる」かき氷しか作れないというわけです。
私の好みで云えば、「高級かき氷」は、最初に食べた「抹茶金時」のように天然の氷と素材をシンプルに組み合わせたかき氷までなら許せますが、昨今は「とろとろでふわふわ」が嵩じて、「涼味」とは無縁の奇想天外な「超高級かき氷」が増えて閉口してしまいます。これもかき氷が通年営業できる食べ物になったからなのかもしれません。かき氷は冷たくてすぐ溶けますが、「決してカロリーはゼロではない」ということを忘れてはいけませんね。諺に「年寄りの冷や水」というのがありますが、私はせめて、波に千鳥の「氷」の幟の出た喫茶店のかき氷を「アイスクリーム頭痛」の出ない程度に溶かしてからチュルチュル楽しみたいと思います。
今月は、鄙からの涼しい貢物「氷室香」(ひむろこう)をご紹介いたしましょう。
「氷室香」は、『外組八十七組(第二)』に掲載のある「夏」の組香です。同名異組の「氷室香」は米川流香道『奥の橘(月)』にも掲載があり、こちらは、要素名が「霰」「雪」「氷」の三種組で、本香の出によって「山下風」や「氷の貢」などの聞の名目で答えるようになっています。建部隆勝の『香道秘伝書』には「夏は、香は聞かれぬなり」とあり、熱い香炉を持ち、部屋を閉め切って風を入れない環境での聞香は、「納涼」とは対極の苦行だったのかもしれません。一方、現代では、冷房の効いた部屋での聞香が可能ですから、「納涼香」を含め、涼しさを誘う景色で香を楽しむ「夏の組香」は貴重とも言えます。そこで、志野・米川系の流派では夏の定番として催されている「氷室香」を流派問わず楽しんでいただくためにご紹介することといたしました。今回は、表す景色が深淵で美しい『外組八十七組』を出典として書き進めたいと思います。
まず、題号にある「氷室」とは、涼しい山かげに深い穴を掘ったり、天然の洞窟を利用したりして、その中に冬に降り積もった雪や天然の氷を入れて、枯れ草や杉皮などの保温材で覆い、天然の氷を夏まで保存する貯蔵庫のことです。氷室は、古代から昭和の初め頃まで、山村のあたりまえの生活文化として伝わっていました。これが、宮中文化と結びついたのは、なんと西暦374年のことでした。
『日本書紀』の「仁徳六十二年夏五月」に次のような逸話が掲載されています。
|
「闘鶏野氷室事」 額田大中彦皇子(ぬかたのおおなかつひこ)が闘鶏(つげ)で猟をされた。山上から野中を望み見ると庵のようなものがあり、使いの者にこれを見せた。使者が帰ってきて「窟(つちくれ)ですと云ったので、国造の闘鶏稲置大山主(つげいなぎおおやまぬし)を呼んで「野中にある窟はなにか?」と問うと、「氷室です」と答えた。「皇子が何を蓄え、どのように使うのか?」と問うと、「地面を1丈掘ってその上を草で覆い、穴には茅荻を敷いて氷を取り置いておく。氷は夏の月を経ても溶けず。熱い月に水酒をひたして用いる」と答えた。皇子はその氷を持ち帰り宮中に献上したところ天皇の歓ぶところとなり、これ以後、毎年、冬に氷を蓄えて夏分から用いるようになった。」 |
これが、「氷室」に関する日本初の記録ということであり、現在、奈良県天理市福住町にある「都祁(つげ)氷室神社」の周辺であろうと言われています。
因みに、『日本書紀』に書かれた「闘鶏」を「つげ」と読むのは、大阪府高槻市氷室町の「闘鶏野神社」が鶏鳴が神託を「告げる」ことに由来すると説明しています。
その後、各地の氷室は朝廷で管理することが定められ、氷室の番人である「氷室守」や氷を宮中へ運ぶ役職のことなどが律令で定められていました。『延喜式(えんぎしき)』の「主水司の項」には「およそ供御の氷は、四月一日に始めて九月三十日に尽きよ。」とあり、毎年4月から9月までは氷室の氷を宮中に運ぶ重要な務めがあったことなどが記されています。当時、朝廷が管理した氷室は、山城国の栗栖野をはじめ、小野、長坂、賢木原、松ヶ崎、大和国では都祁、近江国では竜花、丹波では氷室山などにあったとされていますが、この組香には、そのうち「松ヶ崎」と「都祁野(闘鶏野)」2か所の氷室が採用されています。
続いて、出典の本文には、厳密に証歌とは言えないものの、二つの和歌が掲載されています。
「つげののにおふ山守のおさめたる氷室ぞ今もたえせざりけり (堀河百首519 仲実朝臣)」
意味は「闘鶏の野で大山守(闘鶏稲置大山主)が治めていた氷室は今も絶えることなくあることだなぁ」というところでしょう。詠み人の藤原仲実(なかざね)は、天喜5年〜永久6年(1057〜1118)、堀河院歌壇の中心メンバーの一人で、『金葉集』をはじめ勅撰集に23首入集しています。
ここで、原典では「けり」が「ける」となっていますので小記録を修正していますが、流派の方は「伝書優先」で結構です。
「凍りゐてちとせの夏も消えせしなまつが崎なる氷室とおもへば (堀河百首526 京極関白家肥後)」
こちらは「氷があるので、ここを松ヶ崎の氷室だと思えば、千年の夏も消え失せてしまったことだなぁ」ということでしょう。詠み人の肥後(ひご)は肥後守藤原定成の娘で生没不詳。院政時代の代表的女流歌人の一人で、『金葉集』をはじめ勅撰集に53首入集しています。
このように、この組香では、二か所の氷室が景色として採用されています。出典に仮名書で「津希野」と表記してある氷室は、前述した氷室発祥の地で大和国の歌枕でもある「闘鶏野」と解してよろしいかと思います。また、「松ヶ崎」は、京都市左京区松ヶ崎にあった山城国の歌枕「松ヶ崎氷室」のことです。『源氏物語』の「夕霧」では紅葉の名所としても登場しますし、現在では、五山の送り火「妙・法」が灯る辺りというとお分かりいただけるかもしれません。
ここで、元祖である「闘鶏野」はゆるぎないものとして、数ある宮中御用の氷室の中から最も上質な氷を産出したという「栗栖野」や謡曲「氷室」の舞台となった「氷室山」などを退けて、「松ヶ崎」が選ばれたのは疑問に思えまず。これは、ひとえに「堀河百首」(513〜528)に詠み込まれた氷室は、長坂、闘鶏野、氷室山、松ヶ崎の4か所であり、そのうち「松ヶ崎」が2首詠まれていたため作者の目に留まり易かったのかもしれませんね。
次に、この組香の要素名は、「冬の名残」「消ぬ氷」「杉の下風」「千年の夏」と「客」となっています。同名異組の「氷室香」の要素名である「霰」「雪」「氷」と比べると少し観念的で、「氷」そのものであったり、山里の「氷室」の景色であったり、宮内でそれを感じる「宮人の心象」であったりと1つ1つに解釈の幅がある美しい言葉が採用されていると思いますので、皆様の心の赴くままに味わっていただければと思います。「客」は、最終的には「つげののに・・・」の歌に帰結する要素でもありますので、「千年の夏」同様に「大山守」とでもすれば良かったのではと思いますが、作者は、香の出にバリエーションを付けるということ以外に最も観念的な要素を残して、連衆の結ぶ景色に幅を持たせたかったのかもしれません。
さて、この組香の香種は5種、全体香数は10香、本香数は5炉となっています。構造は、回答方法が異なる段組み構成をとっているところが特徴となっています。まず、「冬の名残」「消ぬ氷」「杉の下風」「千年の夏」「客」ともに2包ずつ作り、そのうち「冬の名残」「消ぬ氷」「杉の下風」の各1包を試香として焚き出します。次に、客香である「千年の夏」と「客」の各2包を打ち交ぜて、そこから任意に2包引き去ります。引き去ったものは「捨て香」として総包に戻します。手元に残った2包は結び合わせて点前座に仮置きしておきます。
本香A段は、「冬の名残」「消ぬ氷」「杉の下風」の各1包を打ち交ぜて、3炉焚き出します。本香A段が焚き出されましたら、連衆は試香と聞き合わせて、これと思う要素名を名乗紙に3つ出た順に書き記します。続いて、本香B段は先ほど結んで置いた客香の2包を焚き出します。本香B段は、同香が2包出たと思えば「松ヶ崎」、異香が組み合わされて出たと思えば「つげ野」と聞きの名目を1つ書き記して答えます。
そうして、本香が焚き終わり、名乗紙が返って参りましたら、執筆はこれを開き、各自の答えを香記の解答欄に縦一列で書き写します。答えを写し終えましたら、香元に正解を請います。香元は、これを受けて香包を開き、正解を宣言します。執筆はこれを聞いて香の出の欄に要素名を書き記します。
ここで、出典の「氷室香之記」の記載例では、要素名を「一」「二」「三」「ウ」「客」と数記号の1文字で示し、各自の答えは要素名で書き記されていますが、本文のどこにも「一 冬の名残」「二 消ぬ氷」「三 杉の下風」「ウ 千年の夏」「客」と読み替えについて記載されていませんので、ここでは、雅趣を優先するためにどちらも要素名で記載することとしました。要素名を書く際は、後で下半分に和歌を書く可能性もありますので、「千鳥書き」をお勧めします。なお、現在の志野流では、聞書に「一(冬の名残)」「二(消ぬ氷)」「三(杉の下風)」「ウ(千年の夏)」「客(客)」と表記され、「一」「二」「三」「ウ」「客」を記録に用いることもあるようです。
香の出を書き終えましたら、各自の答えを横に見て当たりの要素名に合点を打ちます。点法について、出典には「記録様、左の図を見合わせ考うべし。尤も終りの二*柱同香にてウ・ウと出でたれば聞き当たりは二点づつなり」とあり、平点についての記述はありません。そこで「氷室香之記」の記載例を見ますと、A段の3炉については、要素の当たりにつき1点が掛けられ、B段の当たりについては香の出に「ウ・ウ」の同香が出て、名目を塗りつぶすように縦線が4点が掛けられています。一方、「ウ・客」の異香については、記載例に無いため推測となるのですが、敢えて「同香の場合の当たりは4点」と特筆しているのですから、各要素1点と換算して名目の当たりにつき2点を掛けるのが順当かと思います。そのようにしますと、A段は要素名の当たりにつき1点、B段の異香「つげ野」は2点、B段の同香「松ヶ崎」は4点の得点となり、全問正解は7点となります。おそらく、「松ヶ崎」の当たりに加点要素があるのは、次の和歌に通じる趣向となるため、殊勲を認めているのだと思います。
この組香の下附は、全問正解は「全」その他は、合点の数だけ漢数字で書き附します。
続いて、出典には「又、『客・々』と出る時は、出香の下に『つげののに』の歌を一首書くべし」(つげののにの歌)「又、二*柱同香にて『千年の夏・々々』と出たるは『松ヶ崎』の歌を書くべし」(松ヶ崎の歌)「別香の時は、書くに及ばずなり」とあり、B段の香の出が「松ヶ崎」だった場合、それを構成した要素が「客」の同香だった場合は、証歌の段でご紹介した「つげのの」の歌、「千年の夏」の同香だった場合は「凍りゐて」の歌を香の出の欄の下半分に一首、二行に分けて書き記すこととされています。一方、B段が異香で「つげ野」となった場合には「書くに及ばず」ですので、この歌が香記に現れることはありません。そのため、厳密には証歌とは言えず、「香記の景色を彩る脚色」ということになろうかと思います。前述したとおり「客」の要素名が「大山守」だと仮定すれば、「大山守」の上下の句が揃って「つげののに」、「千年の夏」は同じく「凍りゐて」、異香の組合せは、上下が揃わないので歌にならずと解釈できます。おそらくは、作者にもこの意識があったのではないでしょうか。
最後に勝負は、最高得点者のうち上席の方の勝ちとなります。B段に同香が出れば一気に4点のチャンスがありますから大事にしたいですね。
『香道秘伝書』には、「香炉が熱い時は、半分水につけて冷やす」などというノウハウも書かれています。火合いは炭団から上のことなので影響はないのでしょうかね。皆様も涼しい部屋で涼しげな景色の「氷室香」と「冷茶点」で酷暑を乗り切っていただければと思います。
なお、今月の「香書目録」は、大枝流芳編の『改正香道秘傅書 附録奥の栞』の『奥の栞』を公開いたしました。そちらもお楽しみください。
『枕草子』の「あてなるもの(39条)」に・・・
「削り氷にあまづら入れて、新しき金まりに入れたる」とあります。
これは、最高級の天然かき氷「しぐれ」ですね。
槇の香に冬の名残もあるぞかし氷室の風やなおぞ涼しき(921詠)
組香の解釈は、香席の景色を見渡すための一助に過ぎません。
最も尊重されるものは、皆さん自身が自由に思い浮かべる「心の風景」です。
![]()
Copyright, kazz921 All Right Reserved
無断模写・転写を禁じます。
