折々の組香

![]()
![]()
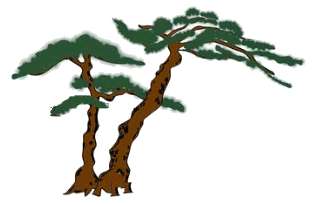
四国八十八ヵ所の遍路旅をテーマにした新作組香です。
「同行二人」で 霊場を巡礼する景色が特徴です。
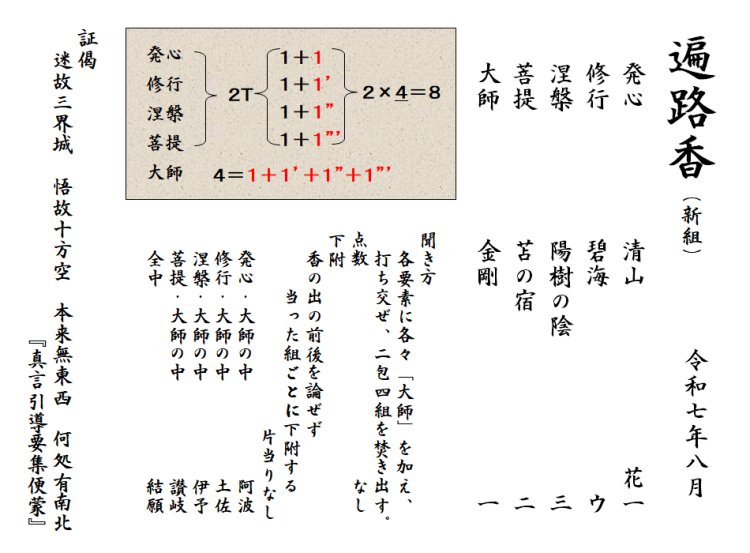
|
|
説明 |
|
-
香木は、5種用意します。
-
要素名は、「発心(ほっしん)」「修行(しゅぎょう)」「菩提(ぼだい)」「涅槃(ねはん)」と「大師(だいし)」です。
-
香名と木所は、景色のために書きましたので、季節や組香の趣旨に因んだものを自由に組んでください。
-
「発心」「修行」「菩提」「涅槃」は各2包、「大師」は4包作ります。(計12包)
-
「発心」「修行」「菩提」「涅槃」のうち各1包を試香として焚き出します。
-
残った「発心」「修行」「菩提」「涅槃」の各1包に「大師」を1包ずつ加えて結び置きします。(2×4=8包)
「発心+大師」「修行+大師」「菩提+大師」「涅槃+大師」
-
本香は、2包ずつ4組で都合8炉廻ります。
-
連衆は、試香に聞き合せて、名乗紙にこれと思う要素名を組ごとに区切って 8つ書き記します。
-
正解が宣言されたら、執筆は当った要素に合点を掛けます。
-
下附は、香の出の前後に関わりなく、2つとも当った組ごとに書き附します。
-
全問正解は「結願(けちがん)」、その他は当った組により「阿波(あわ)」「土佐(とさ)」「伊予(いよ)」「讃岐(さぬき)」と下附します。
-
勝負は、最高得点者のうち、上席の方の勝ちとなります。
吹き始めた秋風が漂泊の想いを誘う季節となりました。
2年ぶりのコラム掲載となります。私こと昨年の晩秋(10/20〜12/3)に「四国八十八ヵ所歩き遍路」を敢行し、無事「満願」を果たしました。実は、一昨年の8月に「今月の組香」の定期掲載を中止したのも 、三百組の達成を機に、来る四国遍路のトレーニングを開始したからでした。完全文科系で仕事もデスクワークだった私は、最初は5kmの散歩から初めて、10km、20kmと距離を増やし、猛暑・荷重・登山 の訓練を加え、目標だった「10kgの荷物を背負い一日20km歩ける爺」の身体を作りました。
「何故遍路なのか?」と問われると、ただ「やってみたかったから」に尽きるかもしれません。仕事を完全リタイアして「金と暇と体力」があるうちに己を試したくて…できれば仏に会いたくて…だったのかもと思います。もともと修行フェチでしたので、出羽三山の「山伏修行」や大崎八幡宮の「裸詣り」の件をご存知の読者の方でしたら容易に納得いただけるかと思います。今年で「香道四十年」…絶えず「香」と向き合ってきた私も齢を重ねるにつれ、「香道の向こうに何があるのか?」を確かめたくなりました。古文書や知識では届かず、稽古の精進だけでも手の届かぬ何か…心の奥底にふと湧き出る「問い」に導かれ、「死ぬまでにやりたいことリスト」の1番に掲げられていた四国遍路を「老後」のスタートにしたかったのです。
四国遍路の道には、安い線香の香りとは裏腹に豊かな自然風土と人とが息づいていました。特に「施しの文化」が根付いた地元の人々の何気ない「声掛け」や「お接待」は、 積年の妬み・嫉み・恨み・辛みで凝り固まっていた私の心を「パッカーン!」と開いてくれました。特に強烈な記憶として残っているのは、宇和島の商店街の入口で出会ったヨレヨレ労務者風の爺様でした。 彼は、指で地面を差して無言で私を引き留め、小さな小銭入れを震える指でほじくり返し始めました。あまりに手間取るために煙草を咥えた口角からは涎が滴り落ち、何が何だかわからない私にとって、それはとても長い時間に思われました。そうして首尾よく硬貨「110円」をつまみ出した爺様は、それを私に握らせて、合掌する私を尻目に無言で立ち去りました。これは「自販機で缶コーヒーでも飲みなさい」という意味だと知ってはいましたが、「お遍路さんに施すことが功徳となることを信じている人々の想いを自分は託されているのだ」と思い知らされました。それまでの道中、金銭のみならず様々な温かい気持ちが差し出され、手を合わせてくださる皆さんの姿に感謝こそすれ、その方たちの想いを背負う気持ちのなかった私は、この瞬間に「ロングトレイル遍路」から「巡礼者」へとスイッチが切り替わりました。
「遍路」を開始した時から、私はもはや「香人」ではなかったのですが、結願も近いある日、八栗寺路にある「仁庵」という接待所のベンチに座っていたところをご亭主に「どうそ中へ」と誘われ、話の成り行きで「香人」で あることがバレて、茶室に招かれ手厚いお接待をいただきました。その際に、ふと「遍路は、単なる"道行き"ではなく、内なる感情や仏心の波が交錯する"心の風景"の総体なのだ」また、「香りは、目に見えない存在で、その姿形は個人の記憶や感情によって千差万別に形作られるもの…そう考えれば、香りも様々な因縁で今ここに存在するように見える"空(くう)"の世界なのだ」と気づきました。そうして旅を終え帰宅すると、手元に残ったのは、線香の煙のように細く真っすぐに立ち上がり、末は香りとともに千々に乱れて大気に溶けていく仏心でした。 そこで私は、そんな思いを景色にした組香をお世話になった四国の人々のためにも残しておきたいと思いました。
このようなわけで、今回は四国八十八ヶ所霊場を弘法大師と共に巡る新作組香「遍路香」(へんろこう)をご紹介したいと思います。
まず、この組香には「証偈(しょうげ)」というものを据えました。「偈」とは、仏徳の賛嘆や教理を述べたもので見た目は詩句の形式をとっていることから、従来通り「証詩」としても構わないのですが、この組香が仏行を精神的支柱に据えていることから、敢えて「証偈」という造語を編み出してみました。
「迷故三界城 悟故十方空 本來無東西 何處有南北」
読みは、「迷うが故に三界(欲界、色界、無色界 )は城なり 悟るが故に十方空なり 本来東西無し 何れの処にか南北有らん」です。意味は、「迷いがあるからこの世の至るところに欲望の城があるが,悟ってしまえば、十方は広々として何のさまたげもない空の世界だ。もともと空の世界に東も西もない。どこに南や北があるというのか。 」⇒世界はもともと自由奔放で、迷いの根源は人の心に在るのだということでしょう。
この偈は、お遍路さんの被る「菅笠(すげがさ)」に弘法大師を表す梵字「![]() 」と「同行二人」を挟んで四方に書かれています。出典を調べましたところ、明暦3年(1657)に臨済宗の天倫楓隠(てんりんふういん)禅師が編集した『諸回向清規(しょえこうしんぎ)』や同年、同宗妙心寺派の無著道忠(むちゃくどうちゅう)禅師の著した『小叢林清規(しょうそうりんしんぎ)』、さらに真言宗では、同年、井上忠兵衞、前川茂右衞門が刊行した『真言引導要集便蒙(しんごんいんどうようじゅうべんもう)』にも掲載があります。いずれも同年の刊行で書物の上ではオリジナルの判別はできないのですが、お遍路さんが真言宗の行であることから、ここでは、出典を『真言引導要集便蒙』としました。この四句の偈は、在家の葬式の際、僧侶が棺天蓋や骨壺に書いたものらしいのですが、出典巻八の「地取作法」では、「墓所の草を一丈ばかり払い、神供幣を五本立て、五穀を撒き供え、散杖で水を撒いた後、卒塔婆を五本用意し、中央は『梵字』、東方に『本来無東西』、南方に『悟故十方空』、西方に『何處有南北』、北方に『迷故三界城』と書いた卒塔婆を立てる」とあります。それが、四国遍路に派生して、巡礼、遍路の途中で亡くなった場合、偈の書かれた菅笠を身体にかぶせて棺桶の代わりとするようになったようです。このように、「証偈」は、遍路の途中で煩悩を滅し、「空」を悟って一切の苦厄から自らを解放されるためのスローガンのようなものと捉えていただければと思います。
」と「同行二人」を挟んで四方に書かれています。出典を調べましたところ、明暦3年(1657)に臨済宗の天倫楓隠(てんりんふういん)禅師が編集した『諸回向清規(しょえこうしんぎ)』や同年、同宗妙心寺派の無著道忠(むちゃくどうちゅう)禅師の著した『小叢林清規(しょうそうりんしんぎ)』、さらに真言宗では、同年、井上忠兵衞、前川茂右衞門が刊行した『真言引導要集便蒙(しんごんいんどうようじゅうべんもう)』にも掲載があります。いずれも同年の刊行で書物の上ではオリジナルの判別はできないのですが、お遍路さんが真言宗の行であることから、ここでは、出典を『真言引導要集便蒙』としました。この四句の偈は、在家の葬式の際、僧侶が棺天蓋や骨壺に書いたものらしいのですが、出典巻八の「地取作法」では、「墓所の草を一丈ばかり払い、神供幣を五本立て、五穀を撒き供え、散杖で水を撒いた後、卒塔婆を五本用意し、中央は『梵字』、東方に『本来無東西』、南方に『悟故十方空』、西方に『何處有南北』、北方に『迷故三界城』と書いた卒塔婆を立てる」とあります。それが、四国遍路に派生して、巡礼、遍路の途中で亡くなった場合、偈の書かれた菅笠を身体にかぶせて棺桶の代わりとするようになったようです。このように、「証偈」は、遍路の途中で煩悩を滅し、「空」を悟って一切の苦厄から自らを解放されるためのスローガンのようなものと捉えていただければと思います。
次に、この組香の要素名は「発心」「修行」「菩提」「涅槃」と「大師」としており、それぞれの意味は以下の通りです。
| 要素名 | 解釈 | 私の印象 |
| 発心 | 「発菩提心」と言い、悟りを得ようとする心を起こすこと 徳島県(23ヶ寺)を「発心の道場」と言う |
旅の始まりの不安と焦燥を鎮めてくれた森と朝露。遍路転がしの苦難と達成感 |
| 修行 | 悟りをめざして心身浄化を習い修めること 高知県(16ヶ寺)を「修行の道場」と言う |
広大な海と空の中、消えゆく自我との対峙した長い道程 |
| 菩提 | 煩悩を断ち切って悟りの境地に達すること 愛媛県(26ヶ寺)のことを「菩提の道場」と言う |
温かい人々のお声がけやご接待に心がほどける優しさ |
| 涅槃 |
煩悩の火を消し、智慧が完成し、一切の悩みや束縛から脱した、円満・安楽の境地のこと 香川県(23ヶ寺)のことを「涅槃の道場」と言う |
旅の終わりの安らぎと寂しさ。「ここからは、なるべく丁寧に巡ろう」と色々なものを目に焼き付けた日々 |
| 大師 | 則ち「弘法大師(空海)」のこと | ふと、お大師様の気配を感じた温かい空気 |
このように、この組香は、私がお遍路の道すがらで感じた様々な想いを皆様にも追体験していただけるように組んでみました。
さて、この組香の香種は5種、全体香数は12香、本香数は「八十八ヵ所」に掛けて8炉としています。構造は、構造式に書くと複雑なのですが、実際に手前をしてみると簡単だと思います。まず、「発心」「修行」「菩提」「涅槃」は各2包作り、「大師」は4包作ります。そのうち「発心」「修行」「菩提」「涅槃」の各1包を試香として焚き出します。試香は、四国遍路に旅立つ前に地図を見ながら心構えや身体作りをする「準備期間」だと思ってください。(因みに私はこの期間に約1年を費やしました。)試香が焚き終われましたら、香元は手元に残った「発心」「修行」「菩提」「涅槃」の各1包に「大師」を1包ずつ加えて結び置きします。すると本香は「発心+大師」「修行+大師」「菩提+大師」「涅槃+大師」の2包ずつ4組となります。これは、どんな時でもお大師様が傍らにいてくださる「同行二人(どうぎょうににん)」を表します。そうして、連衆は各々お大師様と二人で遍路旅を始めることとなります。本香は、組ごとに打ち交ぜて、1組目の結びを解いて更に打ち交ぜて焚き出します。2組目以降も同様にします。そうしますと、各組は「聞いたことのある香り」と「聞いたことのない香り」がペアでランダムに焚き出されることとなります。これは、道すがらお大師様の気配が不意に現れることを意味しています。こうして2包ずつ4組、都合8炉を焚き終えると香による遍路旅は終わります。
因みに、四国遍路は1〜88番まで「順序に一気に巡る」と決まったものではありません。「順打ち」「逆打ち」「区切り打ち」「通し打ち」…どのように区切り、組み合わせて も八十八ヶ寺を巡り終えれば「結願」…ご利益は変わらないとされています。そのため、例えば本香が「大師・涅槃」 「修行・大師」「大師・発心」「菩提・大師」と出てもそれはそのように巡ったということで、遍路旅に矛盾は生じないのです。但し、河野衛門三郎の伝説から「閏年に逆打ちをするとご利益は3倍!」という言い伝えはありますし、土地の人の話では「歩くかそうでないか」では値打ちが変わるそうです。
本香が焚き終わりましたら、連衆は名乗紙に要素名を出た順に、組ごとに区切って8つ書き記します。名乗紙が返って参りましたら、執筆は、連衆の答えをすべて書き写します。答えを写し終えたところで香元に正解を請い、香元はそれを請けて正解を宣言します。執筆はこれを聞き、解答欄の当った要素名に合点を掛けます。(この時点では偶然当った「大師」にも点を掛けて置きます。)合点を掛け終えましたら 、次は下附の段となります。
この組香では、下段に各自の成績を下附のみで表します。
「発心・大師」の組の当り 阿波(徳島)
「修行・大師」の組の当り 土佐(高知)
「涅槃・大師」の組の当り 伊予(愛媛)
「菩提・大師」の組の当り 讃岐(香川)
全中 結願
EX:正解が「大師・涅槃」「修行・大師」「大師・発心」「菩提・大師」の場合
客A「大師・発心」「修行・大師」「菩提・大師」「大師・涅槃」⇒土佐
客B「大師・修行」「大師・涅槃」「大師・発心」「菩提・大師」⇒阿波 讃岐
客C「大師・涅槃」「修行・大師」「大師・発心」「菩提・大師」⇒結願
下附は、香の出の前後に関係なく、2つとも当った組ごとに追記していく方式です。これは、区切り打ちで「無事に一国を巡り終えた」ことを表します。また、4組とも正解した場合は「結願(けちがん)」と下附します。「結願」とは、四国八十八ヵ所を巡り終えたという意味です。 なお、四国遍路の場合、「結願」の後に高野山奥の院にいらっしゃるお大師様に報告と御礼参りをすると「満願」となります。
この方式では、一組聞き外すと、入れ違いでもう一組も聞き外すこととなるので、3ヵ国の下附が附されることはありません。また、この組香に「片当り」は無く、地の香を聞き誤れば、客香の「大師」のみ聞き当てて「合点」は掛かっていても「同行二人」とはならないので、その組自体が外れとなります。(全員に下附がなく、どうしても優劣をつけたい場合は「大師」の当り数で決めることは可能です。)
最後に勝負は、「結願」と下附された方のうち上席の方が勝ちとなります。「結願」がない場合は、下附の数の多い方のうち上席の方を勝ちとします。
「遍路香」は、香気を地図として辿り歩き、焦りや苛立ち、勝負への欲すらも一つの真実と受け容れて心遊ぶ組香です。皆様もかつての私のように「形あるものは実体なきもの」であることに気付き、香気が悟らせてくれる「空」の世界に浸っていただければ幸いです。
香を通じて誰かの心に仏が灯るなら、それもまた一つの巡礼ですね。
私は、今も「果てなきお遍路さん」として香の道を歩いています。
涅槃にて思い果つるや香の道近き遠きは逃げ水のごと(921詠)
組香の解釈は、香席の景色を見渡すための一助に過ぎません。
最も尊重されるものは、皆さん自身が自由に思い浮かべる「心の風景」です。
![]()
Copyright, kazz921 All Right Reserved
無断模写・転写を禁じます。
