

十月の組香


![]()
源氏物語の「紅葉賀」の帖をテーマとした組香です。
段組による場面転換のあるところが特徴です。
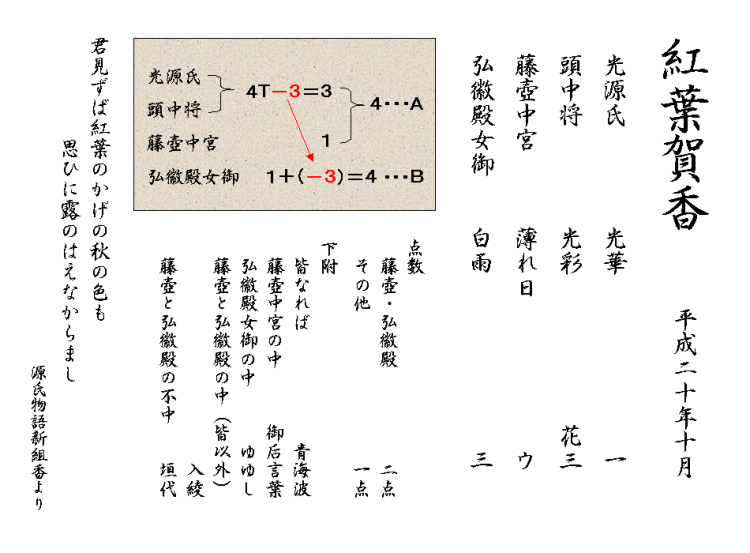
-年に1度の初心者用解説付きバージョンです。-
|
|
説明 |
|
香木は4種用意します。
要素名(ようそめい)は、「光源氏(ひかるげんじ)」「頭中将(とうのちゅうじょう)」「藤壺中宮(ふじつぼのちゅうぐう)」と「弘徽殿女御(こきでんのにょうご)」です。
※「要素名」とは、組香の景色を構成する名前で、この組香ではそのまま答えの名目としても使用します。
香名(こうめい)と木所(きどころ)は、景色のために書きましたので、季節感や趣旨に合うものを自由に組んでください。
※「香名」とは、香木そのものにつけられた固有名詞で、あらかじめ規定された要素名とは違って自由に決めることが出来ます。組香の景色をつくるために、香木の名前もそれに因んだものを使うことが多く、香人の美意識の現われやすい所です。
※「木所」とは、7種類に分かれた香木の大まかな分類のことです。(香木のコラム参照)
「光源氏」と「頭中将」は各4包、「藤壺中宮」と「弘徽殿女御」は各1包作ります。(計10包)
「光源氏」「頭中将」のうち、各1包を試香(こころみこう)として焚き出します。(計2包)
※「試香」とは、香木の印象を連衆に覚えてもらうために「光源氏でございます。」「頭中将でございます。」とあらかじめ宣言して廻すお香です。
「藤壺中宮」と「弘徽殿女御」は、ともに客香(きゃくこう)となります。
※「客香」とは、「試香」が無く、本香で初めて聞くお香のことで、古くは客が持参したお香のことを表していました。
試香で残った「光源氏」「頭中将」の各3包を打ち交ぜ(うちまぜ)て、任意に3包を引き去ります。(この3包はB段で使います。)
※「打ち交ぜ」とは、シャッフルのことで、香包を順序不同に混ぜ合わせることです。
手元に残った3包に「藤壺中宮」1包を加えて、打ち交ぜて順に焚き出します。(計4包)
本香(ほんこう)A段は4炉廻ります。
※「本香」とは、聞き当ててもらうために匿名で焚くお香です。連衆は、このお香と試香の異同を判別して答えを導きます。
※「A段」とは、本香を複数に大きく区切って焚き出す「段組」(だんぐみ)という方式の際に、最初の区切りである「初の段」を示す言葉です。
次に、先ほど引き去っておいた3包に「弘徽殿女御」1包を加えて、打ち交ぜて順に焚き出します。(計4包)
本香B段(後の段)も4炉廻ります。
本香が全て焚き終わったら、各自試香に聞き合わせて、名乗紙(なのりがみ)に香の出の順番に答えを要素名で8つ書き記します。
※「名乗紙」とは、各自が回答を記載して提出する「回答用紙」のことで、流派により「手記録紙」「記紙」とも言います。
執筆(しっぴつ)は、各自の答えを全て香記(こうき)に書き記します。
※「執筆」とは、組香の記録を書き記す担当の人です。
※「香記」とは、香席の景色全体を示す成績表のようなもので、最後に組香の勝者に授与されます。
香元(こうもと)は、香包(こうづつみ)を開き、正解を宣言します。
※「香元」とは、香席のお手前をする担当の人です。
※「香包」とは、香木の入った畳紙のことで、「試香包」と「本香包」に別れています。(ここでは「本香包」のこと。)
執筆は、正解した人の答えの右横に点を打ちます。
点数は、客香の当たりは2点、その他の香は1点と換算します。
下附(したづけ)は、各自の回答欄の下に所定のものを書き記しします。(委細後述)
※「下附」とは、各自の当たり方によって得点の 代わりに付される言葉です。
勝負は、各自の点数を合計し、得点の最も多い上席の方の勝ちとします。
秋の野山も色づいて、木々が一年の有終の美を飾っているようです。
私は、小さい頃からデザイン関係の仕事をしたいと思っており、「絵を描く、詩を書く、曲を書く」 の趣味が昂じて、いつかは総合的な差配のできるアードディレクターになりたいと思っていましたが、志半ばで挫折しました。まあ、これが功を奏して現在の安定した生活環境があるのですが、未だに「厳しい美意識」と「審美眼」 だけは失わずにいようと思っています。
先日、所謂「今どきのガールズファッションショー」を見ましたが、その中に全く「美しさ」を感じなかったのがショックでした。勿論、モデルも可愛いし、着られる服も可愛い・・・オマケに観客までもが可愛いのは間違いないのです。しかし、これらのプレタポルテには、「カワイイ」という「日本の最も新しい文化的価値観である」という理解以外には何も感じず、芸術的な感動などは全く覚えなかったのです。おそらく、このショーを見て携帯で「即買い」する若い女性たちも「カワイイ」とか「有名人と同じものを私も着たい」というような衝動や願望が購入動機なのでしょうが、「カワイイ」の視点もめまぐるしく変りますし、「有名人」は1回着て、ソコソコ売れれば次の商品に着替える余裕があります。第一、その娘自体が有名人とは外見も個性も違うのですから「土台無理!」ということもある わけです。しかし、売る側はそのことをおくびにも出さず、イベントのノリで売り抜くわけです。そこには、「旬」という「価値」があるだけで、「美」は存在していないように思えました。
「ファッション」とは元々が「流がれ行くもの」ですから、自ずと「時間とともに廃れる価値」であるという呪縛からは逃れられません。絶対に留めることのできない無料かつ無限のエネルギーである「時間の流れ」にわざわざお金をかけて竿を差すことは、「最も贅沢」と言えますが、庶民にとっては「最も虚しい努力」かと も思います。一流のファッションモデルでさえ、「私が掲載された雑誌は、僅か半年以内に「流行遅れ」として処分されています。これを見ると私の外見などは消耗品だと感じます。それでも時流のスピードにいつも着いて行こうとして心身ともに消耗してしまいました。」と語っています。時を追うことは疲れるのです。一方、歴史ある欧米のファッション業界の中には、普遍的な芸術性、機能美や素材感を指向するメゾンが今でも残されています。彼らの目指すものは、 「消費とは無縁な良質なもの作り」であり、そこには「飾る美」ではなく「磨く美」が輝いています。
日本は、この「磨く美」を大切にする民族です。皆さんも「掃き清められた座敷」「光り輝く水回り」「洗い立ての衣類」や「湯上がりの肌」に何も無くとも「美」を感じるでしょう。このように掃除や洗濯は「磨く美」の基本であり、そのために心身を磨く修行には欠かせない日課なのだと思います。また、用途によって磨かれた「機能美」、時代によって磨かれた「伝統美」なども無理無駄を省いた「磨く美」の賜物ではないかと思います。たとえ「飾る美」であっても、日本の「錺(かざり)」の文化とは、「よく磨いたところに、良く磨いたものを整然と配置する」ものであり、そこには「ボロ隠し」や「虚飾」の概念は存在しません。唯一、時を消費するものといえば、季節に因んだ調度と花を選ぶことぐらいですが、これは、最小の心遣いで最大の効用をもたらす美意識です。
また、「磨く美」の中には「物理的な美」と「精神的な美」があると思います。まず、「物理的な美」に関していえば、形あるものは全て「磨く」ことができ、磨かれることでその真価を発揮することができます。ステンレス製品のように「新しいこと」が求められるものは「真っ新(まっさら)」にして、その素材を剥きだしにしてやれば良いですし、茶釜の蓋のように「時代を踏まえて尚も輝く美しさ」が求められるものは、そのように
使用感を積み重ねるように優しく撫でてやりましょう。
次に、「精神的な美」は、年月や経験、その人の思いの深さを礎にして磨くものかと思います。「磨かれてできる美しい心って何だろう?」と考えると、もう1コラム書けそうなほど
深遠なテーマですが、端的に言い切るとすれば「行儀」と「礼儀」だと思います。この道を進めば、「親切」「丁寧」「尊敬」から始まって、「自律」し、「謙虚」を得て、自ら「安寧」の境地に達し、自他共に「許容」するに至る全ての「徳」を積むことができるような気がします。その際に磨き落とされるべきものとは、「物心両面から来る飢餓感を埋めようとして、何でもかんでも求めてしまう・・・悪あがきの衝動」のようなものでしょうか?先ほどのファッションモデルは、時の呪縛から離れ、心の美へ転向することで「謙虚と安寧を覚えた」と行っていますので、精神的にもかなり大人だったことがわかります。
結局のところ、「素材」の欠点を飾って覆い隠していては、問題は何も解決せず、素材を磨いて生成りで光り輝けなければ、「本当の美」は得られないと言うことではないでしょうか?このことは、人間の生き方としても、世界のあり方としても正しいのかなと思います。
今月は、『源氏物語』においても、これほどの美の表現はないという光源氏の舞い姿「紅葉賀香」(もみじのがこう)をご紹介いたしましょう。
一方、同名の組香は、『香道蘭之園(八巻)』の「光源氏千種香」にも掲載があり、香道界ではこちらの方が一般的です。どちらの組香も源氏物語の「紅葉賀」をテーマとして、光源氏と頭中将が「青海波」を舞うシーンを切り取った景色であることは共通していますが、構造的には全く異なるため同名異組といえましょう。
① 要素名は「紅葉」「菊」(各5包試香あり)に「舞」(2包無試)を用意します。
② 試香の終わった「紅葉」「菊」(各4包)に「舞」(2包)を加えて打ち交ぜます。
③ 本香は、10包を2*柱1組として、5組焚き出します。(計10炉)
④ 回答は、あらかじめ用意された9種類の聞の名目から1組ずつ選んで、5つの聞の名目で答えます。
この組香は、『香と香 道』(香道文化研究会編)にも『香道蘭之園』を典拠とした掲載がありますが、その中で「昭和乙卯年(1975)神無月旬日」に催行された「紅葉賀香記」に、今回の新組の作者である「出香 武子」「執筆 久美子」と御家流桂雪会とみられる大御所の名前が見られることも興味深いことです。『香道蘭之園』に掲載のある「紅葉賀香」は、10月の定番として多くの香席やお稽古で催行されている組香であり、ネット上の組香解説にも「時雨香」と同様に多く見られ、言い尽くされた感も否めません。そこで、今回は敢えて登場人物の人間模様が直接的に交錯する『源氏物語新組香(上)』を出典として書き進めたいと思います。
まず、『香道蘭之園』の「紅葉賀香」にも言えることですが、この組香には証歌がありません。敢えて「紅葉賀」の帖の前段で詠われた和歌を取り繕えば「物思うに 立ち舞ふべくもあらぬ身の袖打ち振りし心知りきや」(貴女を想うために、立派に舞うことなどはとてもできそうもないわが身が、一心に袖を振って舞った気持ちはお分りいただけたでしょうか?)と光源氏が藤壺に 贈った歌が思い当たります。しかし、この組香は、単に二人の関係のみならず、光源氏を中心とする頭中将、弘徽殿女御、桐壺院との相関関係や右大臣家と左大臣家との対立といった大きなテーマが内在するため、この歌だけでは言い尽くせないものがあります。そこで、今回、小記録には、『源氏物語』からの引用ではなく、出典の「紅葉賀香」の扉に掲載されている歌を参考としてご紹介しています。
ここで、組香の説明に入る前に、この組香の舞台となる「紅葉賀」のあらすじをご紹介しておきましょう。
『源氏物語』第7帖は、光源氏18歳の冬10月から19歳の秋7月までの宰相兼中将時代の物語です。
「紅葉賀」の帖は長文なので、この組香の舞台となっている章を中心に概略をご紹介します。
第一章 光源氏、藤壷の御前で青海波を舞う
[第一段 御前の試楽]
朱雀院(すざくいん)への行幸は、十月十日過ぎに催されますが、通常の行幸と違って格別な興趣のある催し(上皇の算賀)なので、桐壺帝も藤壷が見られないのを物足りなく思って、試楽(予行)を行うことにしました。
光源氏は御前で左大臣家の頭中将 (とうのちゅうじょう)を相手として、「青海波(せいがいは)」を舞い、あまりに素晴らしく趣深いので、帝をはじめ皆も感涙を流しました。詠吟が終わって舞の袖を直している光源氏の姿が夕日に映えて美しく輝いて見えたのを春宮の女御(弘徽殿女御)は、心穏やかならず妬ましく思って、「神などが空から魅入りそうな容貌ですね。おぉ嫌だ。不吉だ。」と言いました。
一方、藤壷は、「大それた恋心さえなかったら、お姿がもっと素晴らしく見えたのに・・・」と思いつつも、夢心地でした。
試楽が終わった夜、帝が「今日の試楽は『青海波』の素晴らしさに尽きましたね。貴女はどうでしたか?」と尋ねると、藤壷は、答えにくそうに「格別でございました。」とだけ返事をしました。帝は「貴女に見せたい一心で用意させたのですよ」と言って、藤壷を心から愛しく思っている様子でした。
[第二段 試楽の翌日]
光源氏から藤壷に「どのようにご覧になったでしょうか?乱れた想いのまま舞いましたが・・・」と手紙があり、「物思うに・・・」の歌が書かれていました。藤壺が、「唐人の袖振ることは遠けれど、立ち居につけて哀れとは見き」(唐の人が袖を振って舞ったという故事は遠い昔のことですが、貴方の舞の立ち居姿は、しみじみと拝見しました。)と返歌すると、光源氏は、「もう既に、皇后様に相応しい品格があるなぁ。」と微笑まれて、大切に持経のように広げて見入っていました。
[第三段 十月十余日、朱雀院行幸]
行幸の当日には、宮中をあげて親王などが残らずお供しました。 先日の光源氏の姿があまりにも素晴らしかったので、帝は鬼神に魅入られはしまいかと不吉に思って、寺々に誦経などをさせたことを聞いた人々は「もっともなこと」と感じていましたが、弘徽殿女御は、それを「大げさ だ」と非難していました。
紅葉の木陰で40人の垣代(かいしろ:青海波の舞楽の楽人)は、言葉に表せないほど素晴らしく、楽の音に併せて吹く松風も本当の深山颪(みやまおろし)と聞こえる程に吹き乱れ、色とりどりに散り交じる木の葉の中から輝き出る「青海波」は、なんとも恐ろしいまでに美しく見えました。光源氏の挿頭の紅葉が散ってしまい、顔の美しさに圧倒された感じもするので、左大将が御前の菊を手折って頭飾りを差し替えました。美しい菊を頭に挿した光源氏の姿と手を尽くして舞われた「入綾」(いりあや)は、ゾクっと寒気がするほど美しく、この世の事とも思えない程で、知識のない下々の者どもでさえ、皆、感涙に咽びました。(『香道蘭之園』の「紅葉賀香」はこの景色をテーマとしています。)
その夜、このような舞いの功もあって、光源氏の中将は正三位になり、頭中将は正四位に昇格しました。
[第四段 葵の上、光源氏の態度を不快に思う]
藤壷は、宮中を退出していましたので、光源氏は藤壷に逢える機会もあろうかと、様子を伺って歩き回っていました。その上、幼い若草の君(若紫)を引き取ったことを「二条院では、新しい女性を迎えたようだ」と誰かが伝えましたので、正室である葵上は、たいそう不愉快に思っていました。光源氏も「素直に恨み事を言ってくれれば、説明して誤解を説き、慰めもしようものを・・・」と思いつつ、葵上の穏やかで思慮深い気性からして、「まぁ、いつか自然に思い直してくれるだろう」と格別な信頼を寄せているのでした。その後、この帖の第二章では、光源氏が引き取った紫の君に心慰める光景が描かれ、第三章では、いよいよ藤壷が男皇子(後の冷泉帝:光源氏の子)を出産して内裏に入ります。続く、第四章は、閑話休題といったところでしょうか、光源氏が50歳過ぎの典侍(ないしのすけ)との好色事件で頭中将と応酬し合います。そして、第五章で、めでたく藤壷は中宮となり、光源氏は宰相となり、その子も人望と寵愛を集め帝位への道を磐石としていきます。
以上のように、この組香は「紅葉賀」の帖、第一章の「試楽」と「行幸当日」の場面を舞台としています。
次に、この組香の要素名は「光源氏」「頭中将」と「藤壺中宮」「弘徽殿女御」となっています。「光源氏」と「頭中将」は永遠の友でありライバルです。前段では舞い姿を比べられますし、後段の好色ごとでは、老いた典侍を取り合ったりもするのですが、いつも「光源氏」が優位に評価されているといった関係です。この組香では、左方(唐楽)二人舞である「青海波」の舞人として「光源氏」と「頭中将」を捉えらるのが順当ですが、香をランダムに打ち交ぜて、香数を「1対1」と固定させていないことから考えると、広くは匿名化された他の曲の舞人や楽人のことも含んでいるものと思います。「藤壺中宮」は光源氏がみちならぬ恋に走ってしまった「藤壺の女御」のことで、第一章の場面では未だ「女御」であり、帝の御宿直などを勤めているのですが、要素名では既に「中宮」となっています。「中宮」となるのは「紅葉賀」の最終章なので、若干気が早いとも感じますが、後世の人からすれば「藤壺中宮」でも違和感はありません。「弘徽殿女御」は、原文では「春宮の女御」と書かれています。右大臣家の出身で、左大臣家とは敵対関係にあるので、左大臣家の光源氏が何かにつけて褒められれば褒められるほど「悔しい~!」という関係にあり、事あるごとに様々な嫌味を仕掛けて来ますが、最終章で藤壺が中宮となってからは、権勢が衰えて いきます。
続いて、この組香の香種・香数は4種10香、本香8炉となっています。「光源氏」と「頭中将」は舞楽の舞人として同数が用意され、互いがまだ同等であることを表しています。また、「藤壺中宮」と「弘徽殿女御」は、それぞれ1包ずつ用意され、それぞれの場面で「帝」以外の主客として取り扱われています。
さて、この組香の第一の特徴は、「段組」があることです。「光源氏(4包)」「頭中将(4包)」と「藤壺中宮(1包)」「弘徽殿女御(1包)」を用意し、「光源氏」「頭中将」を試香で各1包ずつ焚き出します。試香が終わったところで残った「光源氏(3包)」「頭中将(3包)」を打ち交ぜて、そこから3包を任意に引き去ります。この「任意に引き去り」によって、舞人の数に偶発性が生まれ、その数の多少によって「どちら舞が優れていた」というように解釈するのも趣向の一つとなります。そのため、各段の地の香(客香以外の香)が「光源氏だけ」もしくは「頭中将だけ」と焚かれてしまうのは味気ない景色となりますので、この点については香元が注意すべきかと思います。
そして、最初の3包に「藤壺中宮(1包)」を加えて打ち交ぜ、都合4包を「本香A段」として焚き出します。これは、帝が行幸の当日に参席できない藤壺のために、特別に予行して見せてやろうという取り計らいがなされた「試楽」の場面を表します。即ち、この試楽の主客は「藤壺中宮(1包)」ですので「客香」(初客)として扱われています。この試楽は、原文に「御前にて、せさせたまふ。」「入り方の日かげ、さやかにさしたるに」とありますので、おそらく夕方の清涼殿の前庭が舞台ではないかと思います。ここで舞われた「青海波」が帝をはじめ観衆の感涙を誘い、藤壺も光源氏の姿に夢心地となります。
試楽の夜に帝が藤壺に「見せたてまつらむの心にて、用意せさせつる。」と言う場面があるので、明らかに「試楽」の主客は藤壺だったということが確認できます。因みに、「試楽」の場面でも「弘徽殿女御」が登場しますが、光源氏のすばらしさに少し嫌味を言うだけに留まっています。
次に、残った3包に「弘徽殿女御(1包)」を加えて打ち交ぜ、都合4包を「本香B段」として焚き出します。こちらは、行幸の当日、朱雀院の庭ので催された「紅葉賀」の場面を表します。この日は、藤壺は参席していないため、帝以外の主客を「弘徽殿女御」と設定して「客香」(後客)として扱っています。こちらは流石に本番ということもあって「楽の舟ども漕ぎめぐりて、唐土、高麗と、尽くしたる舞ども、種多かり。」と贅を尽くした舞台であったことが読み取れます。また、原文に「日暮れかかるほどに」とありますので、こちらも夕方の興行であったことが分かります。ここで舞われた「青海波」は、流石にすばらしく「そぞろ寒く、この世のことともおぼえず。」と評価され、「下人どもの・・・すこしものの心知るは涙落としけり。」とその感動が生半可でなかったことが分かります。
このように、この組香では、「試楽の日」と「行幸当日」の2つの場面を段組によって表し、光源氏と頭中将の「青海波」を見る「藤壺中宮」と「弘徽殿女御」のそれぞれの心音を味わう趣向となっています。
この組香では、基本的に名乗紙に回答を一括して書き記す「後開き方式」を採用しており、本香が焚き終わり次第、連衆は、香の出た順に「A段、B段」に分けて、要素名を4つずつ書き記して提出します。出典では、要素名が長いので「源」「中」「弘」「藤」と略すように記載されています。(敢えて申せば「頭中将」の「中」が「藤壺中宮」と混同しやすいので「頭」でもよろしいかと思います。)
なお、出典には香札を使用する「札打ち」(ふだうち)を想定した記述があります。その場合は「十種香札」を流用して「一(3枚)を光源氏、二(3枚)を頭中将、三(1枚)を藤壺中宮、客(1枚)を弘徽殿女御と定める」とあり、連衆の熟達度によって「札打ち」で行えば、後の訂正が効かない分だけ緊張感も高まります。(ただし、組香の段組の趣旨からして、1炉ごとに正解を開く「一*柱開」には馴染まないと思いますので、正解の宣言は、最後に一括でよろしいかと思います。)
名乗紙が戻ってきましたら、執筆は各自の回答を全て「源」「中」「弘」「藤」と略して香記に書き記します。転記が終わって、香元が正解を宣言しましたら、執筆は当たりの要素の右上に
合点を掛けて示します。
点数は、客香である「藤壺中宮」と「弘徽殿女御」については2点の加点要素があり、試香のある「光源氏」と「頭中将」の当たりは1点ですので、満点は10点となります。
この組香では、主に「客香」の当否によって様々な「下附」が用意され、得点に関わらず 、下記のように書き記すこととなっています。
① 全問正解は「青海波(せいがいは)」と書き記します。
物語の中で「光源氏中将は、青海波をぞ舞ひたまひける。」とあり、ここで舞われたのは、「青海波」であることが分かります。青海波は、左方舞、盤渉調(ばんしきちょう)の雅楽曲で、二人の楽人が鳥兜を被り、紅葉や菊を挿頭(かざし)にして、千鳥螺鈿の太刀を帯び、青海波模様のついた下襲に千鳥の袍の片肩を脱いで、ゆったりと袖を振りながら波が寄せ返す様子を表す非常に優美な舞で、中世以降の堂上の公達が好んで舞うことが多かったといいます。源氏物語の中でも青海波が再三登場するため、このことによって、雅楽の中でも有名な曲となったということです。
因みに、「青海」とは中国西北地区の青海省の地名であり、正式には「輪台」を序として、これに続けて舞う「破」にあたる舞であるため、「青海波は、もともと青海破だった。」とも言われています。このことを新井白石は、正徳元年(1711)に著した『楽考』の中で、「唐の世青海舞あり、統秋云、此曲序四遍を輪台といひ、破七遍を青海波と云、按ずるに青海波は則青海破なるべし。」と書いています。
② 藤壺中宮が当たれば「御后言葉(おきさきことば)」と書き記します。
試楽の翌日に光源氏に和歌を返した歌を見て「かやうの方さへ、たどたどしからず、ひとの朝廷まで思ほしやれる御后言葉の、かねても」と光源氏が感心して微笑む場面で登場する言葉です。
本来の意味は、「皇后が使う言葉」のことで、ここでは、藤壺の知性と教養から出る「言葉の様子が皇后らしい」ということでしょう。この言葉は、藤壺の人となりを端的に表すとともに、「試楽(A段)」の場面を締めくくる言葉ともいえましょう。
③ 弘徽殿女御が当たれば「ゆゆし」と書き記します。
試楽の日に光輝く光源氏の舞姿を見て皆が感涙に咽んでいる時、弘徽殿女御が妬ましく思って「神など、空にめでつべき容貌かな。うたてゆゆし」と言い放った際に登場する言葉です。「ゆゆし」(斎斎し)は、神聖なものに対する「恐れ多い」から派生して「すばらしい」「立派」という良い評価にも使われる言葉ですが、ここでは、「不吉である。縁起が悪い。恐ろしい。気味が悪い。」という意味で用いられており、弘徽殿女御の光源氏に対する感情の核心を表しているといえます。また、この言葉が元になって、帝は行幸の当日まで方々の寺に祈祷をさせて厄を払わせていますので、非常に重い放言であったことが分かります。
④ 藤壺中宮と弘徽殿女御を両方とも当てているのに、他を間違えている場合は「入綾(いりあや)」と書き記します。
行幸の当日の舞について「今日はまたなき手を尽くしたる入綾のほど、そぞろ寒く、この世のことともおぼえず。」と評価されている場面で登場する言葉です。「入綾」とは、当曲舞が終わり、再度同じ楽曲を演奏すると、一部の舞人は舞いながら後面向に一列になって順次降台しますが、主役は舞い続けるという作法のことで、現代風に言えばアンコールのようなものかと思います。これは、主役の「藤壺中宮」と「弘徽殿女御」は、まだ香の舞台に立っているのに舞人(「光源氏」「頭中将」等)の一部は舞台から降りてしまって見えないという景色を表すものと考えます。因みに出典には「組香の主要なものは聞いているのに不均、他をはづしているので今一度よくお聞きなさい」という意味のアンコールであるとも書いてあります。
⑤ 藤壺・弘徽殿を両方とも間違えて、他が当たっている場合は「垣代(かいしろ)」と書き記します。
行幸当日の演者について「垣代など、殿上人、地下も、心殊なりと世人に思はれたる有職の限りととのへさせたまへり。」と、どれ程厳選した舞人や楽人を用いたかを示す場面で登場する言葉です。「垣代」とは、左方舞である「輪台」、「青海波」の時に舞台の後ろに並ぶ者の呼称で、先ほどの「入綾」で降台する群舞用の舞人のことです。また、その後ろに立って奏した楽人などを「垣代楽人」とも呼び、基本的には主役を囲む「人垣」のような扱いで用いられています。このことから、香の舞台に舞人(「光源氏」「頭中将」等)ばかりが見えて、主役の「藤壺中宮」「弘徽殿女御」は人垣に紛れて見えないという景色を表すものと考えます。因みに出典にも「ワンサの方ばかりで肝腎なものは見てゐないと同様に思われる処から」この言葉が用いられたと書いてあります。
以上、解説が長くなりましたので、おさらいの意味で下附の例を①~⑤の順に示します。
|
本香 |
A段 |
B段 |
下附 |
点数 |
||||||
|
一 |
二 |
三 |
四 |
一 |
二 |
三 |
四 |
|||
|
香の出 |
源 |
中 |
藤 |
源 |
弘 |
中 |
源 |
中 |
||
|
例① |
源 |
中 |
藤 |
源 |
弘 |
中 |
源 |
中 |
青海波 |
10 |
|
例② |
源 |
中 |
藤 |
中 |
中 |
源 |
源 |
弘 |
御后言葉 |
5 |
|
例③ |
源 |
藤 |
中 |
源 |
弘 |
中 |
源 |
中 |
ゆゆし |
7 |
|
例④ |
中 |
中 |
藤 |
中 |
弘 |
源 |
源 |
源 |
入綾 |
6 |
|
例⑤ |
源 |
藤 |
源 |
源 |
中 |
中 |
弘 |
中 |
垣代 |
4 |
※ 下線部の当たりは2点と換算します。
最後に、この組香は、「青海波」以外は、下附が同じでも当り方によって得点が様々異なりますので、下附に関わらず、改めて各自の得点を計算し、最高得点の上席の方を勝ちとしてください。
それにしても「空恐ろしいほどの美」とはどんなものなのでしょうか?
私は、未だ「本当の美」を知らないのかもしれません。
組香の解釈は、香席の景色を見渡すための一助に過ぎません。
最も尊重されるものは、皆さん自身が自由に思い浮かべる「心の風景」です。
![]()

Copyright, kazz921 All Right Reserved
無断模写・転写を禁じます。