十月の組香

雄大に拡がる大海原をテーマにした組香です。
証歌の表す景色を存分に味わって聞きましょう。
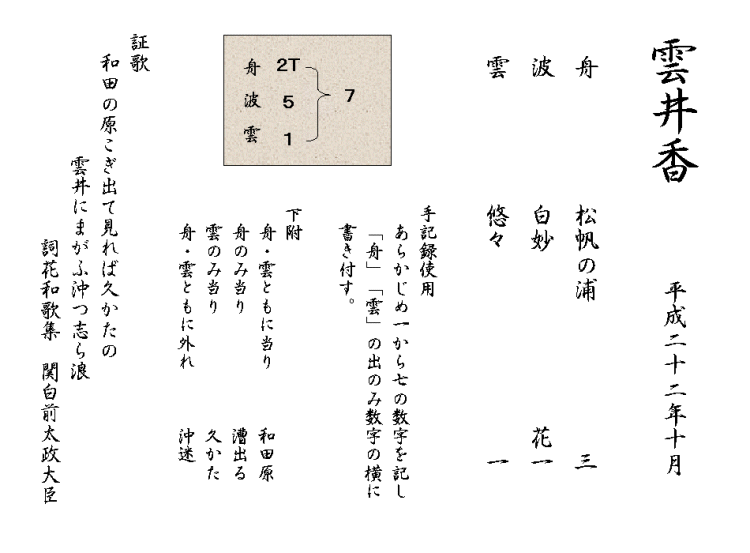
−年に1度の初心者用解説付きバージョンです。−
|
|
説明 |
|
1. 香木は3種用意します。
2. 要素名(ようそめい)は、「舟(ふね)」「波(なみ)」と「雲(くも)」です。
※「要素名」とは、組香の景色を構成するためにそれぞれの香に付された言葉です。
3.
香名(こうめい)と木所(きどころ)は、景色のために書きましたので、季節感や趣旨に合うものを自由に組んでください。
※「香名」とは、香木そのものにつけられた固有名詞で、あらかじめ規定された要素名とは違って自由に決めることが出来ます。組香の景色をつくるために、香木の名前もそれに因んだものを使うことが多く、香人の美意識の現われやすい所です。
※「木所」とは、7種類に分かれた香木の大まかな分類のことです。(香木のコラム参照)
4. 「舟」は2包、「波」は5包、「雲」は1包作ります。(計8包)
5. まず、「舟」のうち1包を試香(こころみこう)として焚き出します。(計1包)
※「試香」とは、香木の印象を連衆に覚えてもらうために「舟でございます。」とあらかじめ宣言して廻すお香です。
6. 「波」と「雲」は、ともに客香(きゃくこう)となります。
※「客香」とは、「試香」が無く、本香で初めて聞くお香のことです。
7. 次に、試香で残った「舟」1包に、「波」5包と「雲」1包を加えて打ち交ぜ(うちまぜ)ます。(計7包)
※「打ち交ぜ」とは、シャッフルのことで、香包を順序不同に混ぜ合わせることです。
8. 本香(ほんこう)は7炉廻ります。
※「本香」とは、聞き当ててもらうために匿名で焚くお香です。連衆は、このお香と試香の異同を判別して答えを導きます。
9. 本香が全て焚き終わったら、各自試香に聞き合わせて、名乗紙(なのりがみ)に答えを書き記します。(委細後述)
※「名乗紙」とは、各自が回答を記載して提出する「回答用紙」のことで、流派により「手記録紙」「記紙」とも言います。
11. 執筆(しっぴつ)は、各自の答えを全て香記(こうき)に書き記します。
※「執筆」とは、組香の記録を書き記す担当の人のことで連歌の世界では「しゅひつ」と読みます。
※「香記」とは、香席の景色全体を示す成績表のようなもので、最後に組香の勝者に授与されます。
12. 香元(こうもと)は、香包(こうづつみ)を開き、正解を宣言します。
※「香元」とは、香席のお手前をする担当の人です。
※「香包」とは、香木の入った畳紙のことで、「試香包」と「本香包」に別れています。
13. 執筆は、「舟」と「雲」を正解した人の答えの右横に点を打ちます。
14. この組香に点数はありません。
15. 下附(したづけ)は、「舟」「雲」の両方が当たった場合は「和田原(わたのはら)」、「舟」のみの当りは 「漕出る(こぎいずる)」、「雲」のみ当りは 「久かた(ひさかた)」、「舟」「雲」ともに聞き外した場合は「沖迷(おきまよう)」と書き記します。
※「下附」とは、各自の当たり方によって得点の代わりに付される言葉です。
16. 勝負は、下附の上位者のうち上席の方の勝ちとします。
長〜い酷暑もやっと一段落し、野山の夏枯れが秋色に溶けてまいりました。
先日、月山に登った日の夜、突然私の携帯が鳴り、大昔に所属していた「劇団の主宰」から「今度の芝居に出てほしい」とのオファーがありました。彼女は、「この芝居のこの役は君しか思い浮かばない。君が出てくれなかったらこの芝居は打たないつもりだ。」と演出家の常套句を駆使して私をタラシコミました。
私に与えられた役は、皆様もお馴染み「モッキンポット師ふたたび(井上ひさし著)」の「モッキンポット神父」です。「守銭奴」のごとくでもあり、「許しの権化」のようでもあり、とりあえず風采の上がらないワイン好きの貧乏神父・・・主宰の脳裏では、そんなことはどうでもよく「関西弁の堪能なフランス人」というキャラクターが私のイメージと重なったらしく、即日、団員に捜索願を出したということらしいです。
私は、役人として「不夜城」に戻ったばかりですので、役者として何処をどう都合をつけて深夜の稽古に勤しむのか・・・?実のところ全く見当はついていないのですが、なんだか話を聞いているうちに「これだけ忙しければ、もう自分がどうなるものか、心身の地平線を越えてみるのも面白いんじゃない。」と思えるようになり、ついには「OK!」と安請け合いしてしまいました。
思えば25年前、「疾走する劇空間」と新聞に評された我が劇団は、「東京キッドブラザース」系のノリで高校生を中心に人気を集め、公演のない時期は、コンサートやストリートパフォーマンス、デパートのイベントに明け暮れたものでした。当時のギャラは劇団に支払われており、我々はどこまでもアマチュアだったのですが、地元テレビの出演をきっかけにレギュラー出演も決まり、個人としてのギャラが発生したところで、役人と役者の二足の草鞋をはいていた私には「兼業の禁止問題」が発生し、芝居から身を引いたという経緯です。この年の10月、私は歌手を目指す女優と恋に落ち、彼女の歌う劇中歌「海のブルース」がとても好きでした。そのためか劇団というと、今でも「このまま〜泳ぎたい〜♪あなたの海は荒れている〜♪何処までも〜漂いぃながら、流されてぇ行きたいのよぅ〜♪」と演歌のようなこの歌が脳裏を巡ります。退団以来、「コアな観客」として関わっては来ましたが、まさか体躯の衰えを自他ともに認めるこの歳になってからの「出演」とは・・・神は私に何を求めておられるのでしょうか?
今回の企画は、仙台市や文化事業団の主催する「杜の都の演劇祭2010」で、街角のカフェや喫茶店を舞台にリーディング(台本を持ったままの芝居)を「飲み食い」しながら楽しみ、「"おなか"も"こころ"も、満たされる」というコンセプトとなっています。なんでも今年は「井上ひさしメモリアル」がテーマということで、氏の著作が8人の演出家の手法により演じられるようです。他会場の作品では、玄人さんの俳優や劇団主宰クラスが目白押しのキャスティングなので「契約」も取り交わすらしいし、公式サイトには写真も載るらしい・・・こちらは25年ぶりの素人ですから、いまさらながらに自分の浅はかさを痛感しています。演劇祭は12月から1月の2カ月間行われ、各会場の公演期間は1週間ほどあります。かなりな長帳場で体調管理にも気をつけなければなりませんが、「欲しいのは36℃の波の音♪」・・・「無視されて生きるよりは、多忙の中で気高く死ぬ」方が私らしいので、ここは一番頑張ってみるつもりです。
今月は、何処に居ても雄大な大海原を思い起こす「雲井香」(くもいこう)をご紹介いたしましょう。
「雲井香」は、聞香秘録の『香道秋の最中』に掲載のある組香です。この組香は、御家流系では「百種組」、志野流系では「外組(雑)」として、ほぼ同じ形で現存しており、昭和の刊行本である『香道の作法と組香(長ゆき著)』に掲載されているためか、現代の香席でもしばしば用いられています。「海」のイメージがあるためか、多くの場合「春・夏」の組香として催されているようですが、この組香は『香道秋の最中』に収録されており、その巻名と目次の流れを勘案すると、本当は「秋の組香」として掲載されたのではないかと思います。確かに小記録の景色からも「秋」という風景は取り立てて伺えませんし、証歌も「雑歌」に分類されていますので季節感は問わなくとも良いとは思うのですが、今回は『香道秋の最中』を出典として、敢えて「秋」の組香としてご紹介いたしましょう。
まず、この組香は、出典に「和田の原こき出て見れば久かた乃雲井にまかふ沖つ志ら浪 この歌にて組める香なり。」とあり、証歌に基づいて創案された組香であることが厳然と分かります。この歌は、皆様もお馴染みの「小倉百人一首」の76番の歌で、11番の「わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと 人には告げよ海女の釣舟(古今集407 参議篁)」 と間違いやすく、最も決まり字の長い「六字札」として印象に残っているかと思います。
原典を探りますと、「新院位におはしましし時、『海上遠望』といふ事をよませ給けるによめる」との詞書に続いて「わたのはら漕ぎ出でてみれば久かたの雲ゐにまがふ沖つ白波(詞花集382 関白前太政大臣)」との記載があります。意味は「広い海原に舟を漕ぎ出して、はるかに見渡すと、沖に立ち騒ぐ白波は天空の白雲と見紛うばかりであるよ」ということで、「題詠」にも関わらず水天一色の景観を生彩に豊かに歌い上げている秀歌です。
「わたの原」の「わた」とは、海を指す古語で当て字は「海の原」と書き、広い海や大海原を指す言葉です。また、「久方の」は、「天」「空」「月」「雲」「雨」「光」等、主に大空になどにかかる語で、ここでは「雲」にかかる枕詞として使われています。さらに「雲ゐ」とは基本的には「雲居(雲のあるところ)」から「空」または「雲」そのものを表す言葉で、題号の「雲井」はその当て字です。
因みに、詞書にある「新院」とは、崇徳院のことで「新」とは鳥羽上皇に対する言葉です。また、詠人の「関白前太政大臣」とは藤原忠通(ただみち)のことで、百人一首では、「法性寺入道関白前太政大臣」と示されています。藤原忠通(1797〜1164)は、26歳で関白家を継ぎ左大臣(従一位)となりましたが、温厚な人柄で人を遇するに篤く、政治的手腕も優れていたため、鳥羽、崇徳、近衛、後白河の4朝に仕えました。文化的にも和歌・漢詩・書道をよくし、彼の歌は、『金葉集』以下の勅撰集に69首選ばれています。
次に、この組香の要素名は「舟」「波」「雲」となっており、大海原の風景を現す最小限の要素となっています。海であれば、「陽光」「風」「松」や「藻塩の煙」などの景色もありますが、そのような雑景を一切排除して、雄大な「青と白の世界」の視覚化に徹したところに証歌の「体言止め」に通じる潔さがあります。
この組香の主景は、泰然と流れる「雲」と立ち騒ぐ「波」が水平線を隔てて動静の対比を見せているところにあります。そこに連衆が各々漕ぎ出す「舟」が配置され、これによって絵葉書のように出来すぎた構図のバランスが乱れ、景色にドラマ性と生気を帯びさせることとなります。この組香の景色は、いわば「雲井香盤」とも言えるものであり、連衆が波と雲の交わる水平線を目指して各々漕ぎ出した舟が「どの辺まで達するか?」を観念的に意識させるものとなっています。
さて、この組香の構造は至って簡単です。まず、「舟」は2包、「波」は5包、「雲」は1包作ります。そのうち「舟」の1包を試香として焚き出します。「舟」は連衆にとって双六の「我がコマ」にような乗り物ですので、試香は、その聞き味を確かめて「始業点検」する意味ではないかと思います。次に、手元に残った「舟(1包)」「波(5包)」「雲(1包)」の7包を打ち交ぜて順に焚き出します。ここで、「舟」と「雲」は、どちらも1包ずつしか出現しませんが、試香と聞き合わせれば「舟」の判別は可能ですから消去法で「雲」にも目星をつけることが出来ます。一方「波」と「雲」はどちらも「試香の無い香」ですので、これにより「雲ゐにまがふ」という景色を呈することとなります。しかし、この組香では、景色の構成要素としての分量も香数として考慮されているため、「雲(1包)」以外は全て「波 (5包)」ですので良く聞き込めば「香数」の違いで結果的に判別は可能と言うことになっています。この組香における厳密な意味での「客香」は「雲」であり、「波」は「星合香」の「仇星」の如く、「舟」や「雲」の聞き当てを阻害する要素として扱われているものと思われます。
このように、香数を配慮して判別しなければならないこともあることから、この組香の回答は「名乗紙を用いた後開き」方式で行われます。そのため、香元が本香を焚き終えたところで、連衆は、各自の答えを名乗紙に書き出します。その際、出典では「名乗りに始めより一二三四五六七と書付け置きて、右出香終りて舟の香、雲の香の出たると思う所へ書きそえ出す。」とあり、下図のように、あらかじめ書いた炉の番号に「舟」と「雲」の聞きのみ並記するという回答方法が指定されています。確かに、「舟」と「雲」を聞き当てれば、結果的に「波」も当ったことになるので合理的とも言え、この回答方式がこの組香の最大の特徴と言えましょう。
名乗紙の記載例
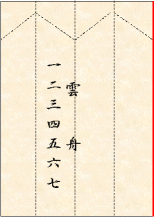
名乗紙が戻って来ましたら、執筆はこれを開き、「常の如く」連衆の回答を香記に書き記します。
この組香では、「舟」と「雲」が当れば「波」は全て当たり、「舟」や「雲」が間違えていれば「波」はそれぞれ入れ違いで間違っていることが自明となっていますので、「波」については合点を掛けず、「舟」と「雲」の正否のみを確かめて当った要素に点「ヽ」を打ちます。
ここで、出典の「雲井香之記」では、全問正解のみ全ての要素に点「ヽ」が打ってありますが、他の人の「波」の当りには点が無いので奇異に感じられます。因みに、『香道の作法と組香』では、「舟」と「雲」だけに点が打ってあり、全問正解でも点は2つなので、こちらの方が矛盾無く理解できるかと思います。
続いて、この組香には点法の記載がなく、各自の成績は点数によらず「舟」と「雲」の当りパターンに対応した下附で示すこととなっています。
出典には・・・
舟雲とも嗅当たる下には 「和田原(わたのはら)」と書く
舟ばかり嗅当たる下には 「漕出る(こぎいずる)」と書く
雲ばかり嗅当たる下には 「久かた(ひさかた)」と書く
舟雲とも嗅はづしたる下には「沖迷(おきまよう)」と書く
・・・とあります。
「和田の原」は、全問正解を意味しますので、証歌の景色が全て反映されたことを示し、大海原と雲の境目まで舟が進んだ景色が想像されます。
最後に勝負は、下附の上位者のうち上席の方の勝ちとするのが順当でしょう。下附の順位は、前述のとおり「雲(客香)の聞き当て」を優先して、「和田原」→「久かた」→「漕出る」→「沖迷」の順が妥当かと思います。
秋の組香の主役が「赤」や「黄」に彩られた「紅葉香」「龍田香」とすれば、「雲井香」は、秋色の対極をなす「青」と「白」の大海原の組香といえます。紅葉狩りの中休みに山荘で開香すれば、聞く人の脳裏に雄大な大海原が広がって異次元トリップができるかもしれません。「今はもう秋ぃ♪、誰もいない海ぃ♪」が思い浮かぶアンニュイな秋に、ふと海が恋しくなったら是非「雲井香」をおためしください。
江戸時代には「雲井香」という有名な「白粉(おしろい)」があったらしいです。
名前の由来は、おそらく「白色」と「フワフワ感」からの発想でしょうが
鉛白粉にどんな賦香がしてあったのか興味が湧きます。
組香の解釈は、香席の景色を見渡すための一助に過ぎません。
最も尊重されるものは、皆さん自身が自由に思い浮かべる「心の風景」です。
![]()
Copyright,
kazz921 All Right Reserved
無断模写・転写を禁じます。
